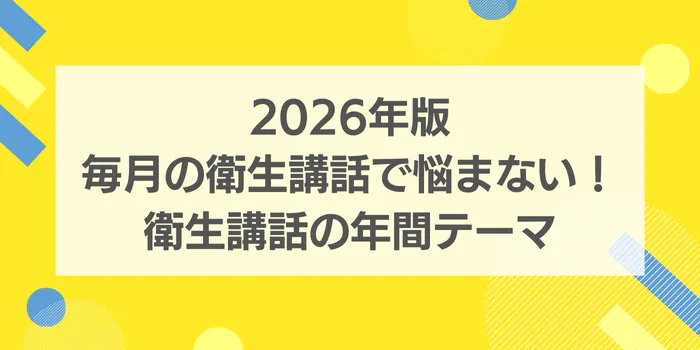
毎月実施しなければならない衛生委員会。講話テーマに悩んでいませんか?
さんぽLABでは、すぐに使える講話資料を80種類以上ご用意しております。
本ページでは衛生講話の1年間のスケジュール例とテーマに合わせた講話資料をダウンロードいただけます。
【目次】
1.衛生講話とは
ア.生活習慣病
イ.メンタルヘルス
ウ.両立支援
エ.女性の健康
カ.高年齢労働者
1. 衛生講話とは
衛生講話とは、産業医(または産業保健スタッフ)が、健康管理や衛生管理を目的に、安全衛生委員会で実施する短時間の研修のことです。衛生講話には法的な実施義務はなく、事業所で独自に行う活動です。安全衛生委員会で毎月実施している事業所もあれば、隔月で実施している事業所、実施していない事業所もあります。
(その他、安全衛生委員会とは別の機会に、従業員向けに行う健康教育のことを「産業医の講話」や「衛生講話」と呼んでいる事業所もあります。ここでは安全衛生委員会で実施する衛生講話について説明します。)
衛生講話を行う目的には、①社員に対する健康教育や情報提供、②事業所の安全衛生活動のキーパーソンとなる労使のメンバーへの健康教育や情報提供、③産業医・産業保健スタッフの顔を知ってもらい相談しやすい関係を築くこと、などがあります。ただし、安全衛生委員会に出席しているメンバーは社員の一部にすぎませんので、主に②や③を目的と考えることが適当でしょう。
テーマは、講話を担当する専門職が一方的に決めるのではなく、事業所側のニーズにあわせて選定するとより効果的です。季節のテーマや健康診断結果の活かし方、感染症対策、ストレスチェックの活用法やメンタルヘルス対策など、事業所で課題になっていることに関する幅広いテーマを取り入れるとよいでしょう。
衛生委員会の基本知識については別途記事を出しております。
2. 脱マンネリ テーマ選びのコツ
テーマ選びのポイント
1.事業所側と話し合ってテーマを決める
2.個人が特定されることがないよう配慮する
3.幅広いテーマ(メンタル・フィジカルの疾病予防、労働災害の防止、季節の話題、法改正等)を選ぶ
事業所が抱えている問題の解決につながるようなテーマの設定を心がけましょう。特定の話題に集中することもありますが、花粉症対策、感染症対策、熱中症対策など季節に応じた話題や、事業所で行う健康診断やストレスチェックなどと関連した話題など、さまざまな話題を取り上げてもよいでしょう。ぜひこの後紹介するカレンダーを基に、季節にあったテーマを事業所側に提案し、話し合ってはいかがでしょうか。
さらに、講話のなかでは、疾病予防、労働災害防止の観点だけでなく、労働生産性や働きやすさの向上につながる内容を盛り込むと、健康管理や衛生管理を取り組む目的が明確になり、事業所側に『役に立つ』と感じてもらうことができます。
例)花粉症
症状が悪化すると従業員の生産性が下がり、経営にどのような損失があるのかを伝える。
生産性に関わる要素を伝えた後、症状を軽減する方法を伝える。
3. 衛生委員会の年間スケジュール
衛生講話の年間スケジュールの一例をご紹介します。衛生講話のテーマに悩んだ際は是非参考にしてみてください。また、健康だよりの作成にもご活用ください。
その季節に合わせた、従業員の関心が向きやすい内容で実施するとよいでしょう。
| 月 | 衛生講話テーマ① | 衛生講話テーマ② |
|---|---|---|
| 1月 | ・肩こり/腰痛予防 | ・レジリエンス |
| 2月 | ・花粉症 | ・生活習慣病 |
| 3月 | ・働く人に多いメンタルヘルス不調 | ・女性の健康保持・増進に向けた取り組み |
| 4月 | ・新人への接し方~ラインケアについて~ | ・定期健康診断 |
| 5月 | ・熱中症対策 | ・禁煙対策 |
| 6月 | ・気象病 | ・運動習慣 |
| 7月 | ・夏バテについて | ・安全配慮義務 |
| 8月 | ・飲み物の注意点 | ・ストレスチェック制度 |
| 9月 | ・睡眠の問題について | ・集団分析 |
| 10月 | ・インフルエンザ | ・長時間労働 |
| 11月 | ・ヒートショック | ・職場でのハラスメント対策 |
| 12月 | ・正しいお酒との付き合い方 | ・糖尿病 |
4. 2026年におすすめのトピック
ア. 生活習慣病
定期健康診断における有所見者率は、年々増加傾向であり、健診結果に基づく適切な保健指導や事後措置の実施が重要です。生活習慣病は通年を通して啓発が必要なテーマであり、定期健康診断実施後や、2月の「全国生活習慣病予防月間」、9月の「健康増進普及月間」に合わせて情報提供するのはいかがでしょうか。
講話資料:生活習慣病
イ. メンタルヘルス
厚生労働省の労働安全衛生調査(令和6年)結果によると、仕事において強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者は68.3%でした。メンタル不調や休職といった問題につながるリスクも高く、企業としてメンタルヘルス対策は急務であり必要不可欠と言えるでしょう。
また、これまで従業員50人未満の事業場はストレスチェックが努力義務でしたが、2025年5月の法改正により全ての事業場に義務化(※)されることとなりました。これからストレスチェックを開始する企業の体制整備にはもちろん、毎年実施してきた企業も現状に合わせた方法の見直しや今後の対策に、ストレスチェックの講話はいかがでしょうか。
※公布後3年以内に政令で定める日から施行
講話資料:ストレスチェック
参考資料: 労働安全衛生調査(令和6年)
その他、職場で多いメンタル不調やラインケアなども通年お勧めのテーマです。
講話資料:働く人に多いメンタルヘルス不調
講話資料:ラインケアの基礎知識
ウ. 両立支援
法改正により、2026年4月1日から職場における治療と就業の両立を促進するため企業が必要な措置を講じることが努力義務となりました。
病気と仕事の両立支援とは、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら働き続けることを指します。社内の理解を深め、両立支援の体制構築に向けて必要な対策を検討しましょう。
講話資料:治療と仕事の両立支援~体制構築~
講話資料:職場復帰後のサポート
▼詳しく学ぶ
エ. 女性の健康
労働力の確保や男女平等による女性活躍、生産性の向上、健康経営などさまざまな観点から、女性特有の健康課題に対する企業の認識が高まりつつあります。しかし、女性の健康についての知識が不足しているのが現状で、企業で男女ともに学ぶ機会があることで、お互いにとって働きやすい職場づくりにつながるでしょう。
講話資料:女性の健康保持・増進に向けた取り組み
講話資料:女性の健康
講話資料:男女の更年期障害
オ. 職場における多様性
企業では、全ての労働者が安全で健康に働けるようにサポートする必要があります。一定割合の障がい者を雇用する法定雇用率は増加傾向にあり(2024年:2.5%→2026年:2.7%)、近年ではLGBTQや外国人労働者への理解も高まっています。衛生委員会で話し合うことで理解を深め、全ての労働者にとって働きやすい環境へとつなげていきましょう。
▼詳しく学ぶ
法令チェック:障害者雇用と合理的配慮
参考記事:LGBTQ+とは~産業保健の立場から考える性の多様性~
参考記事:障害を抱える人への支援~合理的配慮の提供、建設的対話について解説
カ. 高年齢労働者
法改正により、2026年4月1日から高年齢労働者の労災防止措置が企業の努力義務となります。
高齢化や医療の発達により、働く高齢者は増加していますが、一方で労働災害の割合は年々増加しており、企業では加齢に伴う身体機能の変化に応じた対策が求められます。
これを機に高年齢労働者に配慮したエイジフレンドリーな職場づくりを目指しましょう。
講話資料:高年齢労働者の健康管理
▼詳しく学ぶ
法令チェック:高年齢労働者の健康管理
■関連記事
作成者:さんぽLAB運営事務局 保健師
監修:難波克行先生









ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは
衛生委員会のテーマ、毎月すごく悩まされています。
医療機関なので、健康に関する知識がある人が多いので、ハラスメント、メンタルヘルス関連のテーマに偏ってしまいます。
委員会参加者に意見を求めると、ただの愚痴になってしまい、なかなか難しいです。
情報を取り、工夫しながら頑張っています。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示さんぽLAB事務局様
いつも素敵なサイト運営をいただき、誠にありがとうございます。
年間のヘルステーマで悩むこともある中で、とても参考になる情報をありがとうございます。
2点ほどうまくリンク先に飛べず、もし可能でしたらご確認いただけますと幸いです。
6月 食中毒をクリック→花粉症にジャンプ
12月 ヒートショック→本ページにジャンプ