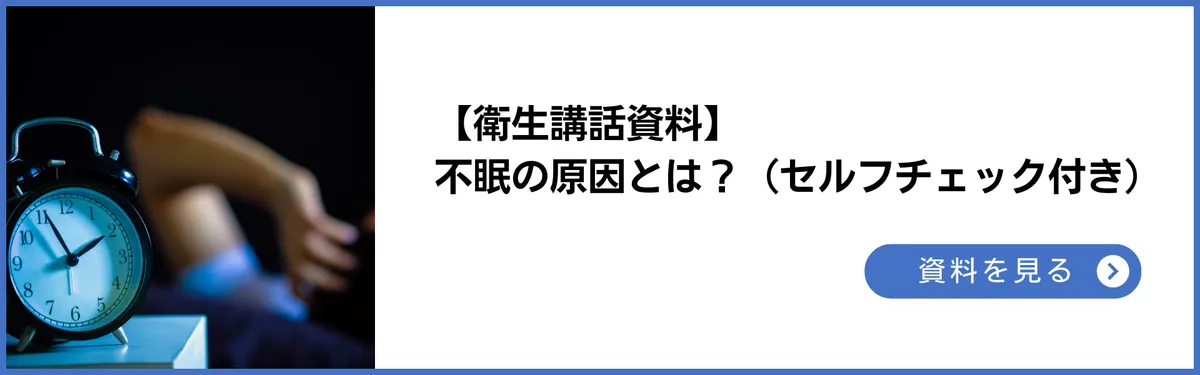夜勤や交代勤務を含む不規則な働き方は、睡眠障害やメンタル不調、生活習慣病などの健康リスクを高めることが知られています。こうした勤務形態が避けられない職場では、企業としてどのような対策を講じるべきなのでしょうか。本記事では、夜勤・交代勤務がもたらす健康影響や、衛生管理者が担うべき健康支援のポイント、企業の具体的な取り組み事例をご紹介します。従業員の健康と生産性を守るためのヒントを、ぜひお役立てください。
<目次>
1.夜勤・交代勤務が健康に与える影響
2.夜勤・交代勤務者の健康リスク対策
3.企業での成功事例と衛生管理者の役割
4.まとめ:夜勤・交代勤務者の健康を守るために
1.夜勤・交代勤務が健康に与える影響
主に24時間稼働が必要な業務やサービスを提供している業界では、夜勤や交代勤務が発生します。例えば医療・福祉業界、製造業、運輸・物流業界、警察・消防・救急、IT・テクノロジー業界、飲食業界、小売業界、メディア・放送などマスコミ業界、ホテル・観光業界、エネルギーなどインフラ関連事業などです。これらの業種では24時間体制を維持するために、シフト勤務を活用しながら夜勤や交代勤務を実施しています。交代制勤務に関しては厚生労働省の労働者健康状況調査によると、我が国の労働者のうち10~20%を占め、特に製造業において高いと言われています。
2交代制、3交代制などシフト形態は様々ありますが、いずれにしても日勤と夜勤をローテーションしながら働く不規則な勤務形態となるため、生活リズムが乱れることにより様々な健康リスクが発生します。
最も代表的な課題は睡眠障害です。体内リズムの変調により睡眠ホルモンとも呼ばれている、睡眠・覚醒のリズムを調整する役割があるメラトニンの分泌が乱れることにより起こります。生活リズムの乱れによりサーカディアンリズムと言われる体内時計の乱れと併せて睡眠不足の状態が続くと、自律神経のバランスも乱れやすくなり、それらの要素が複合的に原因となり、疲労感の蓄積、集中力や注意力の低下、頭痛といった日常的な心身の不調を引き起こします。また、交代勤務に従事していない人と比較して、交代勤務従事者はメタボリックシンドロームの発症リスクが1.06倍、心血管系疾患の発症リスクが1.15倍増加することが報告されています(健康づくりのための睡眠ガイド2023より抜粋)。さらに乳がんや前立腺がんなどの悪性腫瘍、うつ病、認知症の発症リスクが高くなるという報告もあります。時には命に関わる重篤な疾患へつながってしまうこともあるということです。
このような健康リスクを避けるため、夜勤・交代勤務を行っている職場では、適切なシフト制度やサポート体制を整え、健康管理を行うことが重要です。
2.夜勤・交代勤務者の健康リスク対策
夜勤・交代勤務者の健康リスク対策には、シフト制度や睡眠環境の整備、健康管理、運動、メンタルヘルスのサポートが必要です。これらの対策を組み合わせて実施することで、従業員の健康を守り、職場全体の生産性向上にも繋がります。職場として、従業員の健康を最優先に考えた取り組みが求められています。
まず最も重要なのはシフトの工夫です。長時間同じ時間帯の夜勤を続けることは、上述したようにサーカディアンリズムを乱し健康に悪影響を及ぼします。夜勤のシフトはできるだけローテーションシフトを取り入れ、勤務時間帯を適切に調整することが推奨されます。夜勤後は最低でも数日間の休息を取れるようなローテーションを組み、週に数回の昼間勤務を設けることで昼夜逆転を避け、体内リズムを少しずつ調整できるようにします。
また、不規則なシフト勤務だからこそ、長時間労働も問題になってきます。勤務時間前後に時間外勤務を行っていると、特に3交代制勤務の場合などは次の勤務までの休息時間が十分に確保できないことにつながります。この数年、一般労働者においては長時間労働の是正が必要であることに理解が深まり、だいぶ状況が改善されつつあります。一方で各労働者の業務負担を減らすために管理監督者の負担が増え、過重労働が懸念されています。管理監督者には労働基準法の労働時間の上限規制が適用されず、残業時間や休日に関する法律の制限も受けないため、労働時間や残業時間に実質上限がない状況にあるからです。2019年4月に施行された働き方改革関連法に伴い、労働安全衛生法が改正され、こういった管理監督者の勤怠管理も義務化されました。これを行うのが労働時間管理者で、企業内の管理監督者の勤怠管理を行う人を指し、主に企業の人事部門や総務部門の担当者が担います。衛生管理者はそういった職種と協力し、事業場の全労働者の勤務時間が適正な範囲にあるのかを把握しておけるとよいでしょう。過度な状況で勤務しているような労働者がいれば、健康管理の観点から介入することが良さそうです。
こちらの衛生講話資料は裁判例をもとに長時間労働の問題を解説しています👇
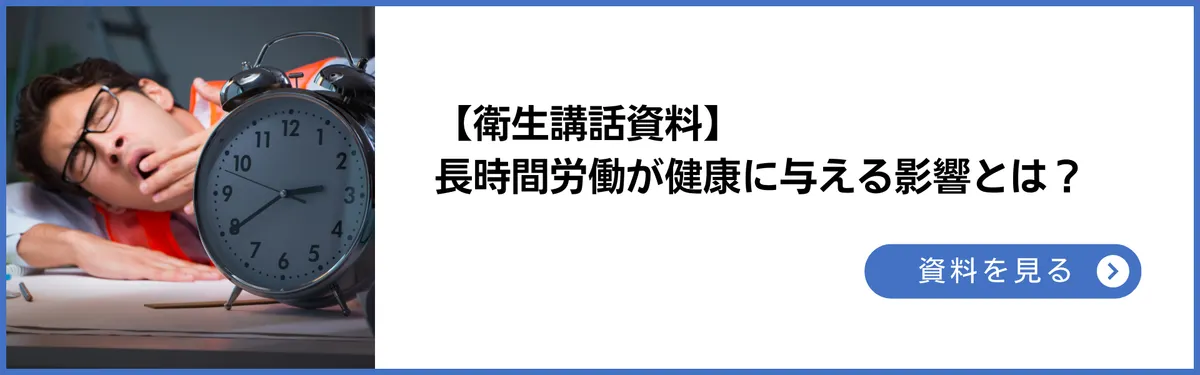
次に、事業場の設備という観点で、仮眠室や休憩室など、睡眠環境を整備することも健康リスクの軽減に役立ちます。夜勤中の仮眠は、仕事の効率も改善させることがわかっており、0~4時に開始する20~50分間の仮眠は、眠気や仕事効率を改善し、疲労対策に効果があることが報告されています。休息をしっかりとるためには静かであること、光の刺激が抑えられた落ち着いた空間であることが重要です。作業場とは離れた静かな環境で、必要に応じて遮光カーテンなども備えた仮眠室や休憩室を整備できると良いでしょう。また、事業場の整備という観点からだけでなく、衛生管理者は労働者への指導として睡眠について介入しサポートができるとベターです。例えば仮眠前にコーヒーなどでカフェインを摂取しておくとカフェインの覚醒効果により仮眠後の覚醒が容易になるとともに、睡眠慣性(睡眠から覚醒状態に切り替わるときに起こる、一時的なぼんやりや眠気、けだるさの状態のこと)も生じにくくなるという報告もあります。こういった事柄を取り入れた睡眠の指導については、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023)」も参考にしてください。
その他、衛生管理者が直接的にできることとして、食生活の改善や運動の推奨などの労働者自身が取り組めるような健康管理のサポートの提供があります。同様にメンタルヘルス対策も衛生管理者が主体的に行えることの1つです。産業医や保健師と連携を取り、適宜指導の場やカウンセリングの場を設けたり、ストレスチェックを行ったりすることが必要です。また、健康管理の一環として健康診断の受診を促すことも非常に重要です。労働基準法では、夜22時~翌朝5時の時間帯の勤務は深夜労働と定められており、この時間帯での勤務を過去6か月間の平均で1か月あたり4回以上行う従業員が「深夜業に従事する労働者」とされます。事業者はこのような労働者に対し、当該業務への配置換えの際、および6か月以内ごとに1回、定期的に健康診断を受けさせる義務があります。シフト制等の夜勤の場合だけでなく、23時までの残業など深夜業に該当する時間帯の勤務が常態的に行われていれば、同じく対象となります。
また、健康診断実施後には、労働者が夜勤や交代勤務を行っていることを産業医に伝え、労働者の健康維持と労働環境の改善につながるようなフォローアップを実施することも必要です。
こちらは変則勤務者向けの食事アドバイスをまとめたリーフレットです👇
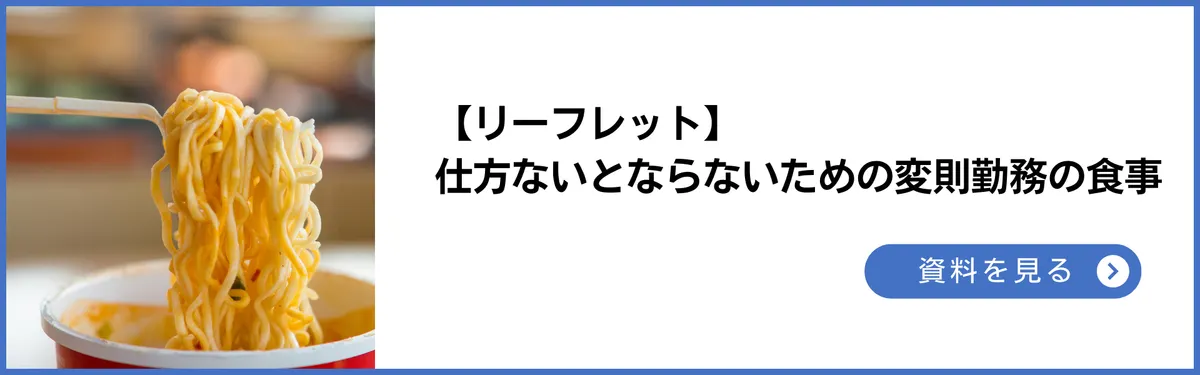
3.企業での成功事例と衛生管理者の役割
A社では、不規則な勤務体系で働く従業員の睡眠を充実させて事故や生産性低下の予防を目指しています。
「睡眠」「運動」「喫煙」等の主要な取り組みに分けて健康経営戦略を実施しており、特に交代勤務がある社員を優先して毎年3グループに分けて睡眠改善プログラムを提供しています。特に、シフト勤務や社泊などの特殊なスケジュールで勤務せざるを得ないことがある部署は健康リスクも高いと産業医との共通認識があり、優先的に睡眠改善プログラムを提供しています。
この睡眠改善プログラムでは、主観アンケートと睡眠計測デバイスによって取得された客観的な睡眠データで、対象者が抱えている睡眠課題や傾向を特定し、その睡眠課題の解決に有効とされる生活習慣の定着と行動変容をすることで、その課題を解決に導くヘルスケアサービスが提供されています。実施した労働者からは、「寝付けないことが少なくなりスムーズに睡眠を行えるようになった」「睡眠習慣を整えることにより、毎日を有意義に過ごすことができると感じた」といった声が聞かれており、「入社して間もなく交代勤務に従事する社員にも参加してもらい、自身の健康を守るための睡眠のとり方をコントロールできるようになってもらいたい」という意見も聞かれています。
このようなプログラムを導入する際には、プログラムの遂行が円滑になるよう、トップを巻き込んだり、職場単位で実施するなど、事業場が一体となって取り組むことが成功のカギと言えるでしょう。
衛生管理者は、意思決定を行う経営層とプログラムを提供する労働者個人との間の橋渡し的な役割を担うほか、職場全体で積極的に取り組めるような体制・雰囲気づくりに貢献する必要があります。
4.まとめ:夜勤・交代勤務者の健康を守るために
夜勤・交代勤務者は睡眠、食事など生活の基本的な部分に変則が生じ、心身への負担が大きくなることで健康リスクが高まることがあります。事業場として環境や制度を整えることと、労働者自身への指導といった両方の側面から健康をまもるためにサポートすることが求められ、特に衛生管理者は後者の労働者自身への関わりの部分で大きな役割を担う存在となります。
■参考
■執筆/監修
<執筆> 衛生管理者・看護師
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』