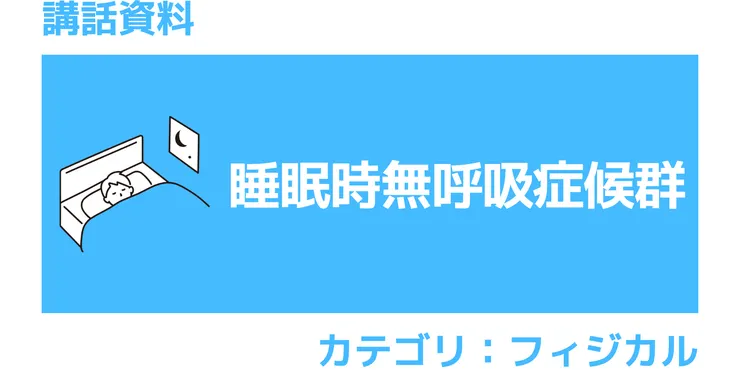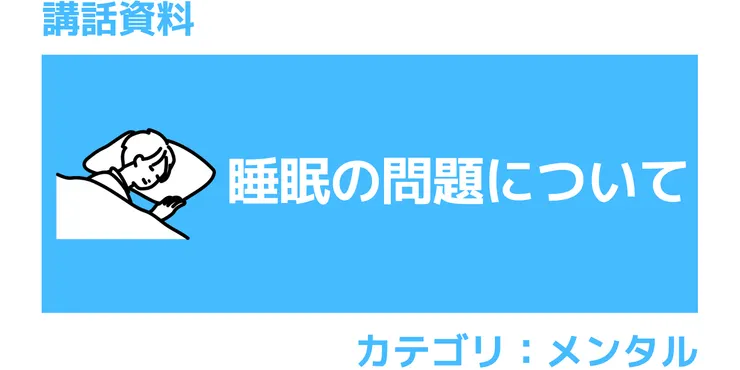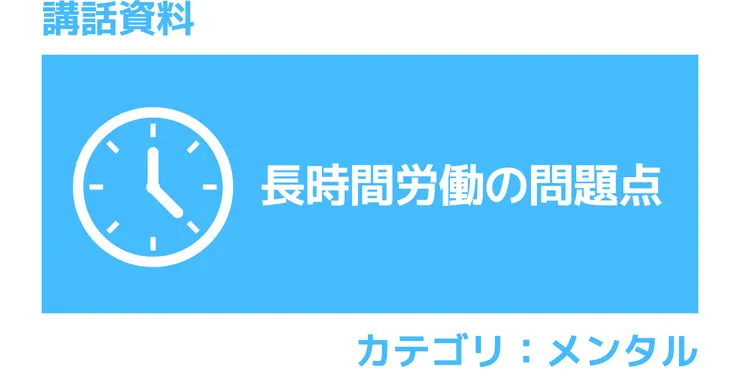産業医が学ぶべき「睡眠マネジメント」— 石田陽子(睡眠社会学の第一人者)が語る健康経営の視点
<目次>
1. 産業医が【睡眠マネジメント】を学ぶ意義
2. 睡眠の法則1:睡眠はサーカディアンリズムの1日1回、7~9時間を核とする
3. 睡眠の法則2:人間は睡眠と覚醒、どちらかしかできず、睡眠中は意識がない
4. 産業保健に活かす【睡眠マネジメント】
5. 黄金の90分をマネジメントする
6. 産業保健視点ですぐに着手できるデータ的【睡眠マネジメント】
1.産業医が【睡眠マネジメント】を学ぶ意義
成人の半数以上が有業者で、その多くが業務に関連して費やす時間は、1日の3分の1以上です。だからこそ、労働者が健康に就労できるような支援を行う産業医の存在意義が大きいのは当然です。同じ文脈で、全成人が3分の1程度、こどもはそれ以上の時間を費やす睡眠の健康を支援するのは、産業保健同様、医師にとって非常に重要な使命です。
令和4年度改定医学部モデル・コア・カリキュラム(文部科学省)は293ページありますが、「産業保健」は目次と索引を入れて単独で13回登場する一方、「睡眠」は薬物中毒のカッコ内の「睡眠薬」の一部として1回のほか、「睡眠時無呼吸症候群」という疾病名の一部として、本文と索引に1回ずつ登場するのみです。就業と睡眠をあわせて1日の3分の2以上の時間を占めるというのに、医学生や医師がそれを学ぶ機会が少ないというのは由々しき問題だと考えています。
このたび、標準生理と社会医学を習得し、産業保健の知識と経験を有する、現役で活躍する産業医の先生方に、【睡眠マネジメント】についての情報を提供する機会を得て、私はとてもワクワクしています。産業医面談ではよく、従業員の「仕事と睡眠しかしていない」という声を聞きます。
それならなおさら、産業医にとっての【睡眠マネジメント】は、まさに「鬼に金棒」です!
お伝えしたいことが多すぎて、とても入り切らないのですが、この記事で睡眠に関心を持ってくださった方は、ぜひ、私の著書、「Dr. Yokoの睡眠マネジメント 眠るほど、ぐんぐん仕事がうまくいく」(文芸社, 2025)を読んでください。また、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(厚生労働省, 2024)(以下、「睡眠ガイド」)は無料でダウンロードできますので、先生方の産業保健業務にお役立てください。
私が提唱する【睡眠マネジメント】は、社会のルールである24時間周期の時計に従いながら、体内時計が司る時間生物学的に健康な睡眠を確保するためのテクニックです。
社会的なルールに従いながら、生物学的な健康をマネジメントする産業保健とは、相性抜群です。
2.睡眠の法則1:睡眠はサーカディアンリズムの1日1回、7~9時間を核とする
生物学的に健康な人間のシンプルな睡眠法則の第一として、睡眠は1日1回、成人では7~9時間を核とする連続する時間が必要です。「核とする」という表現は、「睡眠ガイド」から引用しました。就業のコアタイムを超えて残業している人はたくさんいますが、コアタイムより短い就業時間の場合は、時短勤務という別の特殊な勤務です。睡眠も同様で、コアタイムより長いより、短いほうが特殊です。
人間は、体内時計によって、毎日、最適な時間の睡眠時間を取る能力があります。図1の研究の被験者は、実験前に約7時間半睡眠という習慣でしたが、社会の時間の影響を排除した環境で12時間臥床を続けた結果、4日間かけて睡眠負債を返済し、中央値8時間25分の最適な睡眠に落ち着きました。
TST(Total Sleep Time)は、脳波や交感神経活性などによる他覚的な睡眠検査(PSG)によって測定される生物学的な睡眠で、このTSTに睡眠潜時や中途覚醒を加えた、眠ろうとして寝床に入った就寝時間から起きようと思って寝床から出た起床時間までのTIB(Time in Bed)より短くなります。
TIBに対するTSTの割合が睡眠効率で、85%以上が標準です。中途覚醒がなくても、睡眠潜時は15分程度必要なので、97%以上にはなりません。睡眠効率は高いほどよいのですが、睡眠負債があるのに睡眠時間が短い場合は、健康とは言えない睡眠なのに睡眠効率は上がりますので、睡眠効率単独では、睡眠の評価はできません。
アンケートなどで回答される睡眠時間は、当然、TSTよりTIBに近づきます。睡眠効率を85%とすると、図1の第4日から第10日のTIBは、10時間近くなります。
しかし、この連日8時間25分の睡眠を睡眠日誌にしてみると、図2の非24時間睡眠覚醒症候群のように、毎日、眠る時間が、約1時間ずつ後退していきます。なぜなら、人間のサーカディアンリズム(概日時計:1日を刻む体内時計)は、社会の時計よりも1時間ほど長いことが多いためです。
本能に任せれば、サーカディアンリズム上、規則正しい睡眠時間になるのですが、文明の生み出した社会の時計で見ると、その生物学的に美しい睡眠リズムには、病名がついてしまうのです。
そのため人間は、体内時計と社会の時計の約1時間の時差を、毎日、【睡眠マネジメント】で調整しなければなりません。
3.睡眠の法則2:人間は睡眠と覚醒、どちらかしかできず、睡眠中は意識がない
次に、健康な人間には覚醒か睡眠のどちらかの状態しかありません。睡眠中は意識がないので、生物としては非常に危険ですし、外敵と戦えないのはもちろん、生殖や摂食、排泄という生命活動もできません。それでも進化の過程で睡眠がなくならないのは、睡眠にそれだけ意味があるからです。
回遊魚や渡り鳥の一種は半球睡眠ができますが、人間は睡眠か覚醒かしかできないので、簡単に覚醒から睡眠に移行しないために、複雑で厳重なメカニズムがあります。
具体的には、いくら眠くても、いくら睡眠負債が嵩んでも、いくら寝てもいいような退屈な時間でも、「睡眠にふさわしい環境で」、「横になって(臥位)」、「目を閉じて、じっとして、15分以上かけて自律神経を副交感神経優位に整えて(睡眠潜時)」いなければ眠れないメカニズムです。
ところが、過重面談にいらっしゃる労働者は、ほぼ、「秒で寝オチ」です。長時間残業と睡眠不足の関係は明らかになっているので、過重面談対象者が睡眠不足なのは腑に落ちますが、図3は当院を受診した、すなわち睡眠に関心があり、明確な課題意識を持ち、わざわざ睡眠外来を受診した日本人の有業者121名のアンケート結果です。
睡眠外来を受診した有業者のうち、7~9時間を核とする睡眠時間の方は3分の1に満たず、理想的な睡眠潜時はわずか14%、全体の4割以上を占めた気絶群のうち、その寝付きの良さを課題と認識していた方はいませんでした。
海外から驚かれることの多い、公共機関で眠る人々の姿は、睡眠時間が世界的に短い、だからこそ睡眠潜時が極端に短いという日本の特徴的な社会課題を反映した光景なのです。私はこの「寝付きがよい」という日本語が、よくないと思っています。ちなみに、「寝相がよい」のも好ましくない睡眠です。寝相については、私の書籍をご参照ください。
睡眠潜時は、厳しくプログラムされた覚醒から睡眠への移行を乗り越えるための、睡眠にとって非常に重要な和らぎの時間です。睡眠潜時が30分以上かかるからといって、心配する必要はありません。多くの愁訴同様、それが日常生活を支障しない限り、多様な個性の一つに過ぎません。
4.産業保健に活かす【睡眠マネジメント】
それでは、この2つの法則を用いて、産業保健に【睡眠マネジメント】を活かす具体的な方法を紹介しましょう。
図4は、22時過ぎに就寝し、6時過ぎに起床する、私の日常的な24時間のタイムスケジュールです。私の場合は、平日も休日も全く同じです。
睡眠負債のない状態では、起床後10時間程度で、パフォーマンスが下がりはじめます。これは恒常性のリバウンドによるパフォーマンスの低下です。睡眠物質や疲労が蓄積して、回復を促すフェーズです。
起床後10時間以内でも、昼下がりには生理的体温降下に食後の反応性低血糖が加わり、パフォーマンスが下がり、眠気を覚えやすいです。この一時的な眠気の解消には、軽い運動がオススメです。業務上、必要な移動をしてしまうのも一案です。睡眠負債のない場合、起床後10時間以内に睡眠はしないので、15分程度、目を閉じてリラックスしてもよいでしょう。睡眠負債がある場合は睡眠してしまうリスクが高く、深睡眠に至れば社会的時差ボケの火種となって、ますます夜の睡眠構造が崩れるため、睡眠負債のある方は、軽い休憩のつもりで目を閉じないように、注意してください。
睡眠負債がある場合は、睡眠負債の時間に応じて、パフォーマンスの低下時間が早まります。1時間の負債では起床後9時間で下がり、10時間の負債では、起床直後からフルパフォーマンスは出ず、16時間の負債では起床直後からほろ酔い状態、20時間の負債では起床直後から酩酊状態並みのパフォーマンスです。酩酊していても、お勘定して帰宅できるように、その程度の仕事ならできてしまいます。でも、その程度の仕事しかできていません。
睡眠負債の計算は、さきほどの図1の研究なら8時間25分にどれだけ不足しているかの累積時間ですし、睡眠負債とパフォーマンスの関係を明らかにしたVan Dongenらの研究では、8時間16分が基準になっています。どちらの研究も使用されているのはTSTです。よく知られている、日本が最下位のOECD各国睡眠時間の平均は、図1と同じ8時間25分です。こちらはアンケートなので、TIBに近似しますが、毎日のトップパフォーマンス時間を保つためには、少なくとも8時間のTIBが必要ですね。
20代の女性従業員に、「朝活をしたいのに、早起きすると具合が悪くなる。自己啓発セミナーで教わったとおり、朝早く起きて、勉強をして、資格を取りたいのにうまくいかない」と相談を受けたことがあります。
朝早く起きて、仕事以外のことをすれば、単純に、仕事に集中できる時間が減るだけです。一方、資格試験の受験勉強などは記憶が物を言うので、起床後12時間以降のロスパフォーマンスのタイミングでインプットして、睡眠を挟んで定着させたほうが効率がよいのです。
睡眠中、特に前半で脳は直前の覚醒中のインプットを整理し、後半は翌日以降に使いやすいように様々な形態の記憶に加工します。
無理な朝活トライアルをやめた結果、彼女は資格試験に合格し、業績も上がりました。
5.黄金の90分をマネジメントする
もう一件、具体的に産業医の【睡眠マネジメント】が役立った例を紹介します。
・・・
A子さん26歳は半年前に結婚してから、日中の眠気に悩まされています。独身時代は22時前に就寝し、6時過ぎに起床し、20時から21時に帰宅する生活でした。仕事と通勤時間は変わらないものの、夫が毎晩22時半頃帰宅し、その後、食事をしたり入浴したりします。A子さんは22時前に就寝するのですが、1LDKの広くはない部屋で夫が活動しているために、思うように眠れなくなりました。夫はその後就寝し、8時頃、起床します。
・・・
遅くに帰宅する夫が妻に食事の支度をさせるとしたら明らかにNGだけど、自分は眠っているのだからいいじゃないか、と思うかもしれませんがそれは違います。
図5の通り、7~9時間を核とする睡眠(TST)の間に、①前半に含まれる深睡眠(標準:TSTの13~23%)の合計が長ければ長いほど、②レム睡眠(標準:TSTの20~25%)の合計が長ければ長いほど、③睡眠周期のサイクル数(標準:5~6回)が多ければ多いほど、「よい睡眠」です。
就寝後、15分程度の睡眠潜時を経て、浅いノンレム睡眠に至り、その後、本日最初の深睡眠が始まります。本日最初の深睡眠は最も長く、疲労や眠気を回復し、成長ホルモンを分泌して体内組成を修復し、免疫機能を向上し、メラトニンサージで抗がん作用を発揮し、脂肪分解や骨格形成等の代謝調節をし、グリンパティック・システムで脳の老廃物を除去します。この仕事は全て、睡眠の前半で完了するのが理想です。
最初の深睡眠の後、また浅いノンレム睡眠を経て、本日最初のレム睡眠が始まります。本日最初のレム睡眠は、充分な深睡眠をトリガーに発現します。つまり本日最初の深睡眠は、そのあと8時間以上にわたってシークエンスで機能を果たす睡眠のトリガーです。最初のレム睡眠が完了すると、最初の睡眠周期が完了します。
この最初の睡眠周期に十分な量の深睡眠が発現すると、その後の周期をスムーズに進められ、結果として、前半の長い深睡眠、全体として長いレム睡眠、睡眠周期の回数の多さが実現します。そのため、最初の睡眠周期を「黄金の90分」と称します。DEC2やADRB1などの特別な遺伝子を持つ遺伝的なショートスリーパーであっても、この90分は必要です。
深睡眠の脳波は徐波で、ニューロンの電気的な活動は、ほぼありません。当然、睡眠の中で最も覚醒しづらい状態です。睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害により、深睡眠が分断、短縮すると、第一に認知機能が障害され、第二に副交感神経優位を保てず交感神経優位に傾き、心血管系にストレスがかかり、動脈硬化が進み、耐糖能異常などの自律神経アンバランスが生じます。だから、睡眠障害を治療して、深睡眠を確保する意義は大きいのです。
一方、睡眠の後半は浅いノンレム睡眠とレム睡眠で構成される目覚めやすい睡眠です。私は簡単に、睡眠の前半は前日までの脳の片付け、後半は翌日以降のための脳のブラッシュアップの時間と説明しています。充分な深睡眠を含んでいれば4時間睡眠(睡眠負債4時間)でも、起床後8時間程度は眠気を感じないでいられますが、単調作業をできていても、クリエイティブな作業の能率は下がります。ただ、すでに睡眠負債がある場合の4時間睡眠では、睡眠の構造が確実に崩れるので、特別な遺伝子を持っていない限りは、短時間睡眠で充分な深睡眠を発現させることはできません。
・・・
A子さんは医療機器メーカーの営業職で、みなし残業20時間、通常就業時間は休憩1時間を含む、9時から17時半です。通勤時間は1時間弱、6時過ぎに起床し、7時半に家を出て、8時半に出社、19時過ぎまで働きます。顧客が病院の医師なので、朝早くや夜遅くに呼びつけられることも多いのです。
A子さんは独身時代と同じように22時前に就寝するので、22時半に夫が帰宅すると黄金の90分に一致します。ここで深睡眠を乱されると、その後の睡眠構造も崩れて、睡眠の質が下がります。
産業医の私はA子さんの就業時間を10時から18時半に変更するよう会社に提案しました。A子さんの帰宅が21時から22時に遅れるとしても、夫と同じ0時前から8時までの睡眠時間を確保できれば、問題が解決すると考えたからです。
しかし会社はフレックス制度を採用していず、制度の変更はできないという回答でした。とはいえ、ここで重要なのは、一度、トップマネジメントまでこの事例を上げて、検討はしてくれたことです。会社のルールを変更するのは簡単ではありません。従業員である以上、会社のルールに従うべきなのも当然です。
次の解決策として、A子さんには、20時台、少なくとも21時には就寝することを勧めました。これなら22時半の夫の帰宅時は、2サイクル目に入っていますので、その後の睡眠の構造への影響は少なくなります。
この方法でA子さんの眠気は解消し、生産性が上がりました。以前より早く仕事を切り上げるため、実際の労働時間は減ったのですが、診療開始前の面談を望む医師らへの対応を一手に引き受け、業績は上がりました。つまらない夜の会につきあわされる機会も減り、夫にも顧客にも同僚にも、以前より優しい気持ちを持てているそうです。
・・・
この視点での【睡眠マネジメント】は、共働き子育て夫婦でも功を奏した好例がありますが、またの機会にお伝えします。
仕事も家事(育児)も睡眠も24時間を配分する必要がありますが、それぞれの絶対条件、タイミングがあります。そこを賢くマネジメントすることで、全員にとってポジティブな結果を演出することは可能です。
6.産業保健視点ですぐに着手できるデータ的【睡眠マネジメント】
なんということでしょう、一番大事な生産性と睡眠の関係について、皆様にお伝えしたかったのですが、字数が尽きてしまいました。
最後に簡単に着手できる事業場の睡眠データ管理について触れておきます。
現在、全国民への睡眠健診の重要性が叫ばれており、日本睡眠学会、日本睡眠協会、「国民の質の高い睡眠のための取り組みを促進する議員連盟」(略称:睡眠議連)などが、国民総睡眠健診の導入を、医学部の睡眠分野のコアカリキュラム化や標榜診療科としての認定等と同様、提言しております。
成人の睡眠時間も、こどもの睡眠時間も、こどもの睡眠に対する親の意識も、世界でワースト1位の日本ですが、誇れるデータとして蓄積しているのが、健康保険組合の成人病健診問診の、「睡眠で充分に休養が取れているか」という質問に「はい」か「いいえ」で答える項目と、ストレスチェックに用いられる職業性ストレス簡易調査票のB(ストレス反応)の29、「よく眠れない」という質問に4段階で答える項目です。
これらは先行研究も多いので、簡単に事業場の睡眠を可視化できるファクターだと思います。
協会けんぽ富山支部のニュースリリース(令和4年)には、各支部の睡眠で充分に休養が取れていない割合のグラフが掲載されています。社内で計算して、衛生委員会のネタにしてみてください。
紙面の都合で、【睡眠マネジメント】のほんの一部しかお伝えできませんでした。ぜひ、第二弾でお目にかかりたいです。本稿の内容は、「Dr. Yokoの睡眠マネジメント 眠るほど、ぐんぐん仕事がうまくいく」に書いてありますし、ご依頼をいただけましたら、どの事業場へも講演等にうかがいます。
【睡眠マネジメント】が、産業医の先生方の日常業務のスキルアップにつながることを、願ってやみません。
本記事を執筆いただいた石田陽子先生は、2025年5月に仙台で開催される第98回 日本産業衛生学会にて、「睡眠健康経営」をテーマとしたランチョンセミナーに登壇予定です。事前参加登録が必要となっておりますので、ご興味のある方は以下よりお申し込みください。
▶ランチョンセミナー(事前申込)・モーニングセミナー|第98回日本産業衛生学会
■執筆
石田陽子 (産業医、公衆衛生学博士、労働衛生コンサルタント、麻酔科標榜医 )
株式会社心陽代表取締役、ai-X株式会社CEO、心陽クリニック(本郷睡眠センター)院長
麻酔科医として高度急性期臨床に従事しながら、社会医学への関心を高め、企業の健康経営を支援する株式会社心陽を設立。
企業の産業医やセミナー講師、睡眠関連企業顧問など睡眠社会学の第一人者として活躍する一方、睡眠外来で臨床に当たる。
本年2月、働く成人をターゲットにした『Dr. Yokoの睡眠マネジメント 眠るほど、ぐんぐん仕事がうまくいく』(文芸社)を出版。
本年3月、睡眠を中心とする自律神経バランスにフォーカスし、AIを駆使して日本の生産性向上を目指すai-X株式会社を設立。
本年5月17日土曜日、第98回日本産業衛生学会において、【睡眠健康経営】のランチョンセミナーに登壇予定。