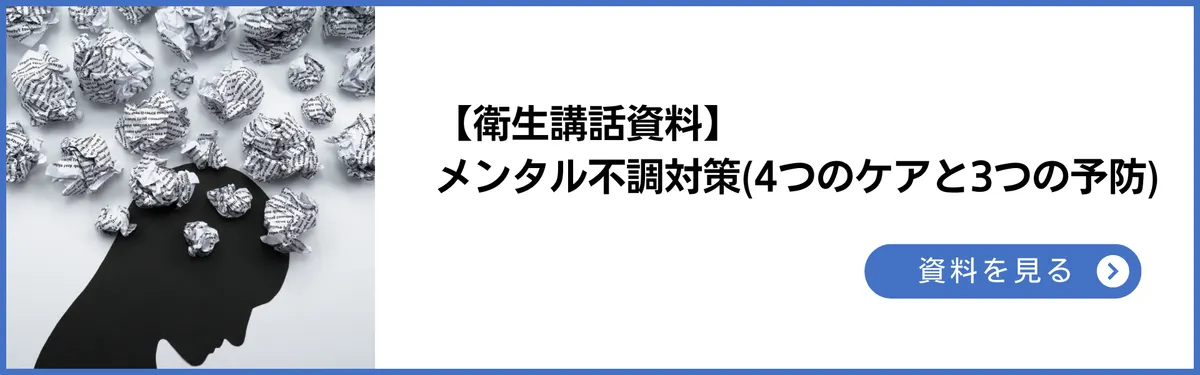管理職は、現場の一担当者だった頃とは立場が大きく変わり、企業側の立場で組織全体の責任を担う重要なポジションになります。日々の努力が評価されて管理職に昇進することは、大きな喜びであり、自信にもつながるものです。 しかし、ストレスやプレッシャーによってメンタル不調を起こしてしまうケースもあります。
この記事では、管理職のメンタル不調に対して、企業が取るべき対策について詳しく解説していきます。
<目次>
1.管理職がうつやメンタル不調に陥る原因
2.管理職の「うつ」の兆候
3.管理職のメンタルを守るために企業が取るべき対策
4.まとめ
1.管理職がうつやメンタル不調に陥る原因
管理職がうつやメンタル不調に陥る原因としては、以下のような理由が考えられます。
- 重すぎる業務と責任、それに見合わない報酬
- 育成の責任と実務の両立の悩み
- 仕事とプライベートの両立による負担
- 経営層と現場の板挟みによるストレス
ひとつずつ、見ていきましょう。
■給料に見合わない業務量や責任の重さ
管理職は、ただ自分に与えられた仕事を終わらせれば良いというわけではなく、組織全体を把握しながら様々な業務を抱えて仕事を進めています。さらに、残業をしても残業代が支払われないなど、業務量に対して給与が見合っていない状況は、精神的な負担をさらに大きくします。
また、部下が何か仕事でミスをしたり、トラブルが起こったりした時は、その責任を負う立場でもあるので、日々のストレスや重圧が積み重なり、「うつ」やメンタル不調を引き起こすケースがあるのです。
■部下を抱えるプレッシャー
管理職は、通常の業務以外にも部下のマネジメントや育成などの役割も担っています。しかし、多くの管理職はプレイヤー業務も並行して行っており、部下の育成に十分な時間を確保出来ていないのが現状です。
このように、管理職はマネジメント業務に専念できない状況下で部下の指導・育成を行わなければならないという状態であり、負担を強いられているのが現状です。
■仕事とプライベートの両立
管理職へ昇進するのは、多くが40代以降になるため、20代の頃とはライフスタイルの変化が生じやすい年代に入ります。企業では、部下の育成や管理職としての成果を求められ、企業側に立って責任ある業務を日々こなす立場である一方、プライベートでは育児や両親の介護問題など、頭を悩ませる問題が出始める年齢でもあります。
このような中で、年齢と共に自分自身の体力的・能力的な限界を感じる時でもあるため、ストレスが重なることでメンタルに不調をきたすケースが多くなってくるのです。
■企業と部下の間でのストレス
管理職は、現場で働く社員と経営層の間に立ち、組織が円滑に機能するよう意見を調整する役割を担っています。現場の声と経営側の方針のあいだで対立やすれ違いが生じた場合、その調整を行うのは管理職です。双方がそれぞれの主張を管理職にぶつけてくることも多く、その板挟みになる管理職の精神的な負担は大きくなりがちです。
2.管理職の「うつ」の兆候
管理職に昇進するような人は、多少のストレスがあっても簡単に仕事を投げ出すようなことはありません。むしろ責任感が強く、無理をしてでもやりきろうとする傾向があります。そのため、気づかないうちに限界を超えてしまい、ある日突然、うつ症状を発症してしまうこともあります。
そのため、管理職が「うつ」によって仕事が続けられなくなるのを防ぐため、出来るだけ早く「うつ」の兆候をキャッチすることが大切です。
管理職の「うつ」の兆候としては、以下のようなものが挙げられます。
- 表情が暗く口数が減った
- 期限までに仕事が終わらなくなってきた
- 怒りっぽくなり、部下を叱る場面が多くなった
- ミスが増えた
- 判断力が落ち、業務スピードが下がった
- 整理整頓が出来なくなっている
以前までは、真面目にしっかりと業務を進め、部下とのコミュニケーションや連携もしっかり出来ていた人なのに、だんだんと上記のような兆候が見られるようになったら、「うつ状態」の可能性が高いでしょう。
3.管理職のメンタルを守るために企業が取るべき対策
それでは最後に、管理職のメンタルを守るために企業が取るべき対策を紹介していきます。メンタルの不調は管理職だけの問題ではなく、企業全体で考える必要があります。
■管理職のストレスケアの体制を構築する
厚生労働省は、労働者のメンタルヘルス対策として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を示しており、その指針に沿ってメンタルヘルス対策を構築することが望ましいとしています。
例えば、セルフケアとして、労働者が自分自身でストレスを抱え込み過ぎていることに気づき、対処できるような環境を整えましょう。必要な場合は、セルフケア・ストレスケア研修などを実施するのも効果的です。
管理職は、よほど心身の変調を感じない限り、多忙な毎日の中で自分自身のメンタルの異常に気付くことが難しい場合もあるでしょう。そのため、管理職向けのメンタルヘルスケアの場を設けることで、ストレスの緩和に繋げます。
保健指導や健康だよりで活用できる「セルフケア」リーフレットはこちら👇

■外部の相談窓口などを案内する
管理職になると、部下のマネジメントや組織運営など、経営側の視点から会社を支える役割も求められるようになります。そのため、自分自身がストレスを感じていたり、うつの兆しに気づいていても、「弱音を見せてはいけない」と思い込み、社内で気軽に相談しにくいと感じる人もいます。
そのため、匿名で申し込める相談窓口を設置したり、メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を持っている外部の相談機関を案内したりすることで、「うつ」を発症する前の対策が出来ます。
心理専門家による24時間・土日祝・全国対応のカウンセリングサービスはこちら👇
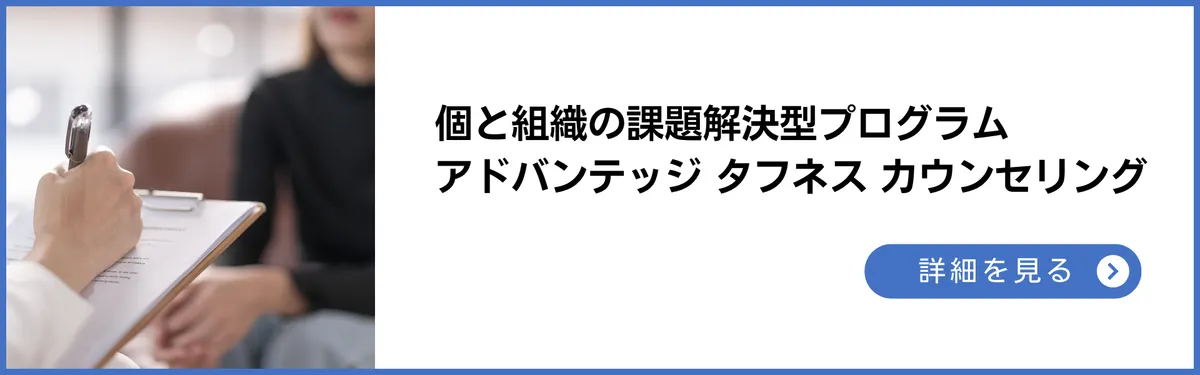
■定期的なストレスチェックの活用
管理職は、日々忙しく業務に追われているため、自分自身のストレスやメンタルの不調に気づかないケースも少なくありません。そのため、管理職も含めた従業員のストレスチェックをすることで、管理職のストレス傾向の把握が期待出来ます。
ストレスチェックの結果から、その後個別に産業医などとの面談を行い、「うつ」を防ぐための対策を考えることも可能になります。
やりっぱなしで終わらせない、ストレスチェックから始めるワンストップサービスはこちら👇
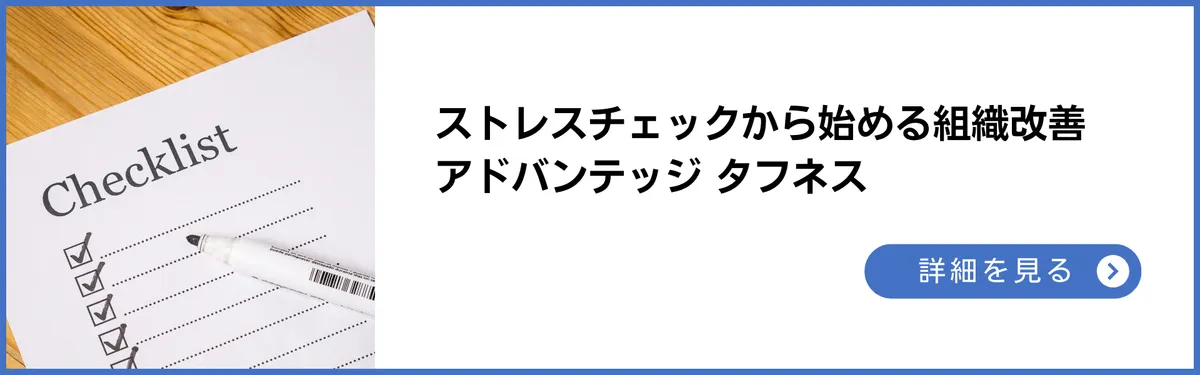
4.まとめ
管理職の心の健康に配慮することは、企業にとって非常に大切です。管理職がうつ症状などによって業務が難しくなると、企業全体の生産性が下がるだけでなく、現場の運営や意思決定、部下への指導にも支障が生じます。その結果、チーム全体の業務がとどこおり、部下の業務負荷も重くなってしまいます。特に管理職は、多忙な日々の中で自分のストレスに気づきにくいことが多いため、企業側が定期的にメンタルヘルス研修を実施したり、不調を感じたときに気軽に相談できる窓口を整えておくことが必要です。
■参考
1)職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~|厚生労働省
2)ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等|厚生労働省
3)中間管理職が抱えがちなストレス要因とは?人事が取るべきケアと対策|アドバンテッジJOURNAL
■執筆/監修
<執筆>久木田 みすづ (精神保健福祉士、社会福祉士、心理カウンセラー)
福祉系大学卒業後、カウンセリングセンターの勤務を経て、心療内科クリニック・精神科病院で精神保健福祉士・カウンセラーとして従事。うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんと家族に対する相談や支援に力を入れる。
現在は、主にメンタルヘルスの記事を執筆するライターとして活動中。
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』