健康診断後に行う再検査や精密検査案内等の受診勧奨は、従業員の健康の維持・増進に直結するだけでなく、企業の安全配慮を果たす上でも重要な業務です。 一方で、「受診が怖い」「医療機関に行くのが面倒くさい」等、医療機関を受診することに抵抗を感じて受診を先延ばしにする従業員も少なくありません。
ここでは、産業保健師が実施する受診勧奨の文章作成のポイントや表現例をFAQ形式で解説します。
Q1. 受診勧奨の文面で重要なポイントは何か?
医療機関受診の目的・理由・受診期限の3点を明確に書くと受診につながりやすくなります。 「なぜ医療機関受診が必要なのか」「どの項目に対して受診が必要なのか」「診療科はどこが望ましいのか」「いつまでに受ける必要があるのか」を端的に伝えるとよいでしょう。 また、受診前から受診後の流れについて、費用負担の有無などを明記すると安心感が高まります。
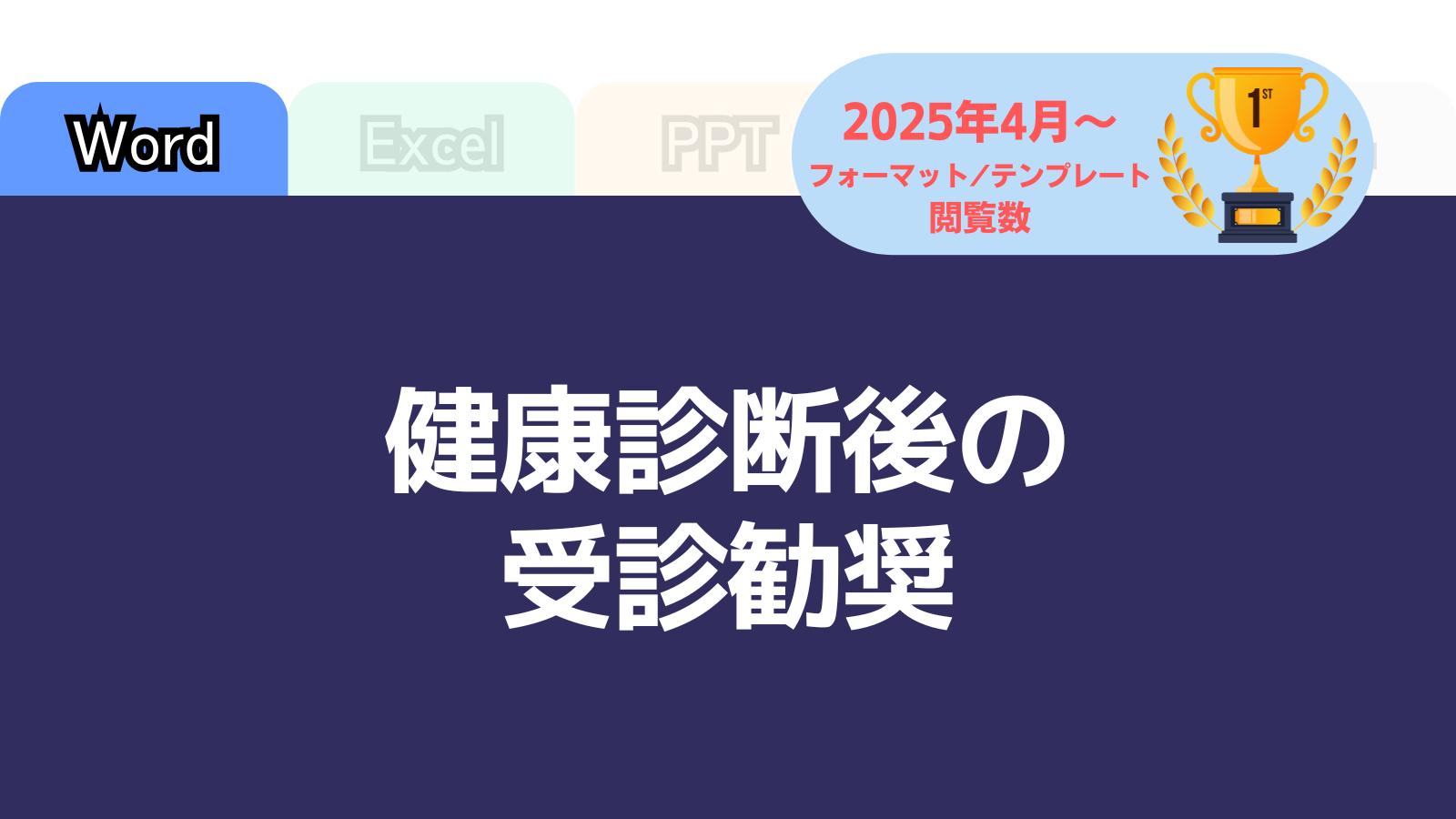
Q2. 受診勧奨で「伝わりやすい」言い回しの例は?
メールなどで案内をする場合は、開封してもらうために、タイトルで何のお知らせかが明確にわかるよう工夫しましょう。文章には専門用語はできるだけ避け、中学生でも理解できる表現を用いることで、従業員に伝わりやすくなります。また、文章は端的にまとめ、必要最低限の情報にすることで、重要な内容がより伝わりやすくなります。さらに、案内にナッジ理論を活用するなど、受診行動につながる記載方法の工夫も重要です。

Q3. 健康リスクを伝えつつ、受診へのハードルを下げる表現は?
リスクを隠さず伝えつつ、医療機関を受診する必要性を強調します。
例:「放置すると症状が進行する可能性がありますが、早期発見や早期対応でほとんど改善が期待されます」
受診予約先や所要時間、持ち物など具体的な情報も加え、心理的・実務的ハードルを下げましょう。また、行動までのステップを具体的に提示することで、受診までの行動に進みやすくなります。
例:
ステップ1:診療科を検索・確認
ステップ2:〇月×日までに電話で予約
ステップ3:健康診断結果と受診勧奨通知書をもって受診
ステップ4:結果を健康管理室へ報告(〇〇と〇〇について報告)
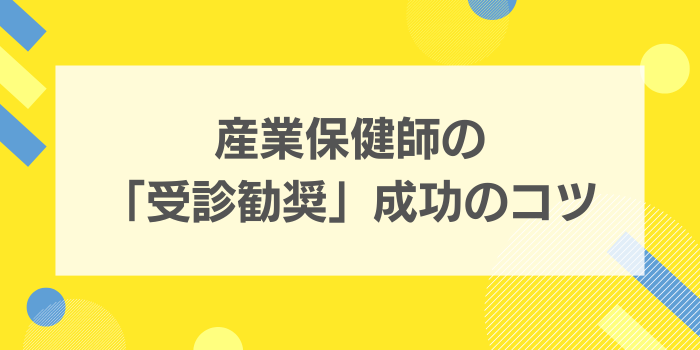
Q4. 法的な注意点や個人情報保護に配慮すべき表現は?
文面には具体的な数値を記載せず、受診が必要な項目のみにとどめる等、必要最低限の記載が望ましいです。 個人情報保護の観点から、詳細は本人のみが確認できる方法(封書・個人メール)で通知します。 また、差別や不利益につながる可能性のある表現は避け、事実と受診推奨理由のみにとどめます。 運用にあたっては、あらかじめ会社で定められた「健康情報取扱規程」に沿って進めるのがよいでしょう。
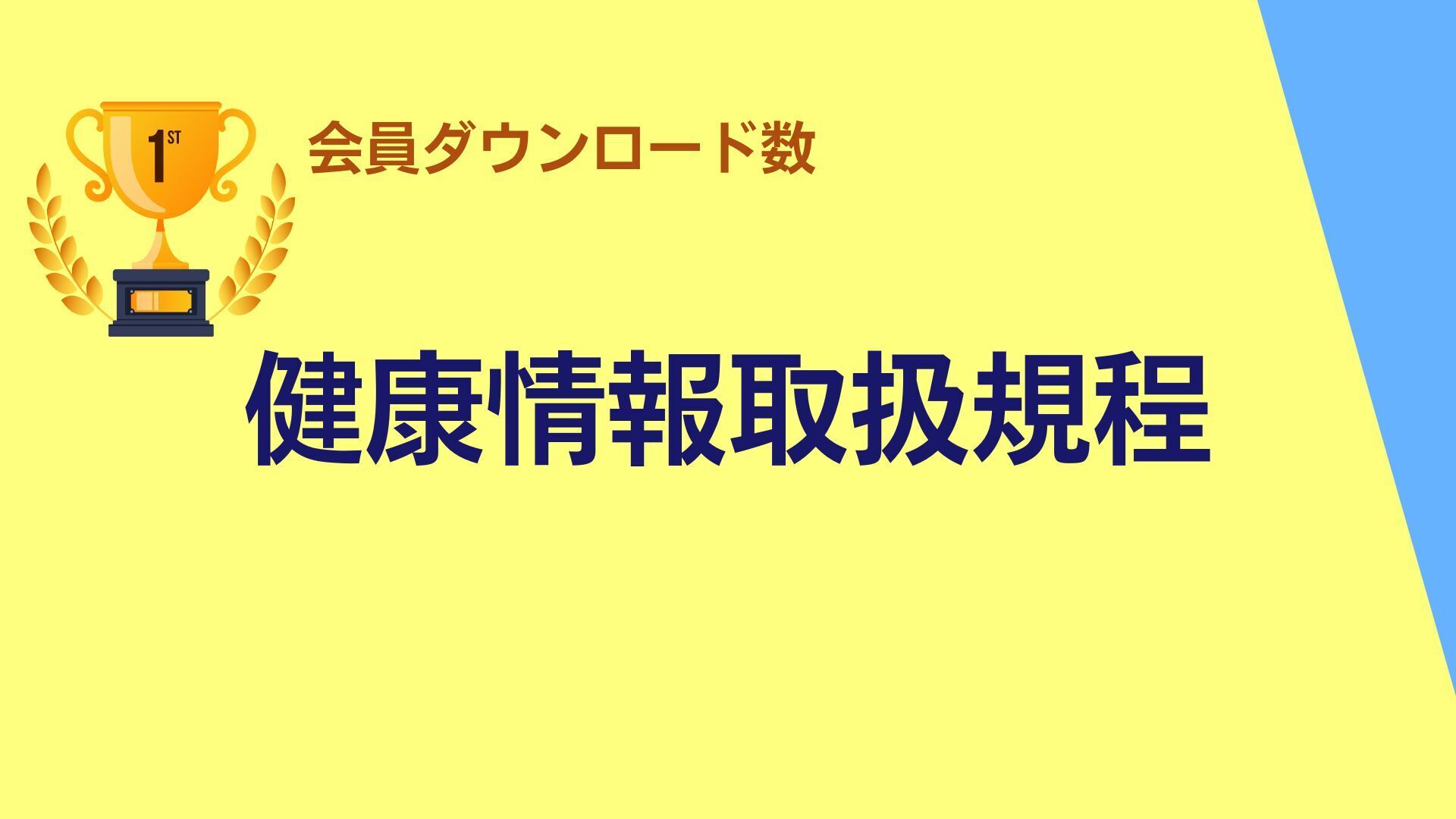
Q5. フォローアップメール・文書のタイミングは?
フォローアップは、健康診断直後に行うのが望ましいですが、産業医が就業判定を行ったうえで産業医の意見を基に対応する場合もあります。そのため、あらかじめ産業医と相談のうえ、会社としてのフォロー体制を構築しておくことが重要です。 受診期限は、会社側で設定するだけでなく、本人に決めてもらう方法も有効です。初回案内で期限を明示し、期限の前後でリマインドや確認を行うことで、受診行動につなげやすくなります。さらに必要に応じて、保健指導や産業医面談などを組み合わせることで、受診の意味や目的をより理解しやすくなり、行動の後押しにつながります。

まとめ
受診勧奨は「必要な情報の提供」と「受診行動に導くための仕組みづくり」を両立させることがカギとなります。 具体的で分かりやすい案内を心がけることで受診率を高めましょう。 また、伝わりやすい文面を意識し、適切な受診行動につなげることは、従業員の健康を守るだけでなく、職場の安全確保にもつながります。
健診結果を健康経営や施策に活かすまで手が回っていないという方は、健康管理システム「アドバンテッジヘルスケア/スマートケア」を是非ご活用ください👇





