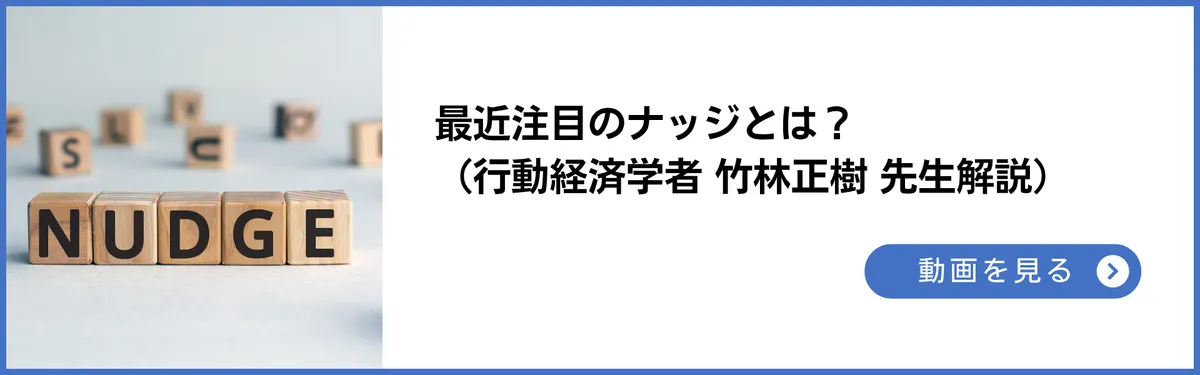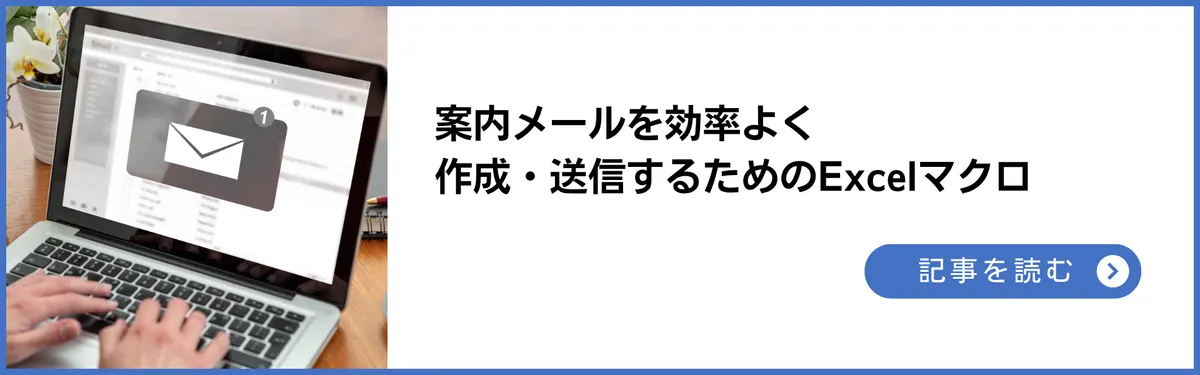産業保健師の「受診勧奨」成功のコツ|断られない伝え方と実践のポイント
産業保健師の多くの皆さまは、従業員に対して受診勧奨を行っていることと思います。素直に受診してくれる人もいれば、「忙しいから」「薬を使いだしたらずっと飲まなければならないから」と何かと理由づけて受診しない方もいらっしゃると思います。今回は「受診勧奨」成功のコツについてご紹介します。
<目次>
1.なぜ受診勧奨が難しいのか
2.ケーススタディ:実際に受診勧奨に成功した事例
3.断られても焦らない、フォローの重要性
4.まとめ:受診勧奨は”伝え方”次第で変わる
1.なぜ受診勧奨が難しいのか
厚生労働省の報告によると、受診勧奨判定値が、「服薬開始基準」であると誤解されているケースがあり、現場の運用で混乱をきたしているのではないかという意見がありました。健康診断で『受診が必要』とされた場合でも、すぐに治療や服薬が始まるわけではないことが多く、そのギャップが現場での混乱につながっているようです。例えば、健康診断で高血圧を指摘された方についても、「1週間ほど家庭で血圧を測定して、それでも高かったらまた受診してください」と言われるケースもあります。しかも、結果的に医療機関から「問題ないから帰りなさい」と言われることもあり、従業員から「受診する必要なかったじゃないか!」と言われることもあります。言われるまで至らなくても、従業員から不信感を持たれることもあります。今後の信頼関係に影響することもあるので、受診勧奨を行う身としては辛いものがあります。
健診機関における受診勧奨判定値の在り方について様々な議論がなされているところではありますが、すぐにどうこうということはなさそうです。現状、相手の反応を見ながら伝えていくしかないように思います。
2.ケーススタディ:実際に受診勧奨に成功した事例
過去に受診勧奨に成功した事例についてご紹介します。ナッジ理論のEgo(エゴ)を活用する方法です。ナッジとは「ひじで軽く突く」「そっと後押しする」という意味です。選択の自由を与えながら、行動経済学に基づいて人々に行動変容を促すことがナッジ理論です。 Ego(エゴ)」の具体的な意味が説明されておらず、読者が内容を理解しづらい可能性があります。たとえば「Egoとは『自分自身をよく見せたい』『自信を持ちたい』という気持ちをベースに、人が前向きな行動をとりやすくなる心理傾向です。自尊心を刺激したり、過去の成功体験や社会的な役割を意識させることにより、自然な行動変容が促されます。
ナッジ理論の第一人者である竹林正樹先生によるナッジ解説動画はこちら👇
事例①
43歳、男性の方で、毎年、健康診断でメタボリックシンドロームを指摘されています。特にLDLコレステロール値については150~160mg/dlと高値が続いています。若くして営業課の管理職となり、人一倍プライドは高い方です。接待で外食する機会も多く、なかなか食生活の改善は難しい状況です。
その方に「ホームドクターをつくってみてはどうでしょうか?」と提案しました。「今すぐ薬を服薬しなければならないかは、健康診断の結果だけでは分かりません。ただ、年に1回だけの健康診断だけでは心もとないので、いつでも気軽に相談にのってもらえるホームドクターがいると安心です。今回の健診結果を持って、内科を受診してみてはどうでしょうか?」とお伝えしました。「減量しなさい、この食事はやめなさいと言われることは多かったが、今までそんな言われ方をしたことがなかった」とおっしゃっていました。
ホームドクターという言い方が良かったのでしょうか。減量や禁酒といった行動ではなく、『ホームドクターを作る』という提案は、自分にもできそうで、メリットがあると感じられたのかもしれません」といった説明が考えられます。「また、「主治医」や「かかりつけ医」よりも、「ホームドクター」という言葉が親しみやすく、自分にとってプラスのイメージとして伝わったのかもしれません。 気分を良くされたのか、素直に内科を受診されていました。その結果、頸動脈に狭窄が認められ、高脂血症の治療が開始されました。このまま放置していたら脳梗塞を発症していたかもしれません。何かしらの自覚症状が出る前に受診することができて良かったです。しかも管理職という立場のある方だったので、この一件があって以来、ご自身の部下に対しても「ちゃんと受診しろよ」と声かけをしてくださり、部下の健康管理にも熱心に取り組んでくれるようになりました。
事例②
もう1つのケースについては、60歳、男性で毎年高血糖を指摘されていた方についてです。健康診断の血液検査で高血糖を指摘され、ここ2年ほどは尿糖まで認められるようになりました。娘2人は結婚や就職を機に家を出られ、奥さんと2人暮らしです。近くに実母が1人で暮らしています。実父は心筋梗塞で他界していました。生前、実父は糖尿病の治療を行っていましたが、なかなか禁酒・禁煙ができずに医師に怒られていたと話していました。65歳という年齢で亡くなった実父の姿を見て、「あぁいう死に方はしたくないなぁ・・・」と思いながらも仕事の忙しさもあり、全く病院受診していませんでした。
役職定年をされ、責任ある立場でなくなったときをきっかけに病院受診を促しました。「これまで会社の部下、娘さん、色んな方を育ててきましたよね」「そろそろご自身の身体を労わってあげてください」とお伝えしました。ご自身としてもそろそろ病院受診しなければならない状態だと認識されていたため、素直に病院受診されました。家庭状況や既往歴などの背景を把握していたことが活躍しました。地域で評判のよい病院がまだ診療していたため、そこを受診するように勧めました。糖尿病の内服治療も始まりましたが、「予防的に内服するように」という説明を受けたようです。厳しい食事指導や運動指導も受けており、挫折しそうになることもあったようです。社内ですれ違う際、積極的にお声がけし、「がんばりましょう」「熱心に指導してくださる先生は良い先生ですよ」と励ましていました。結果的に、2年間で15kg近くの減量に成功し、血糖値のコントロールも大きく改善されたため、服薬はいったん終了となりました。ご本人も「独身のときのズボンが入る」と喜んでおり、体重も維持しています。今でも3カ月毎に血液検査と尿検査を受けに経過観察しています。
医療機関への受診を阻害する要因の1つに、「ずっと内服しなければならない」ことがあるように思います。素直に内服を開始するのもありですが、努力次第で減薬や断薬ができることもあります。今回のケースはご本人の背景やタイミングを踏まえ、行動変容を促すことに成功しました。
3.断られても焦らない、フォローの重要性
上記の2つの事例は受診勧奨に成功した事例ですが、失敗した事例も多数あります。先述した通り、何かと理由をつけて医療機関を受診しない方はいらっしゃいます。実際の現場では、受診勧奨するレベルを分けています。特に強く受診を勧めたい人については、強めに受診勧奨を行います。それでも受診に繋がらない場合は、産業医や人事労務担当者の力を借りて受診勧奨を行います。
そこまで緊急性の高い状態ではないが、3カ月以内には受診してほしいなという段階の人については、一通り受診勧奨を行います。だいたいの方は「毎年のことだから」と言って、受診しません。そういった方について、受診勧奨を行ったこと、そのときの反応がどうだったのかという記録を残すようにしています。万が一重篤な病気が見つかり、ご本人やご家族から責められたとしても、その記録がご自身や会社を守ってくれます。そして、最低3回は何かしらのアクションを起こすようにしています。しつこいと思われても、文書なりメールなり受診勧奨を行います。繰り返し、繰り返し受診の声かけをすることで受診率を向上させることに成功したという報告もあります。何かしらのタイミングで受診してくださることもあります。
案内メールの送信業務を効率させたい方はこちらの記事をご覧ください👇
4.まとめ:受診勧奨は”伝え方”次第で変わる
企業が従業員に対して二次検査を受けるように促すことが求められているものの、強制力はありません。あくまでも企業側の努力義務に位置づけられています。それゆえ産業保健師としてあまり強く言えないところが一番のネックです。
文書やメールで受診勧奨を促すよりも、電話や口頭で受診勧奨を行った場合の成功率が一番高くなります。今後、社内のチャットツールやメッセージアプリを利用した受診勧奨も求められてくるとは思いますが、そもそも二次検査が必要となる年齢層についてはアナログな方法が案外効果的です。「受診しなさい」ときつく言うのではなく、「あなたのことを心配しています」ということを強く訴えます。人は心のどこかに「受診しなきゃいけないな・・・」と分かっているもので、誰かの後押しが欲しいときもあるのです。口頭で受診勧奨を行った場合、多くの方が受診結果について報告してくれます。不思議なもので、誰かに何かを言われたらどこかに報告したくなるものです。真っ先に産業保健師に報告したくなるような、そんな存在でありたいものです。
■参考
1)第3回 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ|厚生労働省
2)⾏動科学やナッジ、ソーシャルマーケティングを活⽤したがん検診受診勧奨の取り組み|厚生労働省
■執筆/監修
<執筆>
阿部 春香(保健師、産業カウンセラー、第一種衛生管理者)
日本産業衛生学会、日本産業保健師会に所属する。2024年に日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度登録者として登録する。
広島大学大学院(博士課程前期)を修了後、健診施設に勤務する。現在、中小企業の保健師として勤務し、健康経営の推進を行っている。
働く全ての人に産業保健を届けたいという思いから、産業保健職として産業保健の社会的認知を広げるための活動も行っている。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』