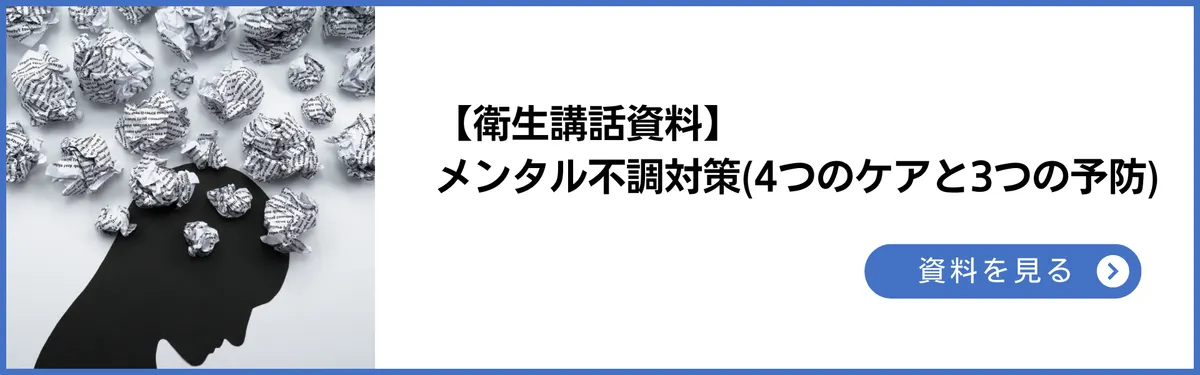厚生労働省が令和5年に実施した労働安全衛生調査【個人調査】によると、仕事上で強いストレスを感じることがあると答えた人が、80%以上という結果が示されました。この中には、20代・30代の若手社員から40代以降の社員も含まれますが、特に20代・30代の若手社員は仕事内容に加えて職場環境や人間関係にも慣れていかなければならないというストレスが大きいと考えられます。事業所にとって、戦力となる若手社員がうつで休職や退職に追い込まれることは出来るだけ避けたいですよね。
この記事では、20代・30代の若手社員がうつになりやすい理由と対策について詳しく解説していきます。
<目次>
1.20代・30代の若手社員がうつになりやすい理由
2.早期発見が新人社員や若手社員のうつを防ぐ
3.20代・30代の若手社員のうつを防ぐために事業所ができること
4.まとめ
1.20代・30代の若手社員がうつになりやすい理由
20代・30代の若手社員がうつになりやすいのは、なぜでしょうか?考えられるものとして、以下のような理由が挙げられます。
- 「業務やキャリアに対する不安やストレス」
- 「スマートフォンが生む“常時接続”のストレス」
- 「職場の人間関係や評価によるプレッシャー」
ひとつずつ、紹介します。
■業務やキャリアに対する不安やストレス
近年多くの企業では、新入社員を大量に採用することが以前よりは少なくなっており、その分採用した新入社員は即戦力として期待をされるようになりました。そのため、時間をかけた教育期間を設けられない企業も多く、幅広い業務を新人の頃から抱えるケースもめずらしくなくなっています。
しかし、こうした労働環境だからこそ、業務量への不安や今後のキャリアに対する心配が増えることが、メンタルの不調をきたしてしまう若手社員が多くなる理由として挙げられます。
また、新入社員や若手社員の段階で、すでに自分のキャパ以上の仕事を抱えていると、昇進によって「さらに業務量が増すのではないか?」という恐れも大きくなるでしょう。
■スマートフォンが生む“常時接続”のストレス
20代・30代の若手社員は、スマートフォンを駆使して仕事をこなす姿から「効率よく働いている」と思われがちです。しかし、スマートフォンによって仕事の連絡がいつでも届き、進捗の確認もどこでも可能になったことで、仕事とプライベートの境界があいまいになっています。
この「常に仕事がつながっている状態」は、一見便利に見えるものの、心身には大きな負担を与えます。オフの時間にも業務のことが頭から離れず、気づかぬうちに休息が取れなくなってしまうのです。
さらに、長時間スマートフォンやパソコンを見続けていると、脳の疲労に陥りやすくなる環境に身を置くケースも。完全に仕事から頭を離して休む時間が少なくなっており、徐しだいにメンタルがむしばまれることがあるのです。
■職場の人間関係や評価によるプレッシャー
多くの時間を共に過ごす上司や同僚との人間関係は、メンタルヘルスに大きな影響を及ぼします。特に、社員の心理的安全性が低い職場では、ストレスがあってもなかなか相談しようとは思えず、自分だけで抱え込むケースも少なくありません。
また、実際に評価をする立場の社員との関係性やハラスメントなどによって、うつになってしまう場合もあります。
さらに、他の社員と自分を比較できる状況も、ストレスが大きくなる要因に繋がっています。他の社員が自分よりも効率よく仕事をこなしている状況を感じた時に、メンタルに不調をきたしていても誰にも相談できずストレスが増す場合もあるでしょう。
2.早期発見が新人社員や若手社員のうつを防ぐ
20代・30代の若手社員が、うつによって休職や退職をするのを防ぐためには、出来るだけ早く社員の異変に気付き、早期介入をすることが大切です。
うつの兆候は、本当に小さな変化から始まります。本人がキャパオーバーになっていないか、メンタルの状態を把握してすみやかに対処することが、若手社員のうつを重症化させないための重要なポイントとなるのです。
3.20代・30代の若手社員のうつを防ぐために事業所ができること
20代・30代の若手社員のうつを防ぐために事業所ができるのは、どのようなことでしょうか?具体的な方法としては
- 「心理的安全性を高めるための研修を行う 」
- 「1on1ミーティングや相談窓口を設けメンタル状態を把握する」
- 「管理職に対しハラスメント防止策の理解を広める」
などが挙げられます。
■心理的安全性を高めるための研修を行う
心理的安全性とは、職場で自分の意見を安心して言えたり、ミスをしても非難されることなく次に活かすことができるような、精神的に安全な状態を指します。こうした環境があることで、わからないことや聞きたいことがあったとき、社員は余計な不安を感じずに相談することができ、特に若手社員のうつ予防に効果的です。
そのため、若手社員の教育や指導を担う管理職や先輩社員に向けて、心理的安全性を高めるための指導法についての研修を行うことが有効です。この研修では、失敗を責めるのではなく前向きにアドバイスする方法や、若手社員の意見を尊重して受け止めるコミュニケーションの取り方などを学びます。こうした関わり方が、安心して働ける職場づくりにつながります。
■1on1ミーティングや相談窓口を設けメンタル状態を把握する
20代・30代の若手社員は、ストレスを感じていても職場で相談しにくいと感じていることが少なくありません。特に、上司や同僚との関係性によっては、不調を抱え込んでしまうケースもあります。
そこで、上司との定期的な1on1ミーティングを設け、仕事の悩みや不安を気軽に話せる場をつくることが大切です。加えて、上司には言いづらい悩みを吐き出せる、社内外の相談窓口の設置も有効です。
さらに、外部の専門家に匿名で相談できる「EAP(従業員支援プログラム)」を導入すれば、より安心して相談できる環境が整います。こうした仕組みにより、メンタル不調の早期発見と対応が可能になります。
心理専門家による24時間・土日祝・全国対応のカウンセリングサービスはこちら👇
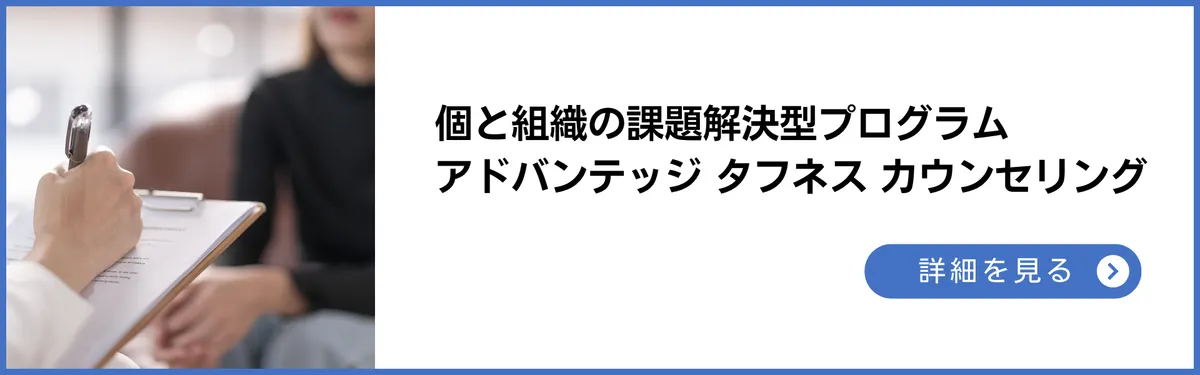
■管理職に対しハラスメント防止策の理解を広める
ハラスメントに関しては、2022年4月から全事業所に対してパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の措置が義務化されており、相談窓口の設置だけでなく、実効性のあるハラスメント対策が求められています。
そのため、20代・30代の若手社員の指導にあたる管理職に対しては、形式的なものではなく部下の話を傾聴し、パワハラ・モラハラのない職場を保証できるような理解が必要になるのです。
特に、長年勤めている社員は、時代の流れの中で若手社員との接し方に悩んでいるケースもあるため、全体的にハラスメントに対して理解を深められるような研修や説明会などを実施すると良いでしょう。
こちらの動画では、パワハラに対する企業の取り組み事例を紹介しつつ、管理職教育のポイントについて解説しています👇
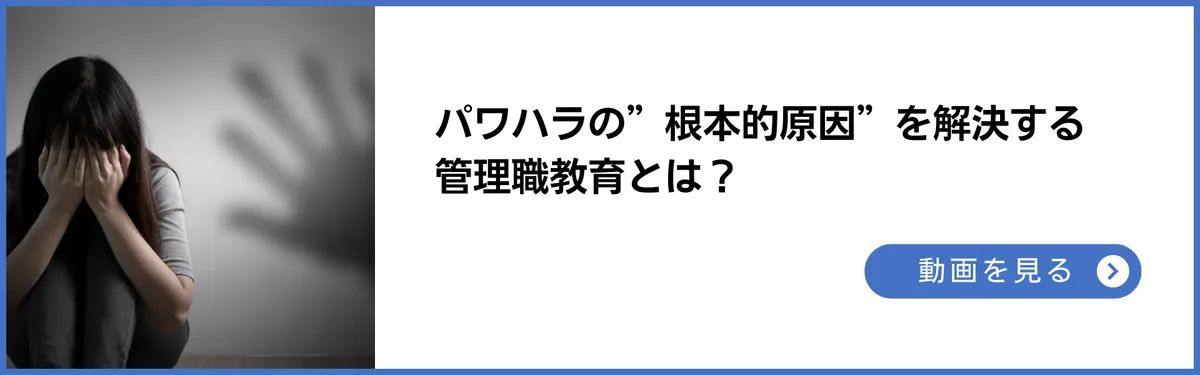
4.まとめ
20代・30代の若手社員は、即戦力となるよう期待される分プレッシャーが大きく、人手不足の影響もあり、1人ひとりが抱える業務量が多い傾向にあります。そうした中で、プライベート時も仕事のことが頭から離れず、少しずつメンタルに不調をきたす社員も少なくありません。
そのため、事業所は管理職などに対してハラスメント防止に関する理解を広めると共に、若手社員がストレスをなるべく抱えこまないような職場環境を整える対処をし、若手社員のうつによる休職や退職を防ぐことが大切です。
こちらの衛生講話資料では、ラインケアにおいて重要な新人・部下との接し方について解説しています👇
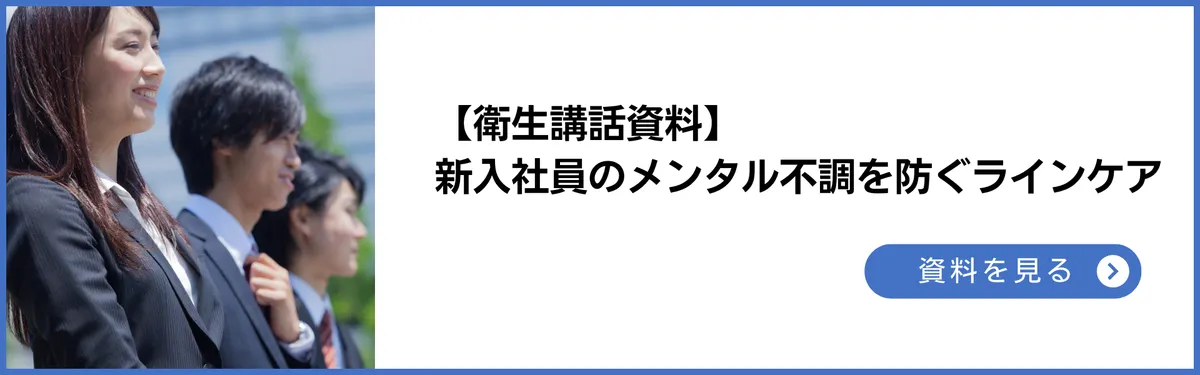
■参考
1)令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要|厚生労働省
2)EAP:用語解説|こころの耳:働く人のメンタルヘルスポータルサイト
3)令和2年 労働試作総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)について|厚生労働省
4)若年労働者へのメンタルヘルス対策 ~セルフケア・ラインケア・家族との連携など~|こころの耳:働く人のメンタルヘルスポータルサイト
■執筆/監修
<執筆>久木田 みすづ (精神保健福祉士、社会福祉士、心理カウンセラー)
福祉系大学卒業後、カウンセリングセンターの勤務を経て、心療内科クリニック・精神科病院で精神保健福祉士・カウンセラーとして従事。うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんと家族に対する相談や支援に力を入れる。
現在は、主にメンタルヘルスの記事を執筆するライターとして活動中。
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』