「音や匂い、人の感情に敏感で、職場で疲弊してしまう……」。HSP(Highly Sensitive Person)という特性を持つ社員が、職場で強いストレスを感じているケースは少なくありません。しかし、HSPは病気ではなく、特性に合った環境があれば本来の力を発揮できる人材です。
この記事では、HSPの特性や職場でのストレス要因を解説し、企業・本人それぞれの視点でできる対策をご紹介します。産業保健スタッフや管理職の方は、HSPの社員が安心して働ける職場づくりのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
<目次>
1.HSPとは?職場で理解しておくべき4つの特徴
2.HSPが職場で感じやすい3つのストレス要因
3.企業が取り組むべきHSP社員へのストレス対策
4.HSPの社員が実践したいセルフケアと働き方の工夫
5.HSPの社員と上手に関わるために|周囲ができる配慮とは
6.まとめ|HSPへの理解と対策が職場全体の安心感につながる
1.HSPとは?職場で理解しておくべき4つの特徴
HSP(Highly Sensitive Person)は、1996年にエレイン・アーロン博士によって提唱された概念で、生まれつき感受性が強く、外部の刺激に敏感な気質を持つ人を意味します。全人口の約15〜20%の人がHSPに該当するとされ、特に職場では環境や人間関係の影響を受けやすい傾向があるのが特徴です。
HSPの人は、以下の4つの特徴(DOES)を持つとされています。
- Depth of Processing(処理の深さ):物事を深く考え、慎重に判断する。直感力に優れている
- Overstimulation(刺激に敏感):音や光、匂い、人の感情変化など社会的な刺激に敏感。刺激の強い環境で疲弊しやすく、回復にはより多くの休息を必要とする
- Emotional Reactivity(情緒的反応):他人の気持ちを感じ取りやすく、共感性が高い
- Sensing the Subtle(些細なことにも気づく):知覚的な鋭さがあり、他人が見逃している些細な変化にも気がつく
HSPの人は上記のような特性があるため、職場のストレスを強く感じやすい傾向があるのです。
また、刺激に敏感な点などのHSP特性は自閉スペクトラム症の特性と似ているように見えますが、脳機能の特徴は異なると言われています。特性の違いとしては、「人の感情変化への敏感さ」や「共感性の高さ」が自閉スペクトラム症の人には認められない点が大きく異なります。
HSPは医学的な診断名や障害名ではなく、「個人の特性」として扱われています。そのため、HSPが病院で診断・治療の対象にはなりません。しかし、ストレスによる不調に対しては、診療やカウンセリングを受けることができます。
2.HSPが職場で感じやすい3つのストレス要因
HSPの人は、職場で以下のようなストレスを感じることが多いです。
- 職場環境によるストレス
- 人間関係によるストレス
- 業務内容によるストレス
それぞれについて解説します。
■職場環境によるストレス
HSPの人は外部の刺激に敏感なため、以下もストレス要因となります。
- オープンオフィスの騒音(電話の音、話し声、タイピング音)
- 照明やエアコンの影響(強すぎる光や寒暖差に敏感)
- 座席の近さ、混雑度合いによる影響(人の気配や動きに敏感)
- 急な業務変更や締め切りへのプレッシャー
音、光などの外部刺激だけでなく、人の気配や動きへの敏感さ、環境変化、突然の予定変更などによる刺激も含まれるのが特徴です。
■人間関係によるストレス
HSPの人は他人の感情変化を敏感に察知する特性があるため、以下の内容もストレス要因となり得ます。
- 上司や同僚の感情の変化に敏感すぎる
- フィードバックを過度に気にしてしまう
- 職場のトラブルや対立を避けようと無理をする
人からの評価や対人関係によるストレスにも敏感なため、HSPでない人に比べて大きなストレスを受けるのが特徴です。
■業務内容によるストレス
HSPの人は、些細な変化に気づく特性があるため、完璧主義になりやすく、以下の内容も大きなストレスとなることが多いです。
- マルチタスクが苦手で、業務負担が増す
- 過度に完璧主義になり、仕事を抱え込む
- ミスを極端に恐れるため、業務効率が下がる
HSPの社員が長期間、安定して働くためには、これらのストレス要因を軽減することが重要です。
3.企業が取り組むべきHSP社員へのストレス対策
HSPの社員が職場への適応を高め、健やかに働き続けるためには、企業と本人、双方のストレス対策の実施が効果的です。
HSPの社員が健やかに働くために、企業側ができるストレス対策を4つ紹介します。
①職種やチーム単位での配置転換
HSPの社員が適性に合った業務を担当できるよう、適性診断や定期的なヒアリングを行います。静かな環境で集中できる部署や、単独作業が多い職種への異動を検討するとHSPの社員が職場に適応しやすくなるでしょう。
②多様な働き方の導入
リモートワークやフレックスタイム制度の導入で、HSPの社員が自分のペースで働ける環境を整えるのも効果的です。リモートワークの導入や1人になれる休憩スペースの確保、イヤホンの使用許可などは、刺激を減らしてHSPの社員のストレスを軽減でき、HSPの社員が疲弊せずに、心身の健康を保ちやすくなります。
③定期的なストレスチェックの実施
HSPの社員は自分のストレスに気づきにくい場合もあるため、定期的なメンタルヘルスチェックを行い、必要に応じて産業保健スタッフによるサポートを行うと効果的です。
④相談窓口の設置
メンタルヘルス相談窓口を設け、HSPの社員がストレスや悩みを気軽に相談できる環境を作りましょう。産業医やカウンセラーとの連携を強化し、専門的なアドバイスを受けられる体制を整えると、適切なタイミングで心身のケアを行うことができます。
カウンセリングサービスの導入にご興味のある方はこちら👇
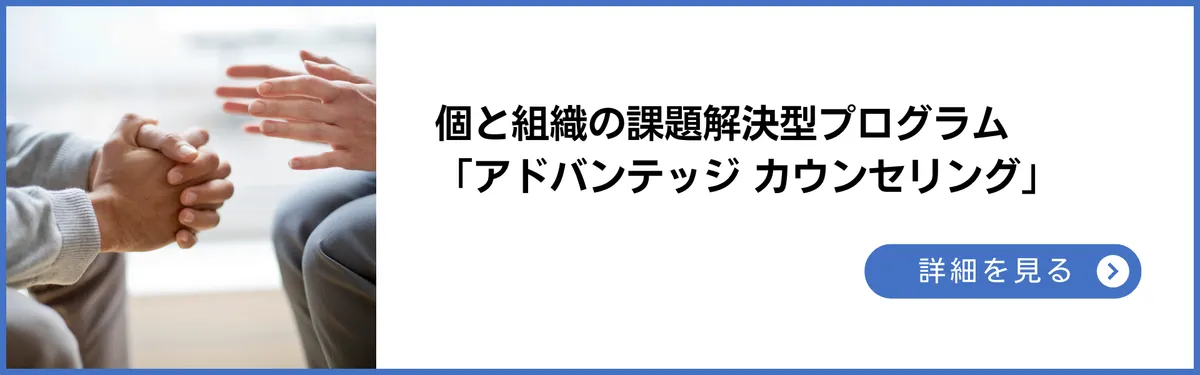
HSPの社員が働きやすい職場環境を整えることは、組織全体の生産性向上にも役立つでしょう。
しかし、すべての要望を実現することは難しいのも事実です。職場のルールや現実的な運用の範囲内で、調整を行うことが必要です。
4.HSPの社員が実践したいセルフケアと働き方の工夫
HSPの社員自身が職場でストレス対策を行うことも非常に重要です。いくら職場環境を整えたとしても、HSPの社員が自己理解を深め、自分に合ったセルフケアを行わないと職場適応度は高まりにくいものです。
ここでは、HSP特性を持つ本人が実施できる職場ストレス対策を以下の3つを紹介します。
Ⅰ.刺激を減らす工夫をする
HSPの特性を持つ人は、以下のような方法で音や光、人の気配などの刺激を減らす工夫をすると、疲労を軽減することができます。
- ノイズキャンセリングイヤホンを活用する
- パソコンのブルーライトカット機能を使う
- 短時間でも1人で休める時間を確保する
特に苦手な刺激は人によって異なります。自分の苦手な刺激について理解して、対策を講じると効果的です。また、イヤホン等については使用前に職場のルールを確認し、不安があれば上司や産業保健スタッフに相談をするようにしましょう。
Ⅱ.仕事の進め方を工夫する
HSP特性を持つ人は、タスクが多いと圧倒されてしまいがちです。以下のような対策を講じることで、落ち着いて業務に取り組むことができるようになるでしょう。
- 仕事を細分化して、1つずつ進める
- 適度な休憩を入れることで、脳の過剰な刺激を避ける
タスクに圧倒されたり、混乱が生じたりしたときには、一旦休憩をとり、落ち着いてからタスクを整理するのも効果的です。
Ⅲ.自分の感情をコントロールする
HSPの特性を持つ人は、他人の感情変化に敏感に反応する傾向があります。自分の感情反応により、苦しさを感じたときには、以下の方法を実行すると効果的です。
- 強い感情や不快感があらわれたら、呼吸法やマインドフルネス瞑想を行う
- 感情を紙に書き出し、自分の思考や感情を客観視する
- 産業医・産業保健スタッフによる個別相談やカウンセリングを利用する
産業保健スタッフが個別に関わり、HSPの社員自身が自己の特性に気づき、自分の特性に合ったセルフケアを行えるようサポートすることも非常に重要です。
保健指導や健康だよりで活用できるセルフケアの無料リーフレットはこちら👇
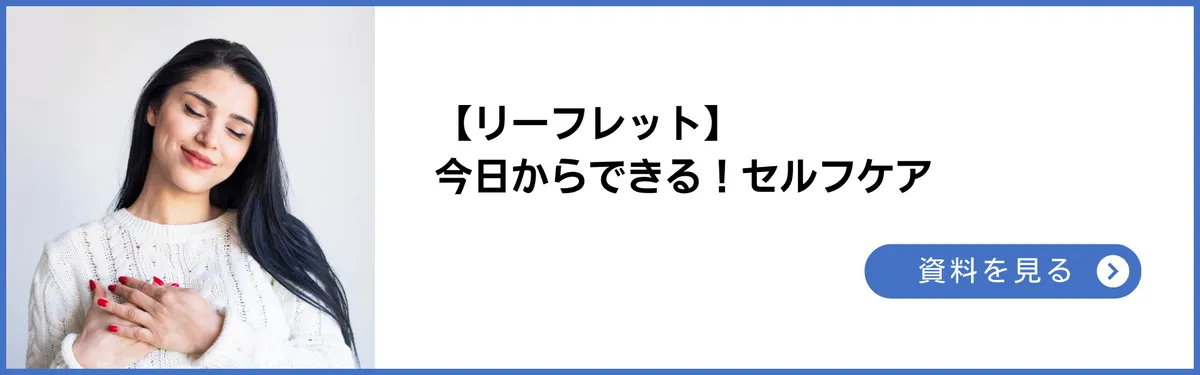
5.HSPの社員と上手に関わるために|周囲ができる配慮とは
HSPの社員が働きやすい職場を作るために、周囲の社員も理解を深めることが大切です。
- 休憩時など1人の時間を尊重し、適度な距離感を持つ
- 「気にしすぎだよ」と言わず、共感する
- 急な予定変更はなるべく避け、事前に知らせる
- 大きな声で叱責や強い怒りの表出など強い感情表現を避ける
- リモートワークやフレックス制度の利用を認める
HSPの特性を理解し、適切なサポートを行うことで、HSPの特性を持つ社員の能力を最大限に発揮できる環境を整えることができます。
6.まとめ|HSPへの理解と対策が職場全体の安心感につながる
HSPの人は職場の環境や人間関係に敏感で、ストレスを感じやすいのが特徴です。HSPの社員自身が自分に合ったストレス対策を取り入れることで、職場適応を高め、心身の状態を安定させ、勤務継続できるようになります。企業は職場環境の改善や柔軟な働き方の導入を行うなど、職場全体でHSPへの理解を深め、サポート体制を整えることが大切です。
HSPの社員が安心して働ける環境を整えることは、企業全体の生産性向上に持つながります。ぜひ本記事を参考に職場環境の改善に取り組みましょう。
■参考
1)エレイン・N・アーロン著. 片桐恵理子訳(2020). 敏感すぎる私の活かし方. パンローリング株式会社.
■執筆/監修
<執筆>桑鶴えみ(保健師、臨床心理士)
精神科医療機関勤務
看護大学卒業後、病棟勤務を経て、企業内の健康相談室やメンタルヘルス・ハラスメント相談室にて相談業務に従事。その後、大学院で臨床心理学を学び、臨床心理士を取得。現在、医療機関が運営するリワークプログラムの所長を務め、プログラム運営や相談業務に従事している。専門は働く人のメンタルヘルス、復職支援。
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』





