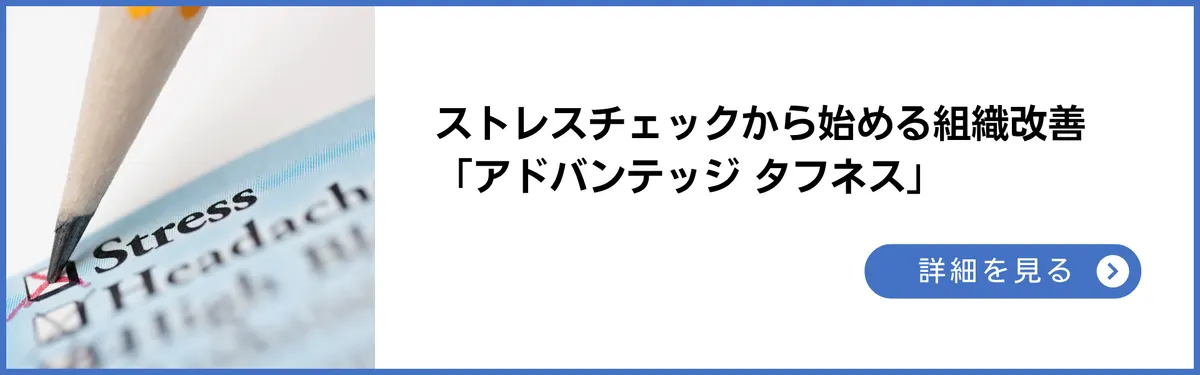AIなどの進化により便利になっている反面で、時間に追われながら忙しく日々過ごすことが多くなった現代人。このような環境下で働いていると、どうしても自分が抱えているストレスに気づけなかったり、気づいていても相談しづらい雰囲気があったりして、そのまま放置してしまうケースが増えてきます。産業保健師は、そのような社員がストレスに気づき、相談しやすい職場環境を整えることが大切です。
この記事では、社員がストレスに気づき、自ら相談できる環境をつくることで、無自覚ストレスを予防できる職場支援について詳しく解説していきます。
<目次>
1.社員のストレス予防のために職場ができる3つのこと
2.社員が相談しやすい環境づくりが大切
3.まとめ
1.社員のストレス予防のために職場ができる3つのこと
ストレスは普通に生活していても、ある程度は感じるものです。しかし、蓄積させないためには各個人がストレス予防のために取り組むことが大切です。
企業で働いている社員のストレス状態が本人も無意識のうちに溜まり過ぎてしまうと、メンタルヘルスの不調を引き起こし、休職・退職に追い込まれるケースが少なくありません。そのため、早い段階に産業保健師を含む職場全体で社員のストレス予防に取り組む必要があるのです。
①ストレスチェックの結果を活用した面談の仕組みづくり
労働者が常時50人を超える企業には、2015年12月よりストレスチェックの実施が義務付けられるようになりました。産業保健師は、そのストレスチェックの結果を見て、ストレスを感じている人や支援が必要と判断された人に対して、面談を行える仕組みを整え、適切な対処法を提案することが大切です。
しかし、ストレスはストレスチェックによって支援が必要と判断された社員本人が自覚していない場合も多くあります。そのため、まずは社員本人に自分自身のストレス状態を自覚してもらい、セルフケアが可能な部分に関しては日常生活の中で出来るセルフケアの提案を行うのも良いでしょう。
また、セルフケアだけではストレスの状態が緩和できない状態の場合は、どのようなことに困っているのか、辛さを感じるのかを聞きながら、ストレスの発生原因を明確にしていくのが大切です。
面談を行う際には、ストレスを抱えている社員のプライバシーが十分に守られるよう配慮することを忘れてはなりません。安心して悩みや困っている問題を話せるように、面談を行う場所の設定を考えるのが良いでしょう。ストレスチェックによって、支援が必要と判断されるレベルの社員の場合は、言葉以外に、本人の態度にも注意を払えるようにしてください。
やりっぱなしで終わらせない、ストレスチェックから始める組織改善サービスはこちら👇
②相談窓口や面談制度の周知
社員のストレス予防のためには、相談窓口や面談制度の周知を忘れてはなりません。産業保健師は、社員が抱えている悩みや困っていることなどメンタルによる不調に対して、個別に相談できる窓口となる役割があります。
ストレスチェックによって、サポートが必要と判断された社員だけでなく、長時間労働になっている社員や勤怠の状態が心配な社員に対しても、体調やメンタル面において不安がないかを聞きながら、必要に応じて社外の専門機関や医療機関への受診を促すことが大切です。
しかし、実際に働いている社員のほとんどが、メンタルの不調を抱えていても相談窓口の存在を知らなかったり、知っていてもプライバシーの問題から相談しにくいと感じたりする人もいます。そうした社員にも気軽にメンタル面での不調を相談できる窓口の存在を知ってもらうことが重要なのです。
労働安全衛生法第69条では、事業者は労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならないと定められています。
また、2022年4月1日には「パワハラ防止法」によってハラスメント相談窓口の設置が企業に義務付けられることも決まりました。
これらの法律面の情報をはじめ、メンタルヘルスの不調に対する相談窓口の設置や面談制度が存在することを、研修などで社員へ徹底して周知する行動が大切になります。
企業が対応すべきハラスメント対策について詳しく知りたい方はこちら👇
③管理職研修などでラインケアを継続的に啓発
近年、メンタルヘルス対策が強化されている中で、ラインケアがより注目されるようになってきました。ラインケアとは、管理職など社員を監督する立場にいる社員が、いつもとは様子が違う部下の状態をいち早く察知して、適切な対処をする取り組みのことを指し、企業が長期的に成長していくためには欠かせないものとなっています。
ラインケアを継続的に行っていくためには、定期的な管理職研修などで効果的な対処法を伝えることが大切です。例えば、口数が減ったり休みがちになったりしている部下はいないか、医療機関への受診が必要なケースはないかを上司が気付けるようにするのが重要になります。
具体的な心身の状態は、産業医の判断が必要になります。しかし、その前に管理職が部下の話に積極的に耳を傾けることの重要性を伝え、部下から相談された時やいつもと様子が違うと感じた時に必要な行動ができるように、啓蒙することが大切です。
ラインケアにおける管理監督者・産業保健スタッフそれぞれの役割を知りたい方はこちら👇
2.社員が相談しやすい環境づくりが大切
無自覚ストレスを予防するためには、何よりも社員が相談しやすい環境づくりが必要不可欠です。一昔前までは、上司の意見には絶対に従うという雰囲気だったり、出世などへの影響を考えて、自分の意見はよほどのことがない限り言わなかったりという環境で仕事をしている人が多い時代もありました。
しかし、そのような職場環境は、社員にネガティブな感情を抱かせ、仕事に対するモチベーションを低下させる要因になります。また、上司に相談しにくい職場環境は、心理的安全性が低く、業務に必要な「報・連・相」が円滑に行われなくなり、結果的にリスクが大きくなるため、企業にとってもデメリットが多くなるのです。
社員の無意識ストレスを防ぐためには、社員1人ひとりが積極的に業務に参加し、何かあった時に相談しやすい風通しの良い人間関係を築ける環境を整える必要があります。
3.まとめ
忙しさや責任感に追われるなかで、ストレスに気づきにくくなっている社員は少なくありません。不調を自覚していても、「これくらいは大丈夫」「相談しにくい」「どこに相談していいかわからない)とがまんし、対応が遅れてしまうこともあります。
こうした状況を防ぐためには、社員自身が心身の変化に気づき、相談できる環境づくりが重要です。ストレスチェック、面談、相談窓口などの仕組みを活用し、本人の気づきを促すと同時に、必要な支援につなげていく体制づくりが求められます。
また、心理的安全性の高い職場は、メンタルヘルス対策だけでなく、組織の活性化や生産性の向上にもつながります。産業保健職や人事部門、管理職が連携しながら、誰もが安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。
■参考
1)ストレスチェック制度導入マニュアル|厚生労働省
2)職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!|厚生労働省
3)職場における心の健康づくり|厚生労働省
■執筆/監修
<執筆>
久木田 みすづ (精神保健福祉士、社会福祉士、心理カウンセラー)
福祉系大学卒業後、カウンセリングセンターの勤務を経て、心療内科クリニック・精神科病院で精神保健福祉士・カウンセラーとして従事。うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんと家族に対する相談や支援に力を入れる。
現在は、主にメンタルヘルスの記事を執筆するライターとして活動中。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』