脳の健康=組織の生産性?ブレインヘルスの基礎・実践方法
職場でのメンタルヘルス対策は多くの企業で行われていますが、働く人の記憶力や集中力の低下は見逃されがちです。ストレスで頭の働きが悪くなると、仕事のミスが増えたり事故が起きやすくなります。本記事では産業保健スタッフができるブレインヘルス対策について解説していきます。
<目次>
1.はじめに-ブレインヘルスとは何か
2.脳の健康を保つ方法
3.産業保健スタッフの取り組み
4.ブレインヘルス対策を始めるポイント
5.まとめ
1.はじめに-ブレインヘルスとは何か
ブレインヘルスとは、近年、健康づくりの分野で提唱されている概念で、「脳の健康を中心に、心や体の健康づくりを進めていく」という考え方です。医学的に統一された定義が確立しているわけではありませんが、働く人の健康保持・増進を支援する新しい視点として、職場の健康づくりや産業保健活動に応用できる可能性があります。
■脳から心身の健康を守る
ブレインヘルスは、脳の健康を軸に心身の状態を総合的に整えるという考え方です。脳の疲労や認知機能の低下が進むと、集中力や判断力が落ち、結果として精神的な疲れや業務パフォーマンスの低下につながる可能性があります。
厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」では、仕事や職業生活に関して強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者の割合は82.7%にのぼります。こうした慢性的なストレスは脳の働きに影響を及ぼす要因の一つと考えられています。
■脳は持続的な負荷で疲労する
脳科学や心理学の研究では、集中状態が長く続くと脳の情報処理効率が低下し、いわゆる「脳の疲労」が起こることが示されています。休憩を取らずに作業を続けると、この疲労が蓄積し、注意力や判断力の低下につながることがあります。
職場では、適切な休息や作業の切り替えを取り入れることで、脳のコンディションを保ち、結果としてミスの防止や業務効率の維持につながると考えられます。ブレインヘルスの取り組みは、こうした働き方の工夫を支援する考え方の一つです。
2.脳の健康を保つ方法
ブレインヘルスの取り組みでは、研究知見を参考にしながら、働く人が認知機能や集中力を維持・向上できる生活習慣を支援します。実施にあたっては、医学的に確立された指針ではないため、安全面や個人の健康状態に配慮することが大切です。
■運動習慣の導入
一部の研究では、前日に中~高強度の運動を30分増やすことで、記憶力の一種であるエピソード記憶や作業記憶が改善する傾向が報告されています(Bloomberg et al., 2024)。ここで言う中~高強度の運動とは、一般的には速歩や軽いジョギング程度の強度です。
職場で運動を促す例としては、スタンディングデスクやラジオ体操の実施、運動プログラムの導入などがあります。安全面や施設環境上の制約を踏まえ、無理のない範囲で実施・検討します。基礎的には、週3回・40分程度の有酸素運動(ウォーキング、階段昇降、自転車など)を目安とし、筋力トレーニングとの組み合わせも有効です。運動習慣のない方は1日10分の歩行から徐々に増やす方法が安全です。
以下の記事では職場でできる簡単なエクササイズや”ながら運動”を紹介していますので、是非参考にしてください👇
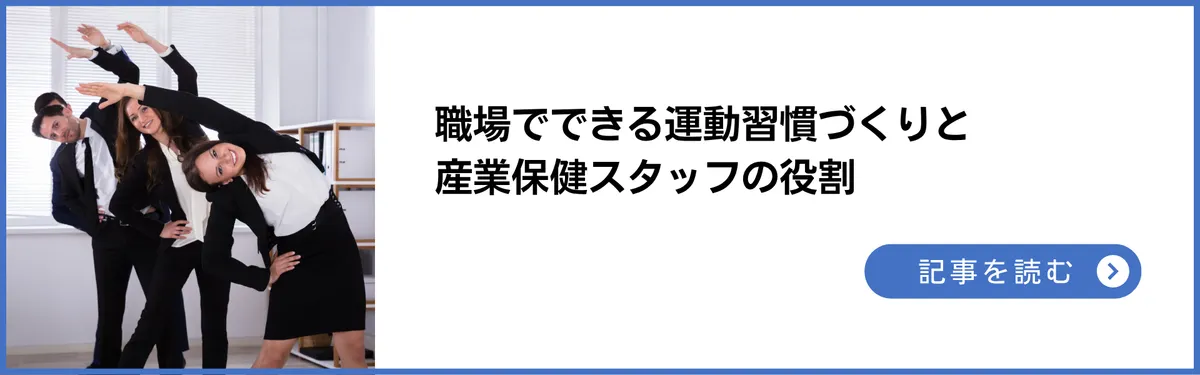
■こまめな休憩
脳は長時間の集中により情報処理効率が低下します。短い時間でもこまめな休憩を取ることは、一見すると作業時間を減らすように見えますが、長期的にはパフォーマンス維持に有効とされます。
例としてポモドーロテクニックがあります。この方法では25分作業、5分休憩のサイクルを繰り返します。休憩中は軽いストレッチや水分補給など、作業から完全に離れることが重要とされています。職場の実情や個人の作業ペースに合わせ、例えば2時間に15分の休憩など、現実的な形で取り入れるとよいでしょう。
■短時間の仮眠(パワーナップ)
一定時間以上の活動が続くと集中力や判断力が落ちやすくなります。職場環境が許せば、15〜30分程度の仮眠が疲労軽減に役立つことがあります。航空宇宙分野の研究では、約26分の仮眠で警戒度や作業パフォーマンスが改善する傾向が示されています。ただし30分を超えると睡眠慣性による眠気が生じやすく、避けたほうがよいとされます。仮眠の直前に適量のカフェインを摂取すると目覚め時に覚醒効果が現れる場合があります。眠れない場合でも、目を閉じて静かに過ごすことは脳の休息につながります。
3.産業保健スタッフの取り組み
産業保健スタッフは、それぞれの専門性を活かしながら、ブレインヘルスという新しい視点を既存の業務に取り入れることができます。
■プレゼンティーズム対策への活用
プレゼンティーズムとは、出勤しているものの心身の不調により十分なパフォーマンスを発揮できない状態のことです。産業医や保健師は、健康相談や保健指導の際に、「集中力が続かない」「判断に時間がかかる」といった訴えに対して、ブレインヘルスという視点からアプローチできます。睡眠不足や運動不足が脳の働きに与える影響を説明することで、従業員の行動変容を促しやすくなるのです。
従来の「疲労回復」という切り口だけでなく、「脳のパフォーマンス向上」「脳のコンディションを整える」という新しい視点を加えることで、社員にとって理解しやすく、モチベーションを保ちやすい健康支援となります。
■社員向け研修の新しい切り口
既存のメンタルヘルス研修やストレスチェック後の情報提供において、ブレインヘルスは新しいテーマとして活用できます。例えば保健師が実施する健康教室で運動・栄養・睡眠の重要性を伝える際に、「生活習慣病予防」だけでなく「記憶力や集中力の向上」という表現を用いると、若手社員や中堅層にも身近に感じてもらいやすくなります。
特に、将来の病気予防よりも日々のパフォーマンスに関心を持つ層に対しては、健康行動への参加を促す効果が期待できます。
■管理職向け研修への導入
管理職向けのラインケア研修においても「脳の疲労のサイン」という視点を追加することが有効です。従来の「メンタルヘルス不調のサイン」に加え、「集中力の低下」「判断ミスの増加」「物忘れの頻発」といった認知機能の変化にも注目するよう意識づけることができます。
これにより、管理職が部下の不調をより早期に発見し、産業保健スタッフへの相談につなげやすくなります。人事労務担当者は、こうした研修資料の作成や、社内報でのブレインヘルス情報の発信を支援できるでしょう。
さんぽLABでは、ラインケアの基礎を紹介する衛生講話資料を無料公開しています。以下よりPDF形式でダウンロードできますので、是非ご活用ください👇
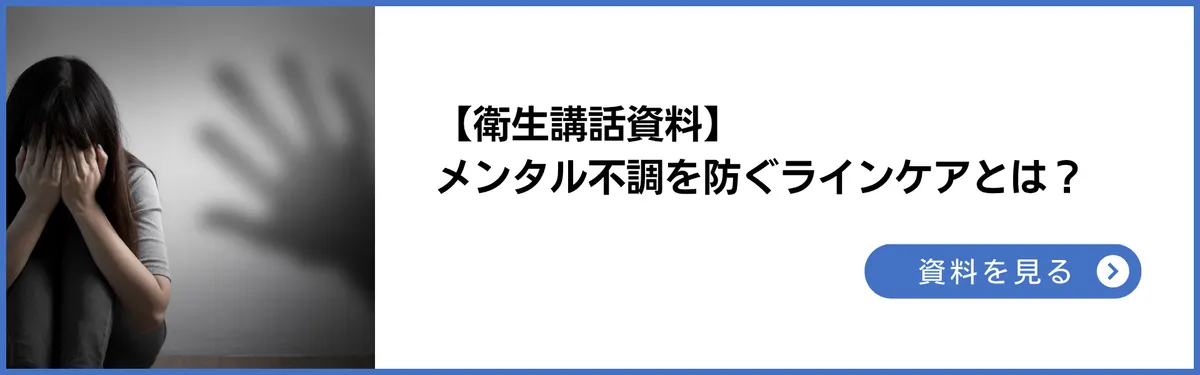
4.ブレインヘルス対策を始めるポイント
ブレインヘルスという新しい視点を、職場の健康づくりに取り入れるための方法を解説します。
■経営陣への提案
ブレインヘルスは現時点では統一された医学的定義や評価指標が確立しているわけではなく、制度化やエビデンスも発展途上です。そのため、経営陣に対しては「職場の健康経営に新しい視点を加える試み」として紹介するスタンスが適切です。
既存の健康経営施策に追加できるテーマとして位置づけ、既存の健康教育や情報提供に「脳の健康」に関する要素を盛り込むことから始める方法などは、提案しやすいでしょう。健康経営優良法人認定のための取り組みを補完し、社員の満足度向上や人材確保といった間接的効果が期待できることも示すとよいでしょう。
■小さく始める
新しい取り組みは、いきなり全社的なプロジェクトとして展開するよりも、小規模な試行から始める方が現実的です。例えば社内報での情報発信や、既存健康セミナーでのテーマの一部として取り上げるなど、無理のない形で組み込むのがよいでしょう。従業員の反応を段階的に確認しながら、内容を充実させていきます。
また、最新の研究動向や他社事例を定期的に収集しておくことで、自社の業種や勤務形態に適した形にアレンジして活用できるでしょう。
5.まとめ
産業保健スタッフによるブレインヘルスの活用は、従来の健康づくり活動に新しい視点を加えるアプローチです。運動・栄養・睡眠の重要性を、「脳の健康」という切り口で伝えることで、従業員の関心を引くことができます。まだ発展途上の概念ですが、社員向けの健康教育や情報提供のテーマの一つとして取り入れることで、職場の健康づくり活動に新たな魅力を加えることができるでしょう。ぜひ本記事を参考に、ご自身の職場での健康教育に「ブレインヘルス」という新しい視点を取り入れてみてください。
当社が提供する従業員向けオンライン健康セミナーでは、幅広いテーマに対応しています。社員向けの健康教育や情報提供にお悩みの方は是非ご活用ください👇
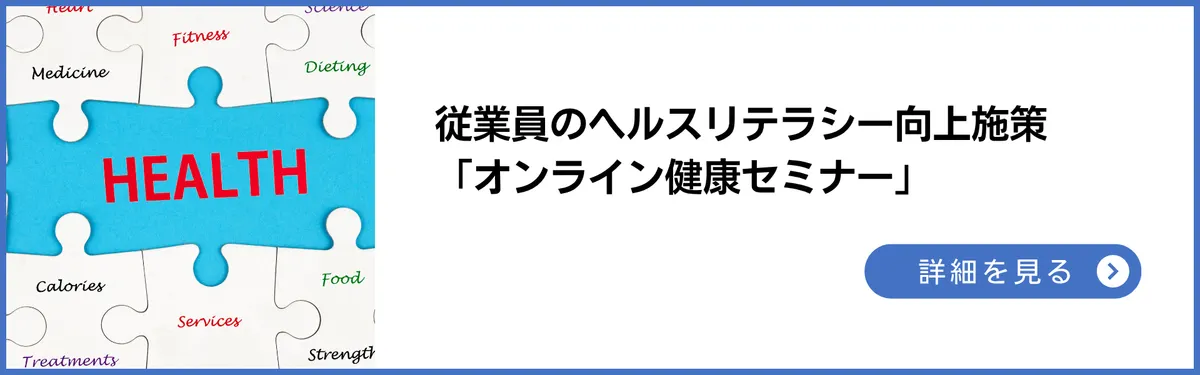
■参考
1)Alertness management: strategic naps in operational settings, MR Rosekind et al., J Sleep Res. 1995 Dec;4(S2):62-66.
2)令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況|厚生労働省
3)運動が支える脳の健康|新潟大学脳研究所
4)日本企業における従業員のライフスタイルと メンタルヘルス関連欠勤率および離職率との関連|順天堂大学
■執筆/監修
<執筆> 豊島優平
幼少期から社交不安に悩まされ、高校時代~独学でメンタルヘルスについて知識を深める。産業技術短期大学校 産業デザイン科を卒業後、2018年~現在まで公認心理師が運営する複数の心理学系メディアにて、執筆・編集を担当。職場のストレス対策~ハラスメント防止など産業保健に関する記事を多数執筆。現在は自身の運営するメディア「マインドフルネス心理学」にて、社交不安を克服した経験をもとに発信活動も行っている。
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』




