「社員の運動不足をどう解消するか?」これは多くの企業が抱える共通の課題です。特に、デスクワーク中心の社員は、不適切な作業姿勢や運動不足が原因で、肩こりや腰痛、頭痛、さらにはメンタルヘルスへの影響につながることもあります。健康経営を実現するためには、社員の運動不足を解消し、日常的に健康を維持できる取り組みが不可欠です。
こうした対策を考えるうえで参考になるのが、リハビリテーションの専門職である作業療法士の視点です。作業療法士は国家資格を持つ医療専門職で、病院や介護施設だけでなく、自宅を訪問して行うリハビリ、デイケアなどの通所施設での支援など、生活の場に近い場所でも活動しています。心身に不調や障害を抱える人に対し、日常の活動やリハビリテーションを通じて、心身の機能回復や健康維持を支援するのが役割です。
本記事では、作業療法士の知見を踏まえつつ、働きながら自然に健康を維持できる仕組みづくりや、産業保健スタッフが果たす役割について、具体的な方法を解説していきます。
<目次>
1.はじめに:運動不足がもたらす健康リスク
2.職場での運動習慣の必要性
3.作業療法士視点のアドバイス
4.産業保健スタッフができる取り組み
5.まとめ:産業保健スタッフがきっかけづくりを担う
1.はじめに:運動不足がもたらす健康リスク
現代の職場で大きな課題となっているのが「運動不足」です。特にデスクワークが増え、1日の大半を座って過ごす社員が多くなり、活動量の低下が目立っています。
こうした運動不足は単に体力の低下を招くだけではなく、生活習慣病のリスクや仕事に影響を及ぼす肩こり・腰痛などの身体症状、さらにはメンタルヘルスの不調にもつながります。
厚生労働省の調査でも、座位時間が長いほど糖尿病や心疾患の発症リスクが高まることが報告されています。近年はテレワークが普及し、通勤やオフィス内移動といった「自然な活動量」が減ったことで、社員の健康課題は一層深刻になっています。
こうしたことから、企業が社員の健康を守るために「職場での運動習慣づくり」に取り組むことは、健康維持に取り組む健康経営の重要なテーマとなっています。
2.職場での運動習慣の必要性
職場の運動習慣を取り入れることは健康経営の面でも重要です。
- デスクワーク・テレワークの増加と身体活動量の減少
- 健康経営の視点
必要性を2つに分けて解説していきます。
◆デスクワーク・テレワークの増加と身体活動量の減少
デスクワークやテレワークが急速に増加したことにより、社員が身体を動かす機会が大きく減ってきています。
長時間の座位や運動不足は、生活習慣病リスクだけではなく、身体的な不調や集中力低下などメンタル不調を引き起こしやすくなります。
その結果、健康リスクや生産性低下を引き起こしています。これは企業にとって病気などによる離職リスクの上昇につながる重大な課題です。
| 影響 | |
|---|---|
| デスクワーク中心 | 原因:長時間の座位姿勢の社員が増加 症状:姿勢の悪化、血流の停滞や筋骨格系の不調 |
| テレワークの普及 | 原因:通勤などの自然な活動の減少、歩数の減少 症状:体力の衰え、体重増加 |
| 生活リズムの変化 | 原因:休息・気分転換の取りにくさ、長時間の座位姿勢 症状:メンタル不調のリスク増加、体力低下 |
まず、職場で運動習慣を意識的に取り入れることは、座りすぎによる健康リスクを防ぎ、身体的な不調を軽減する有効な手段となります。
ストレッチや休憩、歩く習慣が職場にあることで、社員の体調や生産性の維持にもつながってきます。
◆健康経営の視点
職場での運動習慣づくりは、社員の健康維持だけではなく生産性向上や人材定着、さらには企業価値の向上につながる重要な経営戦略です。
社員の健康不調が長引けば、集中力の低下、業務効率の悪化などを招く恐れがあります。こうした状況が積み重なることで、欠勤や休職から最終的には働きづらいと感じる職員の離職まで引き起こし、企業全体にとって大きな経営リスクにつながります。
健康管理は福利厚生だけではなく、経営指標を左右する要素として考えることが不可欠です。
経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」でも、運動習慣の促進は評価項目に含まれています。
職場で運動習慣を取り入れていくことで以下の4つにつながります。
- プレゼンティーズム(出勤していても体調不良で十分に働けない状態)の改善
- アブセンティーズム(病気や不調による欠勤・休職など働けない状態)の減少
- 人材定着
- 企業価値の向上
このように「職場の運動習慣づくり」は、社員の健康維持だけではなく、組織の成長と持続性を強化するのに重要な取り組みです。
産業保健スタッフが中心となり、現場に即した仕組みづくりを推進することが、健康経営の実現に欠かせません。
3.作業療法士視点のアドバイス
◆デスクワーク姿勢と環境の工夫
作業療法士として、環境は心身を維持するうえで欠かせない視点です。
長時間のデスクワークで、どんなに良いストレッチを行っても、椅子やパソコン環境などが悪ければ正しい姿勢を保つことはできません。姿勢の崩れで身体不調を繰り返しパフォーマンス低下にもつながっていきます。
椅子や机の高さ、モニターの位置の環境を変えるだけでも身体的疲労を感じにくくする工夫は可能です。
| デスク環境調整のポイント | |
|---|---|
| 椅子の調節 | 椅子の高さ:膝が90度に曲がり、足裏が床につくことが基本 肘掛けの高さ:肘をおいても肩がすくまず、腕を支えられる高さ 背もたれ:ランバーサポートやクッションがあると腰痛予防になる 座面の奥行:深すぎず、浅すぎない自然に背中が届く位置が理想 |
| パソコン環境 | モニター:目線の水平かやや下に配置 キーボードやマウス:肩がすくまず、肘が90度で操作しやすい場所 |
デスクワークに伴う肩こりや腰痛を予防するには、ストレッチ指導だけでなく、椅子やパソコン環境の調整を組み合わせて支援することが不可欠です。
環境を設定したうえで、運動やストレッチを行うとより効果を発揮します。
さんぽLABでは、保健指導や社内掲示で使えるリーフレットを無料公開しています。デスク環境整備について案内したい場合は以下をご活用ください👇
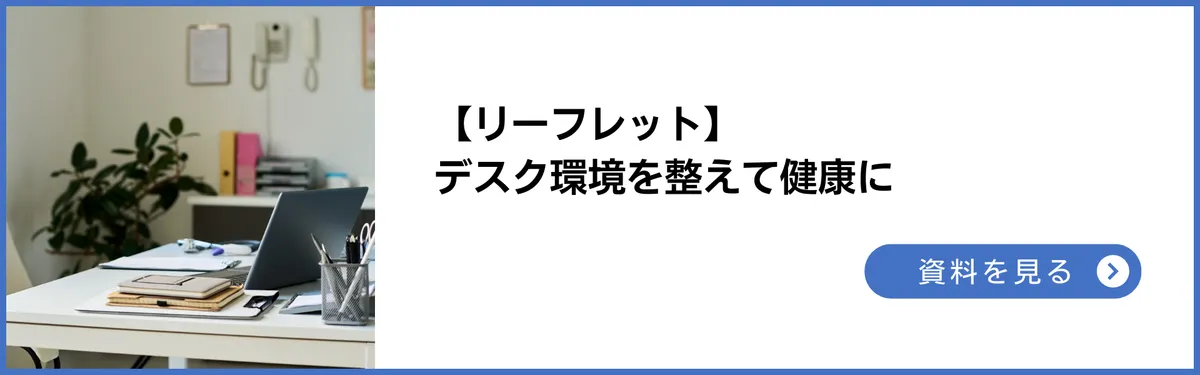
◆簡単なエクササイズ
WHO「身体活動と座位行動ガイドライン(2020年版)」では、成人に対して 週150〜300分の中強度運動と週2回以上の筋力トレーニング が推奨されています。
特に大切なのは、「1回を長時間続けなくても短い時間に分けて行えばよい」「少しでも活動量を増やすことが重要」とされています。
また、厚生労働省でも日常業務の中に取り入れられるストレッチや体操を推奨しています。
つまり、無理のない範囲でこまめに体を動かすことは健康の第一歩につながります。
ここでは、デスクワーク中でも無理なく実践できるストレッチをご紹介します。
| ストレッチの種類 | ストレッチの方法 |
|---|---|
| 首・肩のストレッチ | 椅子に深く腰かけた状態で肩を大きく回す 首はゆっくり横に倒す、回す動きを無理のない範囲で繰り返す |
| 胸のストレッチ | 両手を背中の後ろで組み、胸を開いて深呼吸 |
| 腰伸ばし | 背もたれに寄りかからず、両手を頭上に伸ばして体側を左右に倒す |
| 骨盤前後傾運動 | 座面に腰かけ、骨盤を立てたり倒したりするように前後へゆっくりと動かす |
| 下肢のストレッチ | 椅子に浅く座り、片足を前に伸ばして上体を軽く前に倒す ハムストリングスといわれる太ももの裏を伸ばす |
| 手首のストレッチ | 手のひらを前に出し、反対の手で指を軽く引いて伸ばす これを左右行う |
| 指のグーパー運動 | グーの時に強く握り、パーの時には大きく広げる これを10回程度繰り返す |
簡単でも定期的に継続してストレッチや体操を実施することはデスクワークにおける健康維持に重要です。
◆生活動作に取り入れる“ながら運動”のおすすめ
作業療法士の視点では、日常生活の動作や活動そのものが、健康維持やリハビリにつながる大切な要素です。この考え方は、WHOガイドラインとしても共通しており、特に「長時間でなくても小分けでよい」「少しでも活動量を増やすことが重要」 としています。
その考え方を職場に応用し、日常動作にちょっとした工夫を加えることで、忙しい社員でも無理なく取り組める「ながら運動」が非常に有効となります。
特別な道具や時間を必要とせず、自然に継続できるのが大きな利点です。
■職場でできる「ながら運動」の例
- 電話は立って受ける
- 会議前に肩回しをする
- コピー機の使用中は片足立ちになる
- デスクワーク中に踵上げを行う
- 背もたれを使わずデスクワークをする
- エレベーターは使わず、階段を使う…など
ながら運動は、普段の生活動作を意識するだけで実施でき、健康づくりへの取り組みを始めるきっかけにもなります。
4.産業保健スタッフができる取り組み
効率的な産業保健活動を進めるためには、産業保健スタッフが中心となることが重要です。その中で、実践しやすい第一歩が職場での運動習慣づくりです。
産業保健スタッフは、健康診断や面談の実施だけでなく、職場に健康行動を根付かせる役割があります。
特に運動不足は自分では自覚しにくいテーマであるため、きっかけづくりのためにも積極的な働きかけが必要です。
ここでは産業保健スタッフが実践できる取り組みの紹介をします。
◆ストレッチ習慣の導入
長時間の座位で血流は滞り、肩こりや腰痛が慢性化しやすいという大きな問題があります。そこで、定期的にストレッチを取り入れてもらうことは一つのポイントとなります。
厚生労働省の「職場の健康づくりハンドブック」では、1時間に1回の小休憩と軽いストレッチを推奨しているとされています。
例えば「会議前に肩回しをする」や「席に着く前に腰を伸ばす」など、日常業務の中で習慣化できる取り組みが効果的です。
また、ポスターやリーダー層に実践してもらうことで見える化・共有化につながり習慣にしやすくなります。
腰痛や肩こり予防としてストレッチを紹介したい場合は、以下の無料リーフレットをご活用ください👇

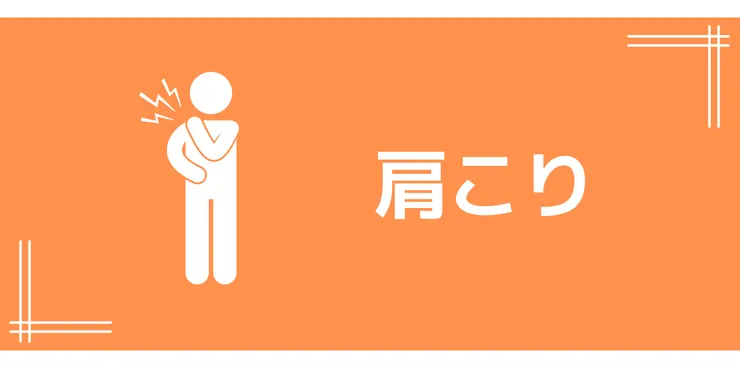
◆環境の工夫
長時間の座位姿勢になってしまうのは、個人の意識だけではなく職場環境も大きく関わっています。環境が整っているからこそ意識が変わることもあります。
まずは、自然に活動量を増やせる仕組みを職場に取り入れることが効果的です。たとえば、導線を工夫して歩く機会を確保したり、階段利用を促すポスターを掲示したりといった、低コストで始められる工夫から取り組めます。
さらに、ワークステーションの多様化も有効です。座る席と立つ席を組み合わせたり、リラックスできるスペースを設けたりすることで、社員が自然に姿勢を変えたり休息を取ったりする機会が増えます。
このように、小さな改善の積み重ねでも職場の環境が変われば、社員の意識づけや運動習慣の定着に直結します。産業保健スタッフが現場に合わせた工夫を提案し、働く人の健康と生産性を同時に支えることが重要です。
◆楽しみながら行える運動イベント
1人の努力だけで運動習慣を長く続けるのは難しいため、全社的な運動のイベントを取り入れることが有効です。
ウォーキングチャレンジやラジオ体操など、誰もが無理なく参加できる仕組みをつくることで、楽しみながら自然と習慣化を促すことができます。
実際に、ある製造業の企業では「始業前の全員体操」を導入し、作業効率向上と腰痛の減少を実現しました。
社内全体の運動会でチーム形式や景品制度を導入すると、ゲーム感覚で参加でき、社員のモチベーションやコミュニケーションが高まります。
こうしたイベントを通じて、健康づくりを業務ではなく文化として根付かせることが重要です。
以下の記事では、全国の産業保健スタッフから募集した健康施策アイデアをまとめてご紹介しています。運動イベント企画の参考にしてください👇
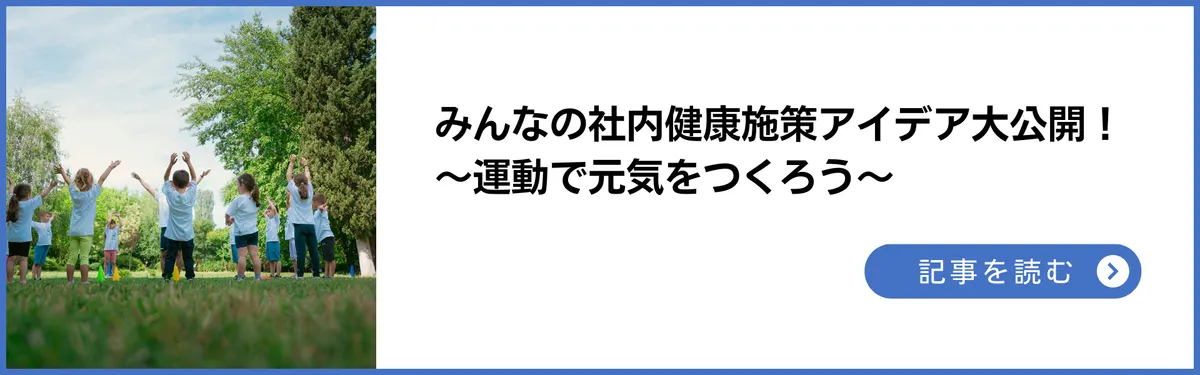
5.まとめ:産業保健スタッフがきっかけづくりを担う
本記事では、職場での運動習慣づくりと産業保健スタッフの役割について解説しました。
デスクワークやテレワークによる運動不足が社員の健康や生産性低下、離職率上昇につながる大きな課題です。
しかし、記事で紹介したストレッチや環境の工夫、ながら運動等の取り組みを進めることで改善は可能です。
こうした取り組みは、社員の定着や企業の発展にも関わるため、産業保健スタッフが中心となって企業への働きかけをすることが不可欠となります。
まずは小さな工夫から始めてみましょう。
■参考
1)座位生活と生活習慣病リスク|厚生労働省
2)健康経営優良法人認定制度|METI/経済産業省
3)職場における心とからだの健康づくりのための手引き~事業場における労働者の健康保持増進のための指針~|厚生労働省
4)身体活動と座位行動ガイドライン(2020年版)|WHO
■執筆/監修
<執筆> ライター飯田(作業療法士)
2018年に作業療法士資格を取得後、総合病院で急性期から訪問リハビリまで幅広く経験。患者さん一人ひとりの生活環境や視点を大切にしながら、支援に力を入れる。
現在はライターとしても活動中。
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』




