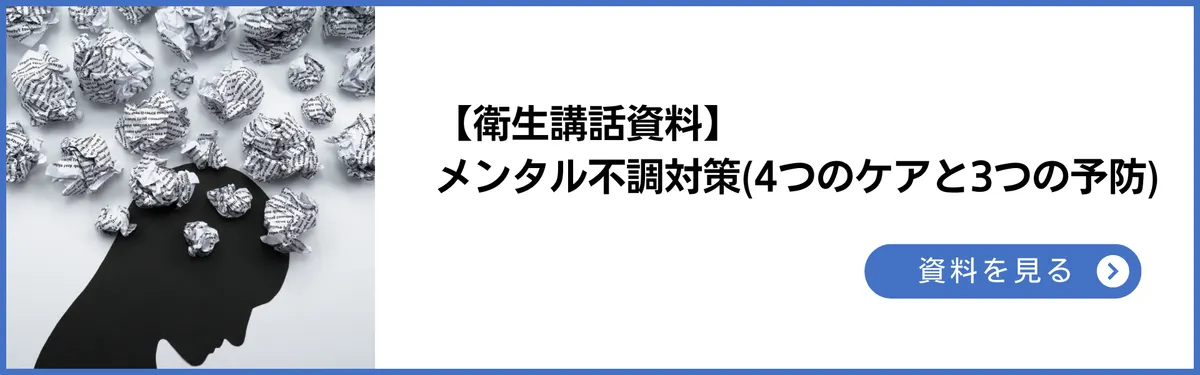不調を抱える社員の相談を受ける中で、ストレスが原因と自覚しているケースもあれば、そうでない場合もあります。自覚が乏しいと、適切な受診やセルフケアに結びつきにくくなることがあります。
ストレスは、度を超えると身体への影響も大きくなることから、ストレス社会で生きていくためには、自分のストレスを自覚し、適切に対処する力が必要になります。ただし、実際に不調をストレスによるものと認識できていないことによって、心身に支障が出て働けなくなってしまう人がいるのも事実です。そのため、社員の心身の健康を管理する産業保健師は、本人が気づけていないストレスに寄り添う支援をしていくことが重要です。
この記事では、無自覚なストレスに寄り添う支援のヒントについて、産業保健職向けに詳しく解説していきます。
<目次>
1.ストレスに気づいていないふりをしている
2.支援の第一歩はストレスに気づいてもらうこと
3.ストレスの自覚がない社員への3つの適切な対応
4.まとめ
1.ストレスに気づいていないふりをしている
通常ストレスは、外部からの刺激によって身体が緊張状態になることを指し、本人にとって辛かったり苦しい状態が継続したりと、心や身体に支障が出てきます。しかし、ストレスを受けている自覚がない場合、自分にとっての苦痛を感じずに過ごしてしまうため、本人はそのつらさを察知できずに、本音を言えないケースが多いのです。
そのため、無自覚なストレスは発見が遅れやすく、心身に大きな影響が出てから対応することになってしまうため、回復までに時間が必要になります。産業保健師は、このような無自覚なストレスを抱えている人の変化を敏感に感じ取り、必要な支援をしていくことが重要です。
2.支援の第一歩はストレスに気づいてもらうこと
無自覚なストレスに寄り添う支援をするためには、まず本人にストレスに気づいてもらうことが大切になります。本人がストレスを自覚しないまま支援をしようとしても、本人が支援を必要とするほどストレスを抱えていないという認識のままでは、サポートが難しくなるからです。
そのため、まずは無自覚なストレスを溜め込むと、日常生活にどのような支障が出るかを理解し、本人がどの程度のストレスを抱えているかを把握することが重要です。
◆無自覚なストレスによって起こること
ストレスは、身体にとって危機的状況に繋がるものなので、本人が自覚していなくても身体にはさまざまな不調が起こってきます。その時点で、周囲の人から指摘されストレスに気づくことができれば良いのですが、そのまま放置してしまうとさらに状態が悪化していきます。
例えば、ストレスによって自律神経が乱れ、めまいや吐き気が起こる場合がありますし、高血圧や頭痛、胃痛や下痢、更年期障害などの病気の引き金になるケースも少なくありません。
また、身体的な面だけでなく、精神面でもイライラしやすく、物や人に当たりやすくなることも。このように、無自覚の状態でストレスを放置し続けてしまうと、心にも体にも不調が引き起こされるのです。
◆無自覚なストレスのサイン
さて、ストレスが溜まっていることを自覚していない状態でも、心や身体からはさまざまなSOSが発せられています。そのSOSであるサインに出来るだけ早く気づくのが、心や身体を守ることにも繋がります。
無自覚なストレスのサインとしては、以下のようなものが挙げられます。
- イライラしやすくなる
- 頭痛やめまいが頻繁に起こる
- 食欲がなくなる
- 過食気味になる
- アルコールやたばこの摂取量が多くなる
- 仕事でのミスが多くなる
- 自分自身を必要以上に責めるようになる
- 外出するのが億劫になる
- 身だしなみに気を遣わなくなる
- 体調を崩しやすくなる
- 身体が疲れていても眠れなくなる
- 欠勤や遅刻が多くなる
など
無自覚なストレスが溜まると、身体に多くの不調が生じて本人が自覚できるようなサインが現れます。同時に、ストレスを発散しようとする行動も増えるため、アルコールやたばこの摂取量がいつもより増える場合もあるでしょう。
また、自律神経の乱れによってしっかり眠れなくなったり、疲れが取れずにミスが増え、出勤するのが困難な状態になったりするケースもあるのです。
3.ストレスの自覚がない社員への3つの適切な対応
ストレスの自覚がない人は、自分自身のストレス状態を正確に把握できないケースが少なくありません。そのため、無自覚のままストレスを放置してしまいがちで、それによって心身の状態が悪くなり、退職や休職へ繋がってしまうことがあります。
無自覚なストレスを放置することで生じる退職や休職を防ぐためには、まわりからの適切な対応やサポートがポイントとなります。
①ストレスチェックを行う
ストレスチェックは、従業員が常時50名以上いる事業所で実施が義務化されています。ストレスチェックは社員のストレス状態を把握し、メンタルヘルスの不調を早期に発見したり、悪化したりするのを防ぐことができるものです。
例えば、仕事上における目に見えないストレスから身体に表れているストレスまで点数化するのが可能なので、社員本人も自覚していないストレスを気づくことにも繋がります。
やりっぱなしで終わらせない、ストレスチェックから始める組織改善サービスはこちら👇
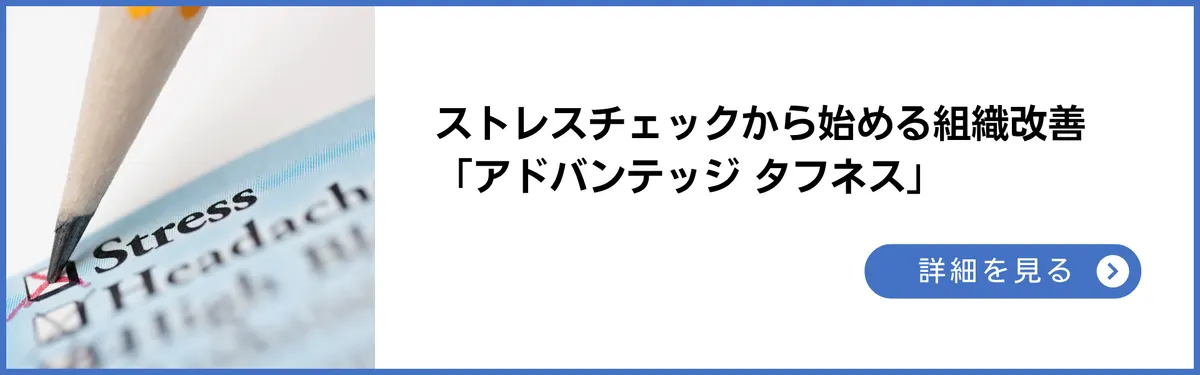
②人事と連携して必要なサポートをする
ストレスチェックを実施した結果、高ストレス者と認定された社員に関しては、面談などを通してどのようなストレスを抱えているかを詳しく相談する場を設けるのが好ましいでしょう。
例えば、仕事上で上司との関係性に悩んでいたり、業務量や勤務時間などに関して辛かったりする場合は、異動や配置転換などを人事と連携しながら検討することも大切です。
面談時には、以下のようなアプローチを試してみるのもよいでしょう。
- 客観的な変化のフィードバック(例:「以前より疲れているように見えます」)
- ストレスによる体調変化の仕組みを簡潔に説明
- 抽象的な質問ではなく、具体的に訪ねてみる(例:「最近眠れていますか?」「食事はとれていますか?」)
仕事上のストレスは、社員本人は自覚していない・気づいていないケースも多く、「このくらいのストレスは当たり前」という感覚で受け止めている場合も多いため、本人の心身が崩れてしまう前に仕事が続けられるサポートを行なってください。
③必要な制度の説明や医療機関への受診をすすめる
ストレスを自覚できない社員の中には、ストレスを自覚し不調を感じてしまったら、仕事を辞めなければならないと思っている人もいます。
実際、従業員50名以上の企業に義務化されているストレスチェックを実施し、それによって「高ストレス者」と認定されても、産業保健師との面談を拒否する人も一定数います。そのため、必要な支援を行うためには、本人がストレス状態を把握し、その上で仕事を負担の少ない範囲で続けられる制度があることを理解できるようにする点も大切です。
ストレスによって、心身に不調が出ている場合であっても、時短勤務や配置転換などによって働きやすい環境を整えるのは可能ですし、必要に応じて医療機関を受診し適切な治療を受け、負担を軽くすることもできます。
これらを社員に説明する場を作り、社員の不安を取り除きながら、ストレスを緩和していく支援が必要です。
4.まとめ
ストレスは、自覚がないと本人は平気だと思うケースが多く、本人自体も不調を招くほどのストレスを抱えていると気づけない場合が多いです。しかし、実際にはメンタルヘルスの不調のサインが出ていることも少なくなく、仕事のパフォーマンスが落ちる場合もめずらしくありません。
そのため、産業保健師がいかに早い段階で社員のストレスに気づき、適切な支援を行うかが重要になってきます。今回は、社員の無自覚なストレスに気づき、適切な対応をするための方法を紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。
■執筆/監修
<執筆>
久木田 みすづ (精神保健福祉士、社会福祉士、心理カウンセラー)
福祉系大学卒業後、カウンセリングセンターの勤務を経て、心療内科クリニック・精神科病院で精神保健福祉士・カウンセラーとして従事。うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんと家族に対する相談や支援に力を入れる。
現在は、主にメンタルヘルスの記事を執筆するライターとして活動中。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』