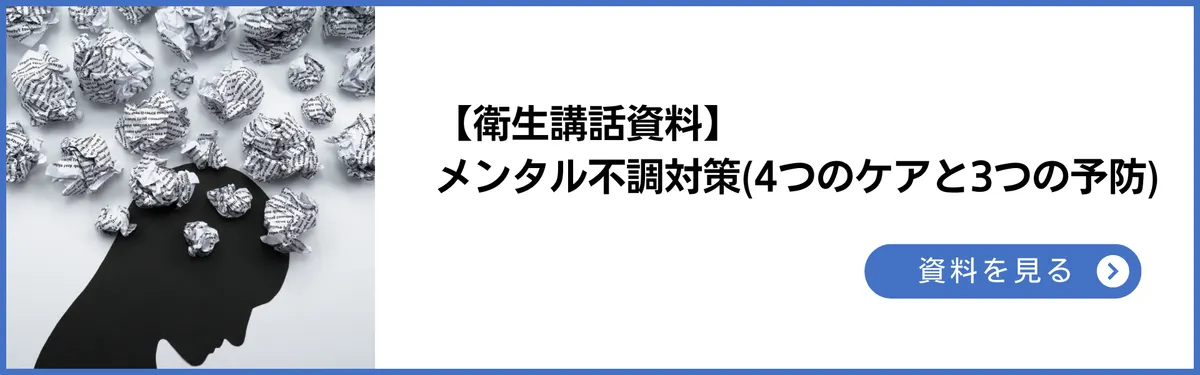ストレスを自覚できない社員にどう気づく?観察とヒアリングのポイント
ストレスは、客観的に見てストレスだと感じるものから、日常の中で少しずつ蓄積する小さなストレスまでさまざまです。しかし、ストレスを自覚できないまま放置すると、やがて心身への影響が大きくなり、仕事が続けられなくなる可能性があるため注意が必要になります。最近では、 不調を感じながらも、相談や受診に踏み出せない社員が増え、体調を崩して退職を余儀なくされるケースもあり、優秀な人材を失わないためにも事業所としての対応が求められているのです。
この記事では、ストレスを自覚できない社員に気づくための観察とヒアリングのポイントなどを解説していきます。
<目次>
1.【社員のストレスサイン】見逃しを防ぐために
2.【気づかないと危険】社員のストレスチェック方法
3.従業員をストレスから守るために産業保健師ができる3つのこと
4.まとめ
1.【社員のストレスサイン】見逃しを防ぐために
社員本人がストレスを自覚できなくても、少なからず仕事中にストレスサインは出ています。そのストレスサインを、出来るだけ早く察知することが重要です。
社員のストレスサインとしては、
- 仕事でのミスが増える
- 遅刻・欠勤が増える
- 仕事の効率が下がり納期までに仕上げられない
などが挙げられます。
◆仕事でのミスが増える
仕事で出やすいストレスサインの代表が、仕事でのミスが増えるというものです。社員本人は、いつも通りに仕事に集中しているつもりでも、なぜかミスが増えて取引先からクレームが増えてしまったり、上司からの指示通りに業務が進められないなど、明らかにそれまでの状態とは異なるミスが増えてきたりします。
単に確認作業が疎かになっているケースも考えられますが、一緒に仕事をしている上司や同僚ならば、「いつもならこんなミスはしない」といった変化に気づくはずです。このような、いつもとは異なるちょっとしたミスが重なったときなどは、社員自身が自覚していなくても、ストレスサインの可能性が高いということを覚えておくのが大切です。
◆遅刻・欠勤が増える
ストレスが溜まってくると、自律神経が乱れ、しっかり睡眠時間を確保していると思っていても、眠りの質が悪くなります。そのため、疲れが十分に取れないまま翌朝を迎えることが増えるでしょう。そうなると、本人は会社へ行こうと身体を動かそうとするのですが、準備に時間がかかったり、時間通りに起きれなかったりして支障が出始めてくるのです。
今まできちんと定時に出社していた社員が、徐々に遅刻・欠勤が増えた時には、ストレスサインかもしれないと気づくべきと言えます。
◆仕事の効率が下がり納期までに仕上げられない
ストレスが溜まって自律神経が乱れてくると、仕事のパフォーマンスが落ち、集中力が低下するとされています。例えば、今まで仕事の効率を考えて優先順位を決めながら作業出来ていたことも、ミスが増えて効率が悪くなり、期限内に仕事が終わらないケースが増えてくるのです。
仕事に対して真面目で、納期に遅れたことがない社員の場合、このような変化もストレスサインと言えるでしょう。
2.【気づかないと危険】社員のストレスチェック方法
従業員が50人以上の企業では、従業員に対して年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。このストレスチェックによって、ストレスを自覚できない社員を早期に発見でき、ストレスによるメンタルの不調を未然に防ぐことが期待できるでしょう。
厚生労働省が推奨している簡易ストレスチェック項目などを活用して、全社員を対象に体調面や感情面の変化を把握するのが効果的です。ストレスが溜まってくると、本人が自覚できなくてもメンタル面や身体面などに、普段とは異なる特徴が出てきます。
例えば、精神面での変化としては、
- 落ち込みやすい
- ミスをした時に必要以上に自分を責めてしまう
- 以前は楽しいと感じていたものが楽しめない
- イライラしやすい
- 涙もろくなる
などが挙げられます。
身体面の変化としては、
- 風邪をひきやすくなって欠勤が多くなる
- 食欲が低下する
- 体重が減少する
- 眠れない
- 胃腸の調子が悪くなる
- 頭痛
などが挙げられます。
このような変化も、ストレスチェックと共に把握すると、社員のストレスフルな状態を早期に発見することに繋がるでしょう。
3.従業員をストレスから守るために産業保健師ができる3つのこと
ストレスを自覚できない従業員は、自分の異変を察知することができずに、気づいた時には仕事が続けられない状況に追い込まれてしまうケースが少なくありません。そこまで悪化する前に、上司はできるだけ早い段階で従業員のストレス状態を把握しておく必要があります。
◆定期的な従業員との面談を実施する
ストレスを自覚できない社員は、自分がそれほどストレスをかかえているという実感がないため、同じ場所で働いている上司がストレスなどについて聞いても、「特に問題ない」という結果で終わってしまうケースがあります。
しかし、産業保健師は社員の健康管理や指導をする役割を担っているので、健康に関する面談として個人的に相談できる場を設ける(1on1など)ことで、直接仕事で悩んでいなくてもストレスを抱えている状態かどうかの把握ができます。
話をしているうちに、仕事上で困っている問題を相談し始めるケースもあり、そこからストレスの緩和に繋げる対策を考えられる場合もあります。
◆ストレスチェックの実施
ストレスを自覚できない社員は、なかなか「ストレス」自体に気づかない傾向があります。そのため、チェック項目として客観的に状態をチェックする機会があると、自分が今置かれている状態がストレスなのかを自覚するきっかけになり、解決へと繋げられる足がかりになります。
ストレスチェックは、厚生労働省が推奨している項目の他にも、さまざまな形式のものがあるため、職種ごとに社員が答えやすいストレスチェックを活用して、メンタルの状態を把握できる機会を設けると良いでしょう。
やりっぱなしで終わらせない、ストレスチェックから始める組織改善サービスはこちら👇
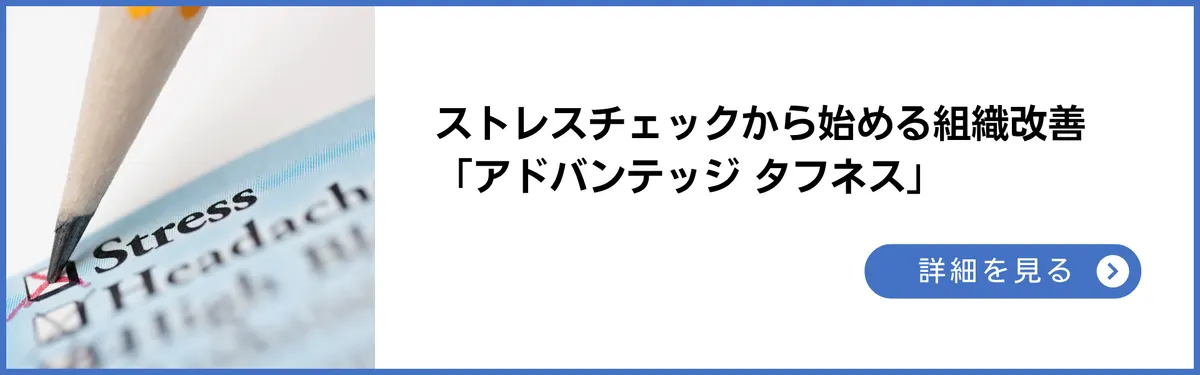
◆専門機関との連携や適切な制度の紹介
社員との面談やストレスチェックを行った結果、ストレスが溜まっていて心身の状態に影響が出ている場合は、さまざまなサポートを行うことが大切です。
例えば、自覚はしていなかったけれど、上司の仕事のやり方が合わなかったり、職場の環境によってストレスが溜まったりしている状態ならば、人事部と連携しながら、異動や勤務時間などの調整を行うのも視野に入れるのが好ましいでしょう。
また、プライベートの悩みによるストレスや睡眠不足などから仕事に支障が出ているような場合は産業医へと繋いだり、医療機関への受診を促したり、時短勤務などの相談に乗ることも必要です。
4.まとめ
ストレスは、気づかないまま溜まって放置するとメンタル面だけでなく、身体的にも影響が出てしまいます。結果的に仕事が続けられない状況に繋がる危険があるので、ストレスが自覚できない社員ほど早期にストレス状態を把握しておくことが大切です。
本人が自覚していなくても、ストレスサインは普段の生活の中で少なからず出てくるものなので、ストレスチェックも上手に活用しながら、社員の心身の健康を管理できるようにしましょう。
■執筆/監修
<執筆>
久木田 みすづ (精神保健福祉士、社会福祉士、心理カウンセラー)
福祉系大学卒業後、カウンセリングセンターの勤務を経て、心療内科クリニック・精神科病院で精神保健福祉士・カウンセラーとして従事。うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんと家族に対する相談や支援に力を入れる。
現在は、主にメンタルヘルスの記事を執筆するライターとして活動中。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』