ハラスメントとは、相手に対して不快感や苦痛を与える行為や言動のことを指します。力関係や権力の差を背景にするという特徴があることから、職場環境の中で発生しやすく、相手の尊厳を傷つけたり、心理的・身体的な負担を引き起こしたりします。セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントに加え、マタニティハラスメント、カスタマーハラスメントなど、最近では、企業にはさまざまなハラスメント対策が求められるようになりました。管理職向けにハラスメント防止研修を行うことは当たり前になってきましたが、最近では『パワハラを恐れて、部下への指導をためらってしまう』といった悩みも聞かれます。
そうかと思えば、部下からも「もっと厳しく指導をしてほしい」と物足りなさを感じていることもあります。ハラスメントなのか指導や注意の範囲内なのか、境界線が不明瞭なところがあり、ハラスメントという言葉は定着したものの、具体的な対策をとるのが難しいと感じている企業は多いのではないでしょうか。
また、産業保健師としても、社員や上司からの健康相談の中で、ハラスメントに関連する相談を受けることがあります。ハラスメント相談への対応について、法令やガイドラインに基づく、適切な手順で対応することが重要です。今回は、企業に求められている対応と、産業保健師として果たせる役割についてご紹介します。
<目次>
1.産業保健スタッフが把握しておきたい最新の傾向
2.職場で起こりうるハラスメントの種類と特徴
3.ハラスメント相談に対して企業に求められている対応
4.産業保健師に求められる対応と留意点
5.まとめ:ハラスメント撲滅月間を契機にできること
1.産業保健スタッフが把握しておきたい最新の傾向
2020年6月に施行されたパワハラ防止法によりその関心は益々高まった背景があるにも関わらず、ハラスメントが関係していると思われる個別労働紛争の発生件数は、ここ数年横ばいの傾向です。横ばいである理由としては、ハラスメントかどうかの判断が難しい、管理職の意識が低い、理解不足、発生状況を把握することが困難といったことがあげられます。
厚生労働省が令和5年度に行った実態調査では9割以上の企業が何かしらの対策を取り組んでいると回答しています。具体的なものとしては、相談窓口の設置と周知、方針の明確化と周知と啓発といったものがあげられます。法律の施行云々以前に、ひとたびハラスメントが発生すると、従業員から損害賠償を求められるだけではありません。対応が不適切だった場合、世間に公表される恐れがあり、社会的な信頼の喪失につながり、深刻な被害をもたらします。
今後、企業にはハラスメント対策を講じつつ、発生した場合の対応方法が求められます。「まだうちは相談がないから大丈夫」と思っている企業でも、実際には既にハラスメントが発生している、もしくは今後発生する可能性があるかもしれないと認識しておくべきでしょう。
2.職場で起こりうるハラスメントの種類と特徴
厚生労働省は、ハラスメントについて「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義しています。代表的なものとして、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどが挙げられます。それぞれ、法令や厚労省ガイドラインに基づく定義と特徴を紹介します。
【パワーハラスメント】
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる① 優越的な関係を背景とした言動であって、② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③ 労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、企業規模を問わず事業主に雇用管理上の措置を義務付けています。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
【セクシュアルハラスメント】
男女雇用機会均等法は、セクシュアルハラスメントを含む性別に基づく差別を禁止し、職場における平等な機会を確保することを目的としています。職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。具体的な例としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと等、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為等があげられます。セクシュアルハラスメントについては、ハラスメントの中でも近年、減少傾向にあります。
【マタニティハラスメント】
「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。男女雇用機会均等法と育児・介護休業法によって義務付けられたもので、妊娠の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。「業務が回らないから」といった理由で上司が休業を妨げる場合はハラスメントに該当します。男性の育児休業取得に向け、上司や同僚から阻害され取得を諦めざるを得ない状況に陥るケースも含まれます。
その他のハラスメントについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇
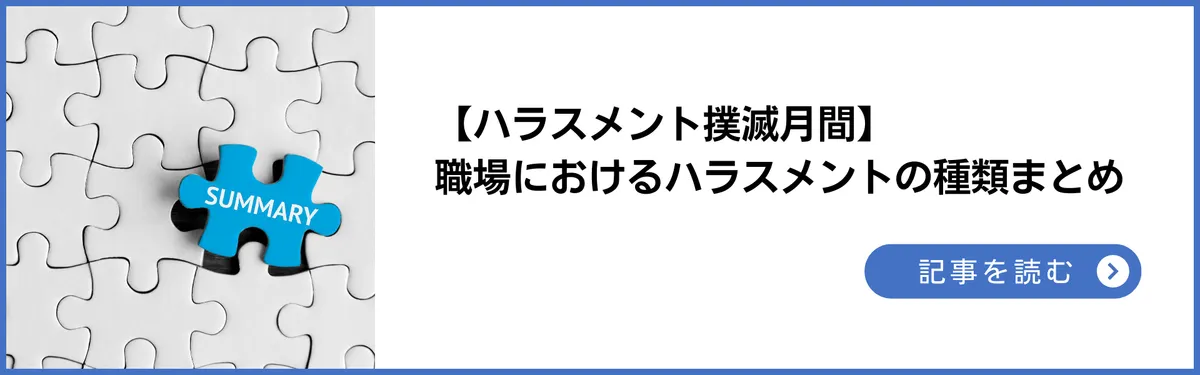
3.ハラスメント相談に対して企業に求められている対応
2022年4月の改正労働施策総合推進法により、すべての企業(中小企業を含む)ハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。相談窓口の役割は、従業員から相談を受けた際に迅速かつ中立的に対応し、被害者の意向を確認しながら心身の保護に配慮することです。相談者が不利益な扱いを受けないよう守秘義務を守り、当事者や関係者に聞き取りを行う際にはプライバシーに十分注意する必要があります。
ただし、ハラスメントに該当するかどうかや、懲戒処分や配置転換などの判断は、窓口担当者が行うものではなく、調査結果を踏まえて会社として判断・決定します。また、会社としての結論を関係者にフィードバックし、再発防止の取り組みにつなげていくことが求められています。
4.産業保健師に求められる対応と留意点
メンタル不調を訴える従業員の中には、背景にハラスメントが関与している場合があります。ハラスメントを受けているという自覚がないケースもあるため、産業保健師には従業員の話を丁寧に聞き取る傾聴スキルが欠かせません。
ハラスメントが疑われる場合には、従業員の訴えを整理し、本人の同意を得た上で、必要な範囲で人事やハラスメント相談窓口に情報を共有します。前述のとおり、ハラスメントか否かの最終判断は会社が正式な調査を経て行いますので、相談窓口の担当者は「それはパワハラだと思う」というような発言は控える必要があります。
また、会社としての調査や対応の最中に、被害者や関係者(場合によっては加害者も)が体調を崩すことがあります。そのため産業保健スタッフは、健康リスクの評価や就業上の措置に関する助言など、通常の健康管理と同様の支援も求められます。
ハラスメント対応における産業保健師の役割の範囲は企業によって異なりますが、傾聴・整理・連携、そして健康管理の支援というスキルが求められています。
5.まとめ:ハラスメント撲滅月間を契機にできること
近年、多様性の普及により、集団よりも個人の考え方が尊重される時代です。企業としては形式的なハラスメント対策ではなく、実質的な対策が求められ、個々人に応じて柔軟に対応していかなければなりません。日頃から、ハラスメント研修等を繰り返し実施したり、職場内のコミュニケーションを活性化させることで、従業員の意識改革を促し、企業文化として根付かせることが重要です。特に、日頃からの上司・部下間、同僚間での活発なコミュニケーションは重要です。何気ないコミュニケーションをとることで、ハラスメントの大半は予防することができます。
厚生労働省は、毎年12月はハラスメント撲滅月間として定めています。多くの企業が繁忙期を迎え、日々の忙しさによりハラスメントが発生しやすい時期でもあります。忙しい時期だからこそ、従業員に対して自分自身が被害者にも加害者にもならないよう、我が身を振り返る時間を設け、心のゆとりをもつように呼び掛けハラスメントの広報や啓発活動を行うのに良い機会です。産業保健師として、企業風土に即したハラスメント対策をとるための活動月間にしてみてはいかがでしょうか。
さんぽLABでは、ハラスメント対策について判例・労災例をもとに解説した衛生講話資料を無料公開しております。PDF形式でダウンロードできますので、是非ご活用ください👇
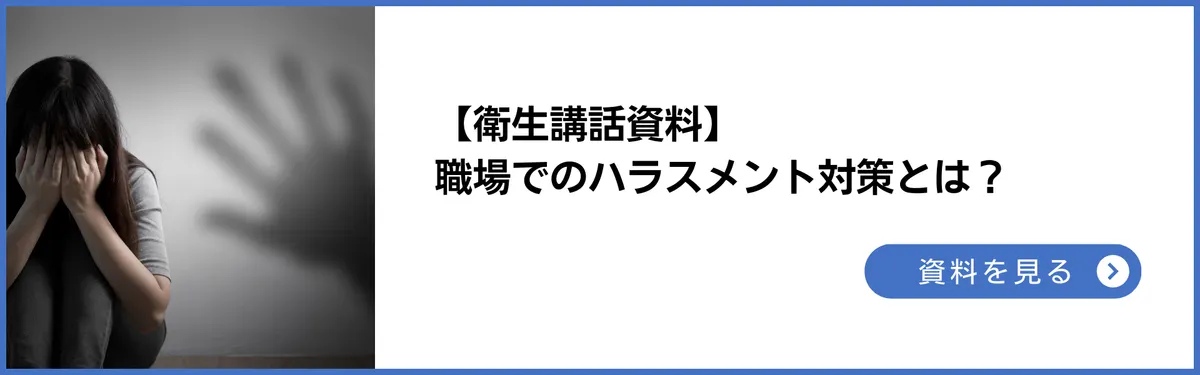
■参考
1)職場のハラスメントに関する実態調査 概要(令和5年度厚生労働省委託事業)|厚生労働省
2)職場におけるハラスメント 対策パンフレット|厚生労働省
■執筆/監修
<執筆>
阿部 春香(保健師、産業カウンセラー、第一種衛生管理者)
日本産業衛生学会、日本産業保健師会に所属する。2024年に日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度登録者として登録する。
広島大学大学院(博士課程前期)を修了後、健診施設に勤務する。現在、中小企業の保健師として勤務し、健康経営の推進を行っている。
働く全ての人に産業保健を届けたいという思いから、産業保健職として産業保健の社会的認知を広げるための活動も行っている。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』




