年末は業務量の増加や人員不足により、労働災害(労災)のリスクが特に高まる時期です。実際、製造業・物流業・小売業・建設業など幅広い職種で事故や体調不良が多発しています。
本記事では、年末に起こりやすい労災の具体例と、衛生管理者が実施すべき予防策・安全衛生活動の強化ポイントを解説します。繁忙期に労災を防ぎ、従業員の「健康」と「安全」を守るための実践的なヒントを押さえましょう。
<目次>
1.はじめに:なぜ年末に労災が増えるのか?
2.繁忙期に起こりやすい労災とは
3.衛生管理者がとるべき事前対策
4.年末に向けた安全衛生活動の強化策
5.まとめ:繁忙期こそ「健康」と「安全」の両立を
1.はじめに:なぜ年末に労災が増えるのか?
年末になると、クリスマスやお歳暮、お正月といったイベントごとや、人が集まる機会が増えることなどを起因として、製造業・物流業・小売業や飲食業などを含むサービス業などの業種で業務負荷が増加します。
繁忙期に伴う長時間労働や作業スピードの加速、人員不足による無理な対応が発生しやすく、それにより労働災害のリスクが高まるのがこの時期の特徴です。
例えば、厚生労働省の令和5年度の労働災害統計確定値を見ると、製造業、建設業では特に12月、1月において死亡災害の発生件数が多くみられます。
年末は業績や納期に対するプレッシャーも強まりやすく、注意力が散漫になりがちです。これらの要因が重なることで、年末は潜在的な労災リスクが高まりやすくなっています。
厚生労働省の後援のもと、中央労働災害防止協会では、毎年「年末年始無災害運動」を提唱しています。
働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、例年12月1日〜翌年1月15日までの期間に提唱されています。
こういったことから、12月~1月半ばまでの年末年始は、労災リスクが高まるため意識的に労災防止に向けた取り組みを行うことが必要です。
さんぽLABでは、長時間労働による健康リスクや、会社の責任について解説した衛生講話資料を無料公開しています。以下よりPDF形式でダウンロードできますので、是非ご活用ください👇
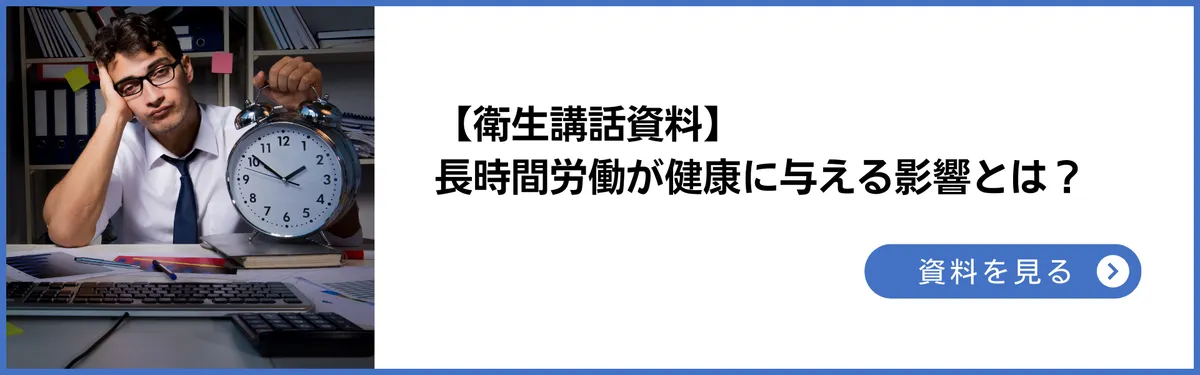
2.繁忙期に起こりやすい労災とは
先に述べたように、年末の繁忙期は短納期の業務が集中し、過重労働・長時間労働が発生しやすくなります。その結果、疲労や睡眠不足による判断力・注意力の低下が起こり、労災リスクを高めます。
また、業務負荷増加のニーズに応えるため、アルバイトや短期雇用者の受け入れを行う企業も多いでしょう。しかし、それにより安全教育の不徹底や不慣れな作業によるヒューマンエラーが起こりやすくなることも考えられ、労災リスクを高める一因となります。
加えて、寒さによる身体機能の低下や路面の凍結など、季節的な環境変化も労災リスクを高める要因となります。これらの原因から考えうる主な労災事例は以下の通りです。
◆製造業
- 機械への挟まれ・巻き込まれ事故
- 重量物の持ち運びによる腰痛・筋肉損傷
- フォークリフトや搬送車の接触・転倒事故
◆物流業
- 荷積み・荷下ろし中の腰痛、ぎっくり腰
- 運転中の交通事故
- 荷物の落下や衝突による打撲・骨折
◆小売業
- 陳列・品出し作業時の転倒・落下物による負傷
- 高所作業(脚立・棚上など)の転落事故
- 混雑店舗での接触・転倒
◆建設業
- 足場や高所からの墜落
- 凍結路面や積雪による転倒
- 寒冷環境下での低体温症などの体調不良
業種別の労災傾向や、具体的な安全対策の立案方法について知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇
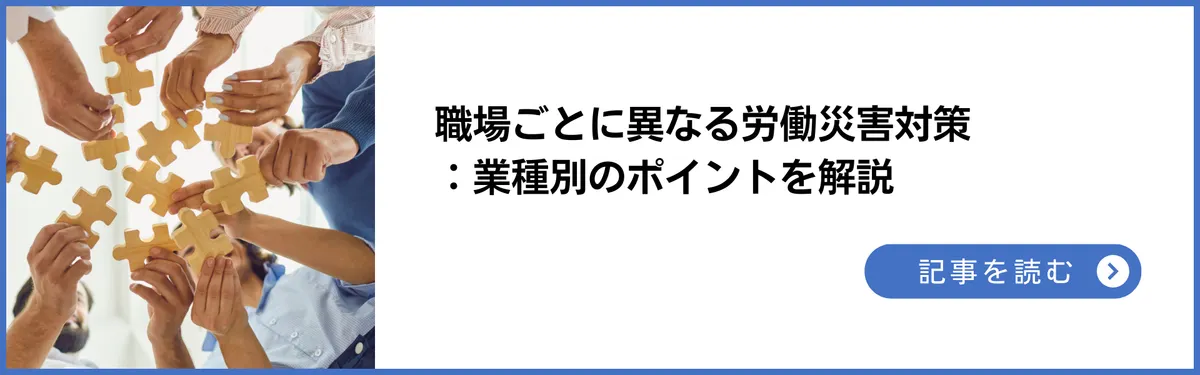
3.衛生管理者がとるべき事前対策
年末の繁忙期に伴う労災リスクを未然に防ぐために衛生管理者が担う役割として、事業主や安全管理者との連携のもと、健康・衛生面からのリスクアセスメントと職場環境の改善提案を積極的に行うことがあります。
例えば、長時間労働や過重労働が生じないようなシフト調整について事業主に提案することや、安全管理者や現場責任者に作業体制の見直しを提案し、労働者自身がこまめな休憩時間を確保することで体調管理をしやすくなるように働きかけることなどが効果的です。
また、衛生管理者自身ができることとして、朝礼や朝の点呼で、発熱・体調不良・寝不足などの健康状態を確認するなど、体調チェックの仕組みを出勤時に毎回取り入れることも効果があります。
労働者の疲労や体調変化に注視し、体調不良を早期に発見できるよう心がけると良いでしょう。
必要に応じて、次の段階として、定期的な面談やストレスチェック、産業医との連携によるフォローアップ体制の整備を行うことも考えられます。
また、作業現場の巡視を通じて、温度環境や照明、換気などの衛生状態を確認することも、衛生管理者ができる対策の一つです。
寒暖差によるヒートショックや乾燥による感染症の蔓延など、冬季特有の健康障害を防ぐことにつながります。
このようにリスクの見える化と早期対応の体制を整備することが、衛生管理者に求められる労災防止のための事前対策と役割です。
4.年末に向けた安全衛生活動の強化策
先に述べたように、年末の繁忙期は、日常業務に加えて業績や納期のプレッシャーが高まり、安全よりもスピードが優先されやすくなります。こうした環境下での労災防止には、全社的な安全衛生活動の強化が不可欠です。主に事業主や各部署のリーダー、安全管理者が主体となって全社で協力して行うことが必要です。
【全社的な意識向上の取り組み】
- 特別安全衛生教育の実施
- 繁忙期直前に事業主や安全衛生委員会の主導で行い、現場のリスク感度を高める。
- KY(危険予知)活動の強化
- 日常業務に潜む危険を洗い出し、作業前に安全策を共有する。
- 重点パトロールの実施
- 物流・製造・小売・飲食の現場では、作業手順の再確認や不安全行動の是正を目的に巡回。
【現場での安全意識の定着】
- ヒヤリ・ハット事例の共有
- 始業時や終業時に全員が集まり、その日にあった事例を話し合い、注意喚起を行う。
- 短期雇用者へのサポート体制
- フォロー担当者を明確にし、職場全体で支援する文化を作る。
【短期雇用者も含めた安全衛生教育】
労働安全衛生法では、雇用形態を問わず雇い入れ時に安全衛生教育が義務付けられています。
また、新規雇用者向け教育に既存の雇用者も参加することで、安全衛生について改めて意識を持つことができる機会となります。
- 教育内容の例
- 機械や原材料の危険性・有毒性
- 安全装置や保護具の正しい使い方
- 作業手順の遵守方法
- 疾病の原因と予防方法
- 事故発生時の応急処置
【繁忙期に特化したリスクへの対策】
- スピードより安全の優先
- 忙しさの中でも安全教育を省略せず、実務前に必ず実施する。
- 短期雇用者への特別配慮
- 経験不足によるヒューマンエラーを防ぐため、丁寧な説明と現場フォローを徹底する。
【緊急時対応の周知】
- 初動対応と報告フローの明確化
- 労災発生時に誰が、何を、どの順で行うかを全従業員に共有する。
- 視覚的掲示
- 緊急時の連絡先や対応手順を、就業期間が浅い労働者にもわかるよう職場に掲示する。
労働災害発生時に衛生管理者がとるべき対応や、労働基準監督署への報告義務、再発防止策の策定方法について知りたい方はこちらをご覧ください👇
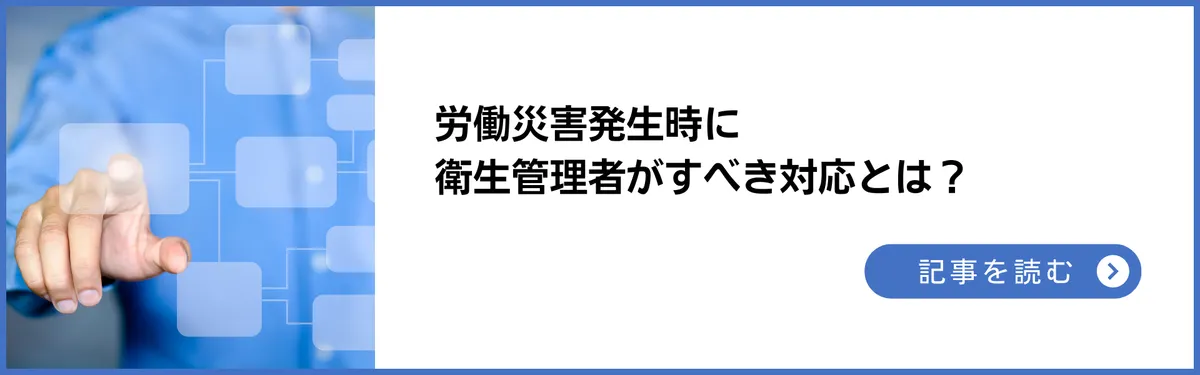
このように、忙しい時期だからこそ、安全衛生教育の徹底やリスク共有の場を確保することが、労災防止のカギとなります。
全員参加型の安全衛生活動を継続的に行い、緊急時にも迷わず動ける体制づくりを行うことが、年末に向けた安全衛生活動の強化策につながります。
5.まとめ:繁忙期こそ「健康」と「安全」の両立を
年末は、一年の締めくくりとして業務量が急増し、納期やイベント対応に追われる職場が少なくありません。しかし、どれだけ忙しくても、健康と安全を軽視すれば、過重労働による労災や体調不良によってかえって業務に支障が出る可能性があります。
繁忙期こそ、衛生管理者や管理職が率先して「無理をしない働き方」を職場全体に浸透させることが重要です。
例えば、長時間労働を抑えるシフト調整、こまめな休憩の確保、体調不良時の早期対応など、基本的な取り組みを徹底することが、事故や健康被害の防止につながります。
また、年末特有の寒さや疲労の蓄積による判断力低下にも注意が必要です。声掛けや体調確認など、小さなコミュニケーションが大きな予防策になります。
年末年始無災害運動の提唱なども活用し、業務効率の追求と並行して、従業員一人ひとりの健康を守る環境づくりを特に意識する期間としましょう。結果として、事故や離脱を防ぎ、最後まで全員で無事に一年を締めくくることができます。
年末こそ、「健康」と「安全」を両輪として走り抜けることが、企業と従業員双方にとって最大の成果となるのです。
労働災害の主な原因と衛生管理者が実施すべき基本対策について確認したい方はこちらの記事をご覧ください👇
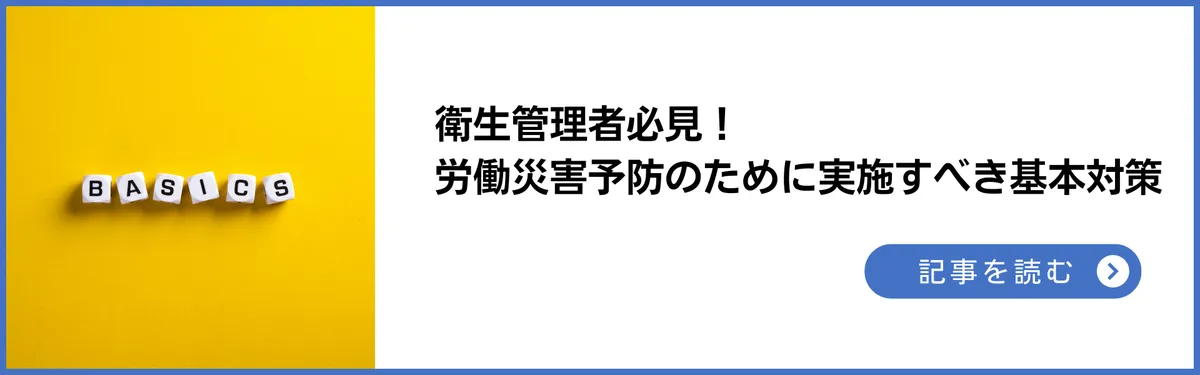
■参考
■執筆/監修
<執筆> 衛生管理者・看護師
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』




