世界メンタルヘルスデーとは、世界精神保健連盟が、1992年よりメンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と定めました。その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)とされています。世界精神保健連盟より、2024年世界メンタルヘルスデーのテーマは、「今こそ職場でメンタルヘルスを優先しよう」であることが発表されました。今回は、世界メンタルヘルスデーにちなんで、職場のメンタルヘルス対策における産業保健師の役割について考えてみたいと思います。
<目次>
1.日本の職場におけるメンタルヘルスの現状
2.世界メンタルヘルスデーをきっかけに実施したい職場の取り組み
3.産業保健師としてできるアクション
4.「こころの健康」を職場文化にする視点
5.まとめ:世界メンタルヘルスデーを形だけで終わらせない
1.日本の職場におけるメンタルヘルスの現状
精神疾患を有する患者自体は年々増加していますが、入院患者は減少し、外来患者が増加しています。外来患者の疾病分類別に見てみると、気分[感情]障害(躁うつ病を含む)や神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害といった疾病が大きく増加しています。この数十年で、精神的な疾患が徐々に社会的に認知され、受け入れられるようになったことが大きな要因と考えられます。身近な問題として捉えられるようになったことで、より早く医療機関に繋げることができ、入院レベルまで至らなくなった疾患が増えたのでしょう。精神科領域では入院患者の長期化、医療費の圧迫という問題を長年抱えているため、少しずつ解消されてきたとも考えられます。
逆に精神疾患に対する認知度が高まり、心療内科や精神科への受診の敷居が下がったことで、精神障害の労災請求件数、支給決定件数は年々増加していると考えられます。それだけ職場においてメンタルヘルスとは身近なものとなり、対策を講じなければならない問題ともなってきました。
2.世界メンタルヘルスデーをきっかけに実施したい職場の取り組み
さて、みなさんは「スティグマ」という言葉をご存知でしょうか。日本語の「差別」や「偏見」などに対応しています。具体的には、「精神疾患など個人の持つ特徴に対して、周囲から否定的な意味づけをされ、不当な扱いことをうけること」です。スティグマには、精神疾患を持つ人が自分自身に対して抱くものも含まれます。例えば就職活動をする場面を例にとって考えてみると、「ハローワークに相談に行っても精神疾患が原因で嫌な思いをするのではないか」と不安になったり、就職活動に難航することで「自分には就職する価値がない」と思い込んでいたりすることを指します。精神障害に対するスティグマを軽減するための対策として、精神疾患を持つ人も含めたメンタルヘルスリテラシー(精神的健康を維持し、精神疾患を予防・早期発見するために必要な知識やスキル)の向上を図る取り組みが必要とされています。
そのようなスティグマを軽減させるための先駆的な良好事例として、ある会社の取組がご紹介されていました。その会社の大半が障がい者です。新卒・中途採用の条件として、障がい者手帳を所持していることが示されていました。その会社で「あなたが働く上で大切にしていることは何ですか?」と従業員同士で話し合いの場を設けたことが注目されました。この話し合いを通じて「従業員同士で語り合うことが誇りと自信をもって向上していける土壌となる」ことを目的としています。一方的な啓発にとどまらず、定期的に対話を重ねる仕組みとして「みんなで話す・みんなで聴く・否定しない会」をモットーとして相互理解や心理的安全性の醸成を深めていくことができました。この取組は障害を抱える労働者の相互理解を深める「支援」としてだけでなく、企業活動を効果的に推進するための戦略として導入したことで注目されました。この取り組みは障害者が多く働く職場での取り組みであり、すべての職場にそのまま当てはまるものではない点はご留意ください。その他、メンタルヘルスに関する情報提供、管理職向けの研修、一般職向けの研修、職場復帰支援制度の整備、相談体制の整備、ストレスチェックの活用など、企業価値を高める活動をメンタルヘルスデーに合わせて実施するのも良いでしょう。
メンタルヘルス関連のおすすめコンテンツを知りたい方はこちらをご覧ください👇
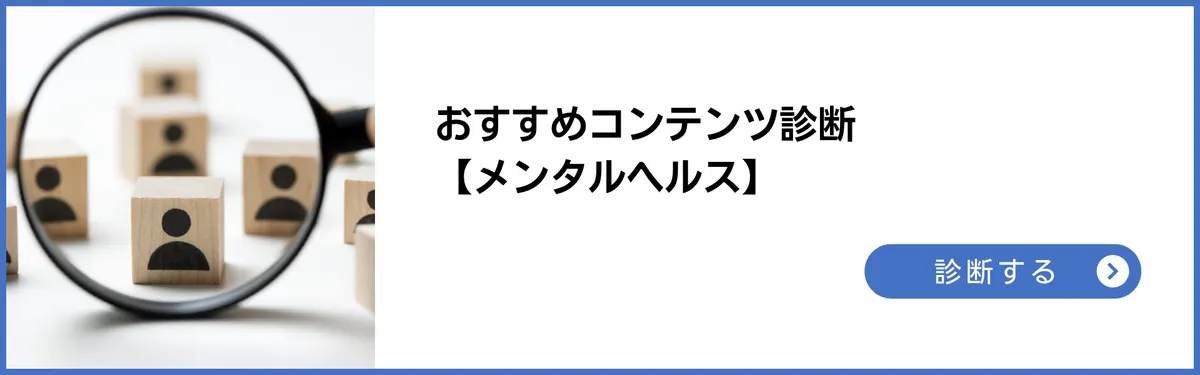
3.産業保健師としてできるアクション
2022年度から始まる高等学校学習指導要領で、精神疾患に関する内容を扱うことになりました。つまり、これからの新卒社会人は精神疾患に関するスティグマの軽減に役立つことが期待されています。精神疾患について学ぶことで、自分や友人、家族等が精神的な不調を抱えたとしても、そのことが特別なことではないと理解でき、適切な対処ができるようになるでしょう。また、身近な人が精神的な不調を抱えた場合にも、寄り添い話を聴くことができる、孤立を防ぐことにつながるかもしれません。
一方で、現在の管理職世代には、スティグマに対する理解が十分とはいえない場合も少なくありません。たとえば、部下が精神疾患を抱えていると知ったときに、「精神的な不調は本人の弱さに起因するもの」といった誤った認識を持っていたり、精神疾患に対して漠然とした不安や恐怖を感じているケースもあります。過去に、精神疾患を抱える部下の対応に苦労した経験があると、「また同じようなことが起きるのでは」といった心理的な抵抗感を抱くのも無理はありません。
職場には、年齢・性別・文化・働き方・ライフステージなど、実にさまざまな価値観や背景を持つ従業員が共に働いています。そのため、メンタルヘルスの課題や悩みの受け止め方、精神疾患に対する考え方も人それぞれです。産業保健師が、従業員のこうした多様性を理解し、一人ひとりの状況に寄り添った支援を行うことは、メンタルヘルスリテラシーの向上にもつながります。また、支援する側である産業保健師自身も、知らず知らずのうちにスティグマを持っていないかを見直し、常に自らの姿勢を問い直すことが求められます。
4.「こころの健康」を職場文化にする視点
こころの健康に限らず、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」に関心を寄せる事業所は年々増加しています。今後ますます少子高齢化社会が進み、日本の総人口は減少、特に2050年には生産年齢人口は30%以上減少すると予想されている中、多くの事業所が人手不足という問題に直面します。人手不足は企業経営に深刻なダメージを与えており、どの事業所においても人材の定着は大きな課題です。逆に、求職者が働く職場に望むものは、心身の健康を保ちながら働けることであり、多様な価値観を持つ働く世代において健康経営が重要な鍵となっています。
もちろん、企業にとって利益を上げることは重要ですが、同じくらい、あるいはそれ以上に「人材を大切にする視点」を持った経営戦略も欠かせません。その実現には、経営トップの理解とコミットメントが不可欠です。産業保健師が経営戦略に直接関わることはできませんが、経営層・管理職層・一般の従業員など、あらゆる層に向けて、地道に情報を発信し続けることが大切だと思います。
5.まとめ:世界メンタルヘルスデーを形だけで終わらせない
まだまだメンタルヘルスに対するスティグマの課題は多く残っています。メンタルヘルスへの理解を促す取り組みは徐々に広がりつつありますが、依然として職場や社会全体で十分に浸透しているとは言い難いのが現状です。そのような中、産業保健師として事業所内に「世界メンタルヘルスデー」を紹介するだけでも価値はあるように思います。この時期に合わせて、各行政も街頭キャンペーンや公共施設をグリーンやシルバーにライトアップさせています。仕事帰りの従業員の人々に「今日はシルバーにライトアップされている」「そういえば会社でメンタルヘルスデーとか言っていたな・・・」と思ってもらえれば、それだけで成功ではないでしょうか。産業保健師として、少しずつでも認識してもらえるよう地道に発信し続けましょう。
その他の○○デー/週間/月間について知りたい方はこちらをご覧ください👇
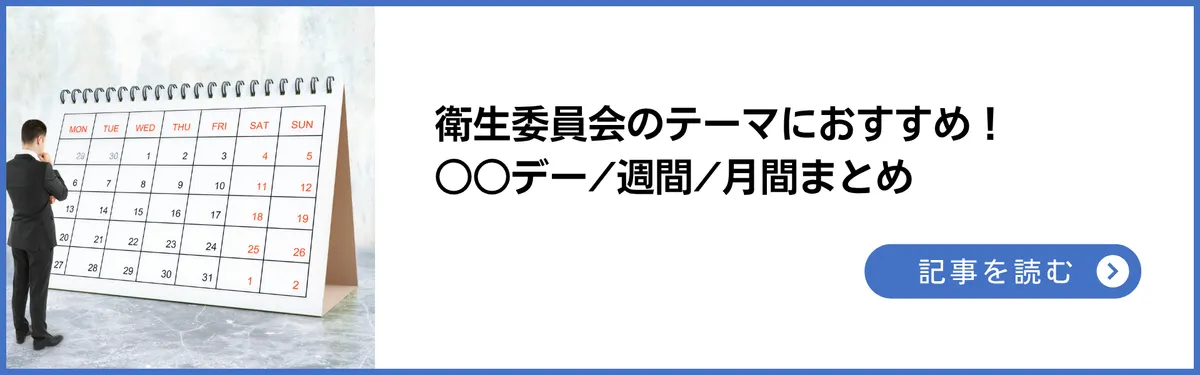
■参考
1)世界メンタルヘルスデー|厚生労働省
2)精神保健医療福祉の現状等について|厚生労働省
3)精神障害の労災認定|厚生労働省
4)スティグマについて|国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部
5)スティグマ軽減とメンタルヘルスリテラシー向上による健やかな職場作り|産業精神保健 33(1): 39–41, 2025
6)健康経営|経済産業省
■執筆/監修
<執筆>
阿部 春香(保健師、産業カウンセラー、第一種衛生管理者)
日本産業衛生学会、日本産業保健師会に所属する。2024年に日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度登録者として登録する。
広島大学大学院(博士課程前期)を修了後、健診施設に勤務する。現在、中小企業の保健師として勤務し、健康経営の推進を行っている。
働く全ての人に産業保健を届けたいという思いから、産業保健職として産業保健の社会的認知を広げるための活動も行っている。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』




