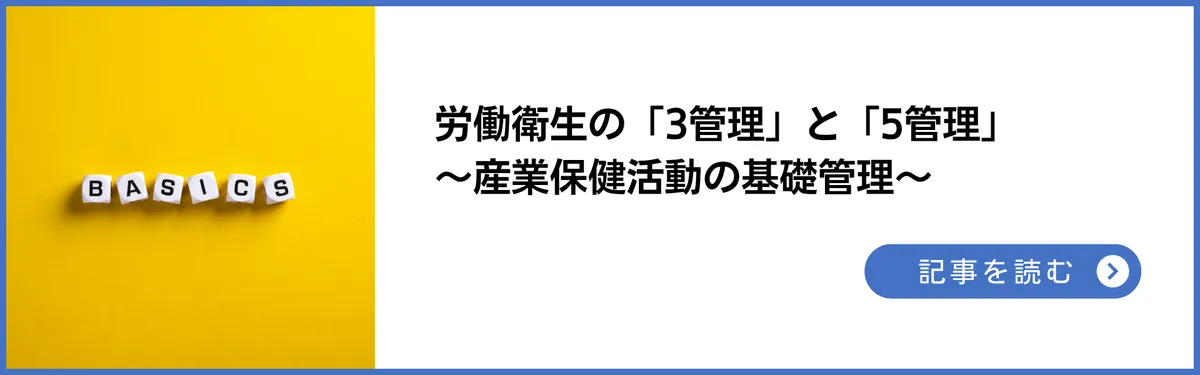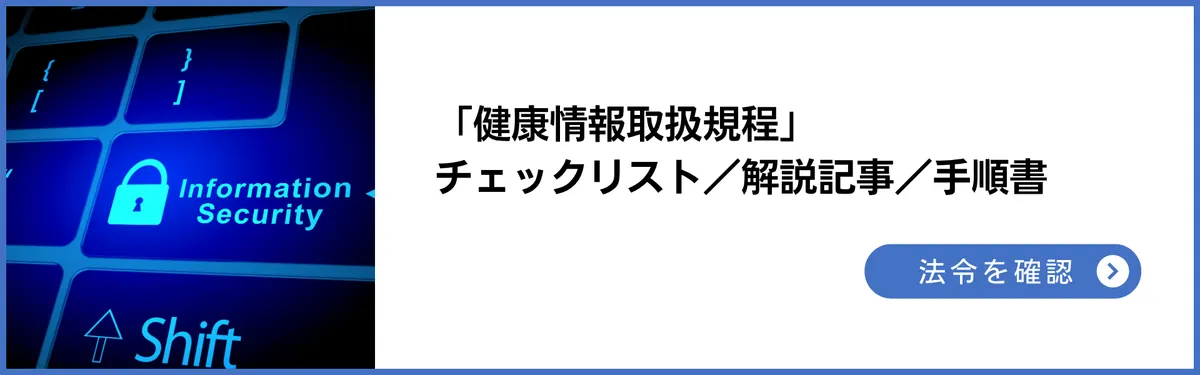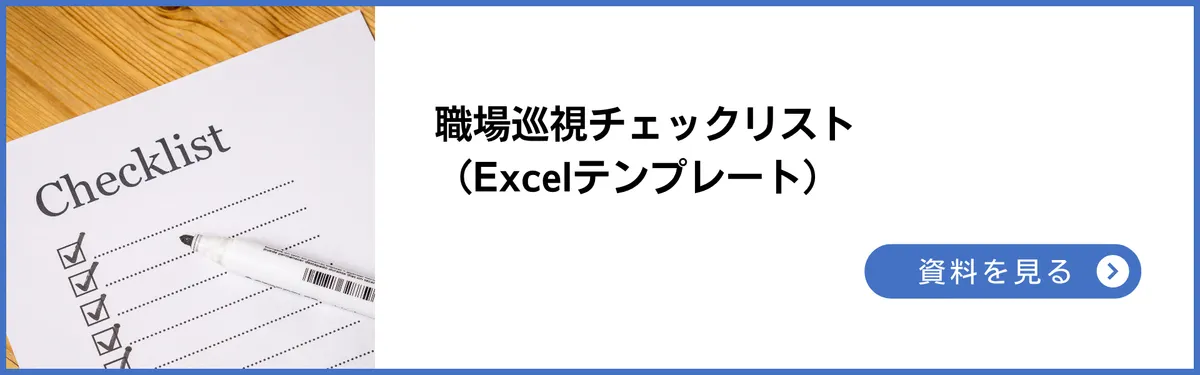【全国労働衛生週間】産業保健師が押さえておきたい重点ポイントとは?
全国労働衛生週間は、働く人の健康の確保・増進を図り、快適に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。例年10月1日から10月7日までとされ、実効を上げるため9月1日から9月30日までを準備期間としています。
近年、労働者の健康をめぐる状況については、高齢化の進行により、一般健康診断の有所見率が上昇を続けているほか、何らかの疾病を抱えながら働いている労働者が増加するとともに、女性の就業率が上昇し、働く女性の健康問題への対応も課題となっています。今回、労働者が安心、安全に働けるために産業保健師の押さえておきたいポイントについてご紹介させていただきます。
<目次>
1.全国労働衛生週間とは?
2.労働衛生週間で見直したい3つの視点
3.産業保健師ができる具体的な取り組み例
4.労働衛生週間をきっかけに、社内で取り組みを強化した事例
5.働く人の声を拾い上げる好機に
6.労働衛生週間を「形式」で終わらせない
1.全国労働衛生週間とは?
さて、全国労働衛生週間と聞くと、全国安全週間と似ているため、どのように違うのか気になる方も多いのではないでしょうか。全国労働衛生週間と全国安全週間との違いを確認しておきましょう。
大きくは、活動の目的が異なります。全国安全週間が「労働災害防止」に主眼が置かれているのに対し、全国労働衛生週間は「労働衛生意識と管理の向上」に主眼が置かれている点が大きな違いです。「労働安全(安全)」と「労働衛生(衛生)」と覚えてください。「労働安全」は職場における事故や怪我、災害を防ぐための対策や管理を指して使われる言葉です。主な取り組みとして、安全パトロールやヒヤリハット報告、KY活動などの活動が挙げられます。一方で「労働衛生」とは労働者の健康と安全の確保に関する研究および実践活動を指します。
実施期間も異なります。労働衛生週間は先述した通り秋に開催していますが、労働安全週間は例年7月1日から7月7日まで(準備期間:6月1日から6月30日)です。
2.労働衛生週間で見直したい3つの視点
労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理、健康管理のことを指し、これは労働安全衛生法に基づく基本的な枠組みです。
◆作業環境管理
作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理することを指します。作業環境中の有害因子の状態を把握するためには、作業環境測定が行われます。3管理の中で最も基本となる対策です。
◆作業管理
環境を汚染させないような作業方法や、有害要因のばく露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて、それが適切に実施させるように管理することを指します。改善が行われるまでの間の一時的な措置として保護具を使用させることなどもこれに含まれます。作業の内容や進め方を適切に管理することで、労働者の健康障害を防止します。
◆健康管理
労働者の健康状態を健康診断により直接チェックし、健康の異常を早期に発見したり、その進行を防止したり、さらには、元の健康状態に回復するための医学的及び労務管理的な措置をすることを指します。
この3管理に労働衛生教育(健康教育)と総括管理(統括管理)を加えて『5管理』と呼ばれることもあります。
労働衛生の3管理(5管理)についてもっと詳しく知りたい方はこちら👇
3.産業保健師ができる具体的な取り組み例
企業の社会的責任への関心が高まる中、従業員の健康保持・増進は、従業員を守るだけでなく、企業にとって経営リスクを低減する重要な取り組みです 。見えないリスクを可視化し予防する専門家として、産業保健師の役割が期待されています。
まず、労働安全衛生法に定められているものとしては、健康診断とストレスチェックがあげられます。産業保健師は健康診断やストレスチェックの実務、あるいはその実務を支援する役割を担います。また、その結果に基づく措置(事後措置)として、健康の保持増進のための就業上の措置や、保健指導の実施などが求められます 。
産業保健師には、健康情報を適切に取り扱う役割が求められています。健康情報は要配慮個人情報であり、社内の管理規程に基づいて安全に管理する必要があります。また、従業員の健康管理を適切に行うためには、産業医、衛生管理者、人事労務担当者、上司などと連携し、必要な範囲での情報共有を行うことも重要です。
健康情報取扱規程について法令をもとに自社の状態をチェックしたい方はこちら👇
4.労働衛生週間をきっかけに、社内で取り組みを強化した事例
労働衛生週間を機に、日頃の職場の取り組みを見直し、改善を図ることができます。たとえば 、労働衛生週間に限らずですが、産業保健師としてふだんから取り組むべきこととして、職場巡視があげられます。職場巡視の主な目的として、作業環境を実際に見て、安全衛生上の問題点を見出し改善していきます。産業医の基本的業務として月1回の職場巡視が労働安全衛生法、および労働安全衛生規則に規定されています。また同様に、衛生管理者には週1回の職場巡視も規定されています。
ある事業所では、労働衛生週間に総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、産業保健師を一同に介して職場巡視を実施しました。全工場を巡視するので1日がかりで、巡視メンバーの日程調整も困難でした。そこで特に心がけられていたことは、従業員や産業医と積極的にコミュニケーションをとることでした。従業員の中で治療と仕事の両立支援を実施している者については、健康上の理由で就業制限がある社員や、継続的な支援を行なっている社員の職場については、周囲の環境や勤務状況などをさりげなく確認するようにしていました 。産業医からも「無理なく働けていますか?」とお声がけしていただき、産業医と従業員のコミュニケーションをとるきっかけの場にしていました。普段から従業員から健康についての相談があった際、その内容について産業医に共有していましたし、従業員にも「産業医に情報共有させていただきます」と同意も得ていました。産業医も従業員もなんとなくは双方の存在を認識していたとは思いますが、実際にどんな人なのかまでは把握できていなかったと思います。巡視の機会を通して、産業医と従業員のコミュニケーションをとることができる場にしていました。
職場巡視チェックリストのExcelテンプレートを無料で提供しています👇
5.働く人の声を拾い上げる好機に
「働く人の一番身近な相談者」として安心感を提供することは、産業保健師のもつ重要な役割の一つです。そのためには、困った時に顔が浮かぶ存在となるように関係づくりができていることが求められます。誰しも病気や体調不良に陥った場合、話を聴いてもらいたいという心理に陥ります。社内で話を聴いてもらえる専門家がいるというのは心強いことです。産業保健師は、従業員から気軽に相談にのってもらえるような存在であるべきだと考えています。安全に働くためには、怪我をしたり健康を損ねたりする状態を脱し、安心感を持っていきたいものです。
6.労働衛生週間を「形式」で終わらせない
労働衛生週間に事業所内で労働衛⽣旗の掲揚、労働衛生に関する様々なポスターを掲示していることでしょう。その期間内に労働衛⽣に関する優良職場、功績者などの表彰を行っている事業所もあります。そういった形式的な対策ももちろん大切ですが、何のためにそういった週間を定めているのかを忘れてはなりません。誰もが安⼼して安全に、そして健康に働ける職場づくりを目指していきましょう。
■参考
1)キャンペーン・運動・標語|JISHA中災防 中央労働災害防止協会
2)労働衛生のしおり 令和6年度, 第1章 労働衛生管理の基本 1基本的対策
3)労働衛生対策の基本 ④ 職場巡視のポイント|産業保健21, 2015.4, 第80号
■執筆/監修
<執筆>
阿部 春香(保健師、産業カウンセラー、第一種衛生管理者)
日本産業衛生学会、日本産業保健師会に所属する。2024年に日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度登録者として登録する。
広島大学大学院(博士課程前期)を修了後、健診施設に勤務する。現在、中小企業の保健師として勤務し、健康経営の推進を行っている。
働く全ての人に産業保健を届けたいという思いから、産業保健職として産業保健の社会的認知を広げるための活動も行っている。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』