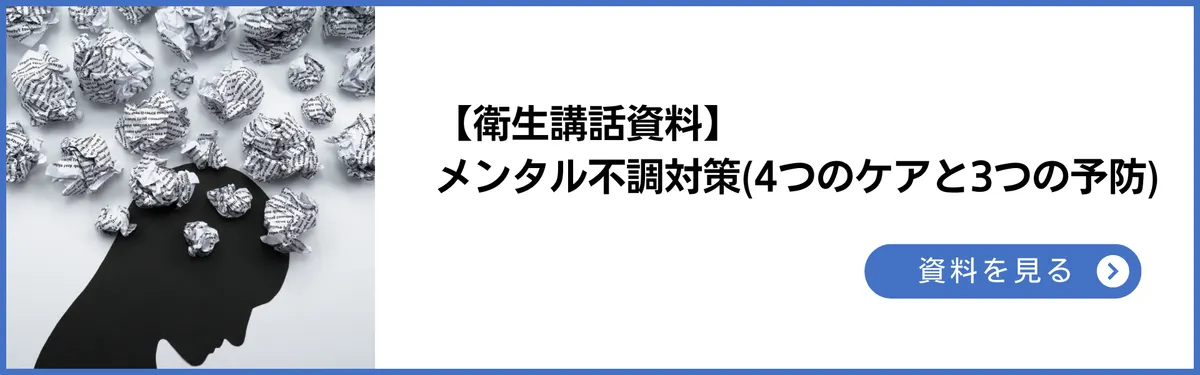特別大変なことをしていなくても、日々生活していると、知らず知らずのうちにストレスが溜まる場合がありますよね。しかし、無自覚なストレスが溜まり過ぎると、心身の不調に繋がり、回復が遅くなってしまう危険性があるため、注意が必要です。
この記事では、無自覚なストレスの原因やストレスによって身体に表れるサイン、放置することで考えられるリスクなどを解説していきます。
<目次>
1.無自覚なストレスとは
2.私たちがストレスに気づきにくい理由
3.隠れストレスのサイン
4.無自覚なストレスを放置することで考えられるリスク
5.従業員の無自覚なストレスを防ぐために事業所ができる3つのこと
6.まとめ
1.無自覚なストレスとは
無自覚なストレスとは、その名前の通りストレスがかかっていることや溜まり過ぎている状態にもかかわらず、本人に自覚がない状態を指します。
そのため、心身の不調が自覚できるほどの強さで現れるまで気づかないので、不調を感じたときには精神的にも身体的にも、大きなダメージを受けてしまっているケースが多いでしょう。
2.私たちがストレスに気づきにくい理由
現代社会に生きている私たちは、さまざまな理由から自分のストレスに気づきにくくなっています。主な理由は次の3つです。
①ストレスが「あるのが普通」になっている
②自分のサインに気づく余裕がない
③無意識のストレス回避や発散行動
ひとつずつ、見ていきましょう。
①ストレスが「あるのが普通」になっている
現代社会では、忙しさやプレッシャー、人間関係のストレスなどが日常的に存在します。そのため、多少の不調や疲れを「いつものこと」、「こんなもんだろう」と見過ごしやすくなっています。ストレスが「特別な状態」ではなく「日常の一部」になっていることが、気づきにくさの一因です。
②自分のサインに気づく余裕がない
常に仕事などに追われていると、その状態が「普通」になり、自分の心や体の変化に目を向ける時間が少なくなります。また、長期間ストレスにさらされると、それが当たり前になり、ストレスを感じる感覚そのものが鈍くなることもあります。「頭痛・胃痛・肩こり・眠れない・集中できない」といった体のサインも、ストレスではなく「単なる体調不良」や「年齢のせい」と片付けてしまうケースもあります。
③無意識のストレス回避や発散行動
過剰な飲酒、やけ食い、衝動買い、ゲームやSNSのやりすぎなど、ストレスから一時的に気を逸らす行動は、知らず知らずのうちに私たちの習慣になっています。こうした行動によって「なんとなくスッキリした」ように感じても、根本的なストレスが解決されているわけではありません。
3.隠れストレスのサイン
では次に、隠れストレスのサインを紹介していきましょう。無自覚なストレスが溜まると、身体的や精神的、行動面に関して分かりやすいサインが表れるようになります。
◆身体に表れるサイン
身体に表れるサインとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 頭痛
- めまい
- 肩こり
- 耳鳴り
- 全身のだるさ、倦怠感
- 下痢または便秘
- 胃痛や腹痛
- 食欲不振または食欲増進
- 動悸や息切れ
- 不眠状態
- 風邪などをひきやすくなる
上記のサインは、一見すると日常の中でよく表れる症状でもあるので、ストレスが原因とは気づかずに放置してしまうケースも多いかもしれません。しかし、このようなサインは身体からのストレスのSOSなので、放置するとホルモンバランスが乱れ、免疫力や抵抗力なども低下し他の疾患にかかりやすくなるので、注意が必要です。
◆精神面に表れるサイン
精神面に表れるサインとしては、以下のようなものがあります。
- 気分が落ち込みやる気が起きない
- 以前は楽しいと感じていたことが楽しいと感じられない
- 仕事に集中できなくなる
- ミスが多くなり自分を責める
- イライラしやすい
- 不安や緊張感が強くなる
無自覚なストレスが溜まってくると、自律神経の働きが乱れ、緊張状態がつづくようになります。その状態が長期化すると、しっかり睡眠をとれなくなりやすく、交感神経と副交感神経のバランスも乱れ、イライラしやすくなったり集中力が保てずにミスが増え、自分を責めたりするような精神状態になりやすいのです。
◆行動に表れるサイン
行動に表れるサインとしては、以下のようなものが挙げられます。
- ミスが増える
- 遅刻が増える
- 身だしなみや清潔感を気にしなくなる
- 飲み会や集まりの場に参加しなくなる
- アルコールの摂取量が増える
- たばこの本数が増える
- 突然涙が出てくるようになる
無自覚なストレスが溜まると、身体の中のさまざまな機能が正常に働かなくなります。そのため、今まで普通に出来ていたことが思うように出来なくなるケースが多いです。また、お風呂に入るのが億劫になって、清潔感を保てなくなる人もいます。
4.無自覚なストレスを放置することで考えられるリスク
先ほども、無自覚なストレスが身体的・精神的・行動に多大な影響を与えることをお伝えしました。しかし、このような状態になってもなお、忙しさを理由に放置してしまう人もいます。そうなると、身体や精神面の限界を超え、より深刻な病気の発症に繋がる危険性があるので注意が必要です。
具体的には、うつ病や適応障害などを発症してしまったり、アルコールやたばこの量が増え、依存症を発症したりするリスクがあるのです。ここまで来ると、回復までに長い期間を必要とするようになってしまうため、休職や退職を検討しなければならなくなります。
無自覚なストレスを放置すると、大きなリスクがあることを覚えておかなければなりません。
5.従業員の無自覚なストレスを防ぐために事業所ができる3つのこと
最後に、従業員の無自覚なストレスを防ぐために事業所ができることを紹介していきます。事業所は、従業員と一緒に対策を考える必要があるのです。
◆Ⅰ. 定期的に従業員のストレスチェックを実施する
従業員が無自覚なストレスを溜め込んでいても、自分自身で気づくのは至難の業です。そのため、ストレスチェックテストなどを活用して、定期的に従業員全体のストレスチェックを行う場を設けるようにしましょう。
そうすれば、従業員自身も自分のストレス状態を把握して、ストレス度が低い状態ならば自分で対処法を取り入れることもできます。
◆Ⅱ. 1on1ミーティングによる従業員の異変の早期発見
ストレスフルな状態で働いている環境では、なかなか弱音などを同僚や上司などに相談する機会がなく、従業員の無自覚なストレスはさらに溜まってしまう危険性があります。
そのため、定期的に部下が上司に悩みを相談しやすい場を設けることで、上司にとっては部下の無自覚なストレスを早期に発見できる機会が増えますし、部下にとってもストレスを溜め込まずに適度に吐き出すことで、働きやすい状態の維持ができます
◆Ⅲ. 必要な場合は休職や専門機関へ繋げるサポートを行う
定期的なストレスチェックや1on1ミーティングなどによって、従業員の無自覚なストレスを発見し、そのストレス度合いが高い場合は、必要に応じて休職制度の説明や産業医・医療機関に在籍する専門家への相談を促すなどのサポートを行うことをおすすめします。
ストレスによる心身の不調は、放置すればするほど悪化する可能性が高くなります。無自覚なストレスによって、従業員が退職しなければならない状態になる前に、必要な制度や支援の説明をすることが大切です。
6.まとめ
普通に生活していても多少のストレスは存在するものですが、ストレスに気づかないまま放置してしまうと、ある日突然身体面や精神面などへの影響が表面化します。悪化すると休職や退職を余儀なくされる従業員もいるので、注意しなければなりません。無自覚なストレスによる従業員の心身の不調を防ぐためには、定期的なストレスチェックや上司に相談しやすい環境を整えることが大切になります。
やりっぱなしで終わらせない、ストレスチェックから始める組織改善サービスはこちら👇
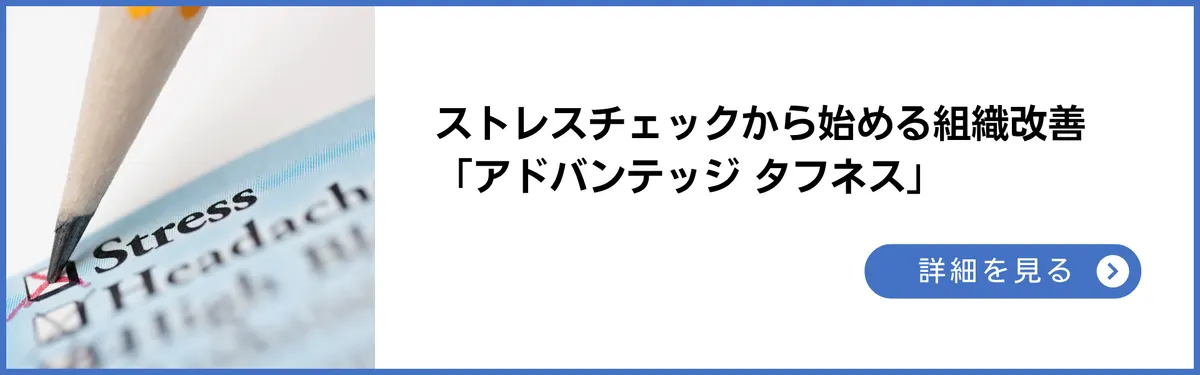
■執筆/監修
<執筆>
久木田 みすづ (精神保健福祉士、社会福祉士、心理カウンセラー)
福祉系大学卒業後、カウンセリングセンターの勤務を経て、心療内科クリニック・精神科病院で精神保健福祉士・カウンセラーとして従事。うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんと家族に対する相談や支援に力を入れる。
現在は、主にメンタルヘルスの記事を執筆するライターとして活動中。
<監修>
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』