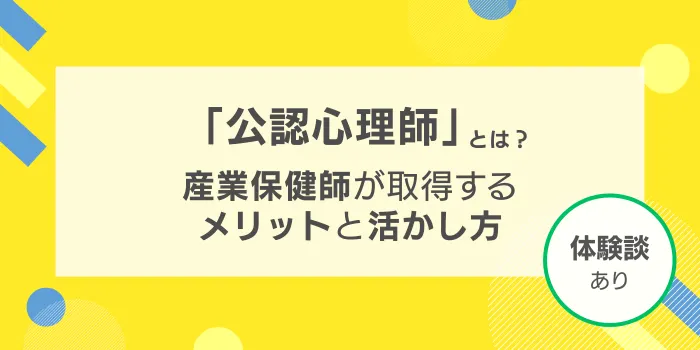
産業保健師がキャリアアップのために取得する資格のひとつとして人気なのが公認心理師です。一方で、資格取得は一歩を踏み出すハードルが高く、なかなか挑戦できずにいる人も多いのではないでしょうか。
本記事では、産業保健師が公認心理師を取得するメリットやキャリアへの活かし方について体験談を交えご紹介します。
<目次>
1.公認心理師とは?
2.公認心理師と臨床心理士の違い
3.公認心理師になるには
4.産業保健師が公認心理師を取得するメリット
5.体験談:産業保健職が語る「資格取得のリアル」
6.まとめ
1.公認心理師とは?
公認心理師とは、2017年に施行された「公認心理師法」に基づく、心理職における日本初の国家資格です。保健医療・福祉・教育やその他の分野において心理学に関する専門知識および技術をもって様々な支援を行います。
公認心理師が行う業務について、公認心理師法により次のように定められています。
| 1.心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 2.心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 3.心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 |
さんぽLABが2025年に産業保健職を対象に実施したアンケートでは、産業保健職(全職種)が持っている資格の第3位、今後取りたい資格の第5位に挙げられており、産業保健の現場でも非常に興味関心が高い資格であることが伺えます。
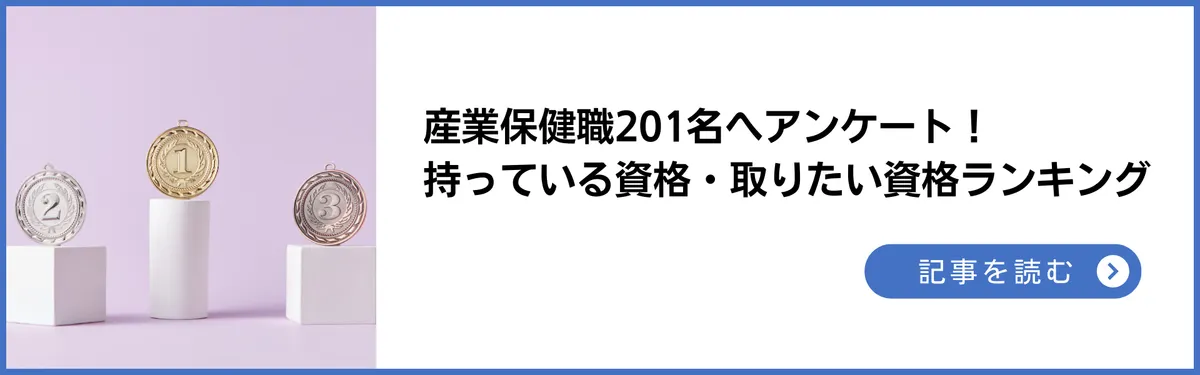
2.公認心理師と臨床心理士の違い
心理職の資格としてよく知られているのが、臨床心理士です。業務内容に大きな違いはありませんが、資格の種類や更新の有無などに違いがあります。
| 公認心理師 | 臨床心理士 | |
|---|---|---|
| 歴史 | 2017年に法制化 | 1988年に資格認定が開始 |
| 資格の種類 | 国家資格 | 民間資格 |
| 資格更新 | 一度取得すれば更新は不要 | 5年毎に更新が必要 |
| 業務 | 法律(公認心理師法第二条)に、対象者の心理状態の 観察・分析、対象者やその 関係者に対する相談・助言・指導、教育・情報提供 等に ついて規定されている |
臨床心理査定、臨床心理面談、臨床心理学的地域支援、上記の調査研究など、 臨床心理学に基づく知識や 技術を用いて、心の問題に アプローチし解決を目指す |
| 取得条件 | 大学で指定科目終了後、 大学院または実務経験など |
指定大学院または専門職大学院修了、医師免許保持者で心理臨床経験を2年以上有する者など※ |
※詳細は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会ホームページを参照
3.公認心理師になるには
公認心理師になるには、公認心理師試験(国家試験)に合格し、登録簿に登録されることで「公認心理師」としての名称を用いることができます。
公認心理師試験の受験資格
試験を受験するためには、次の条件が必要です。
| ① 大学において指定の科目を履修し、かつ、大学院において指定の科目を履修し終了する ② 大学において指定の科目を履修し、卒業後一定期間の実務経験を積む ③ ①及び②と同等以上の知識及び技能を認められる |
公認心理師試験
公認心理師の試験は1年に1回実施され、試験は、一般財団法人公認心理師試験研修センターが管轄しています。
4.産業保健師が公認心理師を取得するメリット
産業保健では、職場のメンタルヘルス対策が強く求められる業務と言えます。その上で、産業保健師が公認心理師の資格をとると以下のようなメリットが期待されます。
① メンタルヘルス支援における専門性が高まる
公認心理師は、大学および大学院または一定期間の実務経験が必要です。公認心理師の資格を取得することで心理学に基づく面談や支援スキルを体系的に学ぶことができるのでメンタル不調者への対応や職場の支援体制の構築など幅広く関わることができます。
② 信頼性が高まる
公認心理師は国家資格であるため、企業・管理職・産業医などから信頼が高まり、「メンタルヘルスの専門家」として立場をより明確にすることができます。
③ キャリアの幅が広がる
産業保健師としての面談スキルに加えて、カウンセリングの専門的な知識や技術を身につけることができます。メンタルヘルスの専門家を求める企業は多く、公認心理師の資格を持つことで、キャリアアップや転職の選択肢がさらに広がります。
5.体験談:産業保健職が語る「資格取得のリアル」
実際に公認心理師を取得した産業保健専門職へ資格取得のリアルを伺いましたので共有いたします。
※一部抜粋・修正をしております。
Q1.なぜその資格を取ったのですか?
● 看護師資格では一般疾患についての知識はあるが精神疾患についての知識やカウンセリング技術に乏しかったため。
● 休職者の相談を受けたり、所属の上司へのアドバイス、復職に向けた調整、従業員への教育等、メンタルに関連した業務を担う中で、より質を上げ、説得力を持って対応できるには、資格取得が必要と考えました。
● 知り合いの保健師さんに勧められて。
● 産業カウンセラーの資格の更新のための受講更新などが大変だったこともあり、更新が不要な国家資格の方に絞りました。
● 実務経験のみで受験可能だった、他の保健師と差をつけたかった。
● メンタルケアの仕事を保健師として、すでに行っていましたが、より一般職の方達に私たちの仕事を理解してほしいと思い取得しました。
Q2.資格を取得して、実際の仕事やキャリアにどのように役立っていますか?
● メンタル不調者の相談、カウンセリングなどで役立っています。
● 資格取得で終わりではなく、関連学会への出席や研修会の受講など継続的に学び続けています。必要な知識を持って、的確な判断ができるよう、今後も継続していきたいです。資格を持っているということで、社内でも信頼してもらえているように感じます。
● 公認心理師を中心として従事しているわけではないため、資格取得しても大きな違いがあるわけではないです。一方で、メンタルヘルスに関する知識や対応などもできると、会社などに説明(証明)しやすい。経験も含め、資格を取得しただけに終わらせないようにしています。
● 心理のセミナーなど会社でやらせてもらった。
● 変わっていません。
Q3.今後のキャリアにどう役立つと考えていますか?
● 心理職は医療や教育現場などで活躍の場が多く、産業保健スタッフとしての心理職が少ないため他企業や大学の講師などで声を掛けていただくことがあるので活躍の場を広げたい。
● より専門性は高めていきたいです。
● 公認心理師と共に、産業医カウンセラー、キャリアコンサルタント資格も有していますが、キャリアコンサルタント技能士の取得も考えたいです。また、各資格を生かし、起業することも将来の夢として持っています。
● 産業保健分野としても、フィジカル、メンタル面にかかわらず対応していますが…今後、メンタルヘルス対応の割合が多いので、専門性を高めていきたいと思います。
● 活かし方が分からない。実際に心理職の経験がないため。
6.まとめ
公認心理師を取得することで、産業保健師として休職者対応や従業員の相談などの実務で力を発揮できるほか、社内外での信頼性向上や活躍の場拡大にもつながります。
一方、公認心理師は国家資格であり、取得には大学での指定科目の履修や大学院での学び、または実務経験など、一定の努力と時間が必要です。資格は一度取得すれば更新は不要ですが、支援の質を維持・向上させるには、自ら学会や研修に参加し、知識や技能を磨き続けることが重要です。
資格取得を通じて経験と学びを重ねれば、産業保健師としての専門性や活躍の可能性はさらに広がり、多様なキャリアチャンスを切り拓くことができるでしょう。
<参考>
・公認心理師 |厚生労働省
・公認心理師とは|一般社団法人東京公認心理師協会公式サイト
・臨床心理士とは|一般社団法人東京公認心理師協会公式サイト
・受験資格 | 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会





