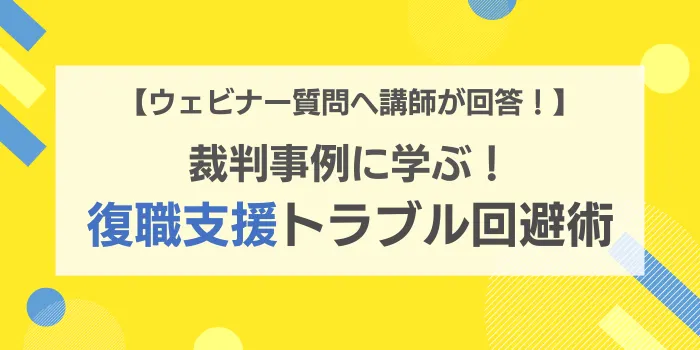
復職支援の対応に、不安や迷いを感じたことはありませんか? 「この判断で本当に大丈夫だったのか…」「あとからトラブルにならないか…」そんな不安を抱える産業保健職の方は少なくありません。
6月26日に実施したウェビナーでは、休職・復職制度の基本から実際の裁判事例に基づくリスク回避の視点まで、講師である佐々木規夫先生に幅広く解説いただきました。
ウェビナー内でお答えしきれない回答について、講師の佐々木規夫先生にご回答いただきましたので本記事にて紹介させていただきます。
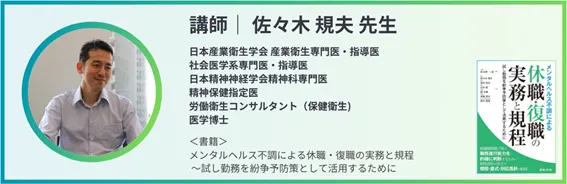
本記事に掲載する回答は、セミナーにご登壇いただいた佐々木先生より、豊富なご経験に基づいていただいたご意見です。法律の専門的な見解を示すものではございませんので、あくまで一般的な参考情報としてご理解くださいますようお願い申し上げます。
目次
1.復職準備・試し出勤・模擬出社・通勤訓練
2.配置転換・職場復帰先の検討
3.軽減勤務・復職条件・恒常化リスク
4.就業規則・制度の整備と運用
5.主治医との連携方法
6.企業への働きかけ
7.支援の頻度・支援者側の負担・コミュニケーション
8.障害者雇用・合理的配慮
9.その他
1 復職準備・試し出勤・模擬出社・通勤訓練
質問①
主治医から復職可の診断書が出たのちに、模擬出社をする場合、診断書の日にち以降は、傷病手当金申請の書類を病院が記載してもらえず、会社としては、復職前の状況なので、給与や通勤手当は出ないという中で、模擬出社を行うのは就業規則に明記されていれば可能なのでしょうか。
■回答
主治医から復職可の診断書が出た後のご質問ですね。重要なのは、模擬出社(業務命令無し、無給)なのか、試し勤務(業務命令あり、有給)なのかだと思います。
復職前の模擬出社は労務提供が可能な状態ではない時点で行われるため、業務を行わない限り事業者は賃金を支払う義務がありません。ただ一般的に明確な目安があるわけではないですが、企業側の指揮命令下において業務をさせる場合は、給与支払いの義務が生じます。
傷病手当金は、無給で行う模擬出社の場合であれば、主治医が書類を書いていただけるのであれば、健保組合から支給されると思います。主治医等には「あくまでリハビリ的な勤務をしているにすぎず、未だ本格的な復職している状況ではない」旨の連絡をして傷病手当の記載に協力してもらう依頼をしておくのであれば尚よいでしょう。一方で、試し勤務中に業務を行い給与が発生すると、傷病手当金が支払われないのが通常であると思います。
模擬出社や試し勤務などの給与・通勤手当の取り扱いについては、就業規則またはそれに準じた内規等を作成し社内の制度として整備されていれば実施可能と考えます。
質問②
通勤訓練を就業規程などで明確に必須、または慣例とした場合、業務指示性が生じることにはならないでしょうか。この辺り法律専門性や判例の対照が必要に感じますがいかがでしょうか。
■回答
通勤訓練は復職するための準備段階として位置付けられており、労務提供が目的ではないため、基本的には業務指示性は生じないとされています。業務ではないことから就業規則に明記があったとしても、労務提供に入らないと個人的には考えています。一方で、通勤訓練は、本人に協力を依頼し、意思決定は本人に行わせる流れが良いでしょう。協力いただくことで復職の判断の材料にすることも伝えきながらも、拒否する権利は本人に持たせておくことが安全と思います。
仮に就業規則に必須とし強制性を持たせた場合、業務の枠組みになるのかどうかは、一度、顧問弁護士に確認いただくのが良いかと思います(私も知識なく、教えてください。以下のブログはご参考までです。)https://sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2024/08/13/234319
質問③
先生のこれまでのご経験において、メンタル疾患に対する試し出勤の最終盤での業務負荷は、どの程度を目安とされていましたでしょうか(復職前と同等か、ある程度軽減されたものか。業務内容・勤務時間の観点を含めて。)よろしくお願いいたします。
■回答
メンタル疾患の試し出勤における最終段階の業務負荷については、個別性が高いと思われます。一般的に明確な目安があるわけではないですが、元来の職務で求められる程度の7割程度のイメージを持っています。時に10割を目指す企業がありますが、それであれば復職して通常業務をしていることと変わりなく、試し勤務における軽減業務の枠を逸脱していると考えます。
2 配置転換・職場復帰先の検討
質問④
嘱託産業医です。上司との人間関係が原因で、メンタル休職をさせた社員を復職させるときに、再度、同じ職場(同じ上司の下)に戻すことは適切でしょうか?それとも配置転換まで会社に配慮を求めるべきでしょうか?
■回答
まず個人的な見解ですが、その方の持つ業務スキルがあれば、人間関係が破綻している場合には、同じ職場に戻ることが生産的とは思えず配置転換を積極的にするのが良いと考えています。一方で、日本では現職復帰というのが基本的な考え方があり、それに適用するように求めてきている日本の産業保健の現状もあると思います。私としては、小売りなど同様の業務が他の場所でも展開されているような店舗などにおいては本人や職場との状況において、配置転換を積極的に行うことも勧めています。また公務員など異動が常時行っているような企業であっても同様です。一方、外資系などジョブで業務を行っている企業は、配置転換したくともヘッドカウントの関係で容易ではないでしょう。この辺りは現職復帰という原則を守りながら、どの程度会社が調整できるか企業ごとに考えるのがよろしいかと思います。
質問⑤
飲食業界のため、調理師・栄養士・管理栄養士・資格を持たない調理補佐をやっている社員がメインとなります。栄養士だと事業所によれば、半分は事務作業で半分は調理業務という仕事内容もあり、復職時の条件として「事務作業なら可能」と診断書が提出された場合、会社としてはそのように配慮をする必要があるのか。ご意見いただけますと幸いです。
■回答
難しいご質問ですね。この件は法的な側面が主ですので、私が回答するのは適切ではないかと思います。一般論ですが、大きいのは、その方の労働契約の内容だと思います。基本的に、労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合、その能力・経験・地位・企業規模等を考慮して配置可能性がある他の業務について労務提供が可能であれば、配慮すべきとされています。ただし、企業の規模や業種、配置転換の実情等を総合的に勘案し、現実的に不可能な場合は配慮義務の範囲外となります。診断書の内容と企業の現実的な対応可能性を産業医等と相談して判断することが適切です。栄養士として職務を限定して労働契約をしている場合は、基本的には栄養士としての業務を行っていただくのが原則と思います。この辺りはカントラ事件を参照にされても良いかと思います。
3 軽減勤務・復職条件・恒常化リスク
質問⑥
交代勤務が必須の職場で、メンタル不調から復職する社員に対し「夜勤ができること」を復職条件としています。しかし、服薬の影響などで夜勤が難しい場合もあり、会社側は「日勤のみは不可」として退職を求めることがあります。このような対応は、労務上・法的に問題ないのでしょうか?企業側に求められる配慮についてもご教示ください。
■回答
難しいご質問ですね。この件は法的な側面が主ですので、私が回答するのは適切ではないかと思います。顧問弁護士さんにも見解をお伺いください。ただ個人的見解で以下に記載します。労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合、その能力・経験・地位・企業規模等を考慮して配置可能性がある他の業務について労務提供が可能であれば、配慮すべきとされています。仮に交代勤務が難しいとして、日勤勤務ができるのであれば、「日勤のみは不可」として退職を求める対応については、法的問題が生じる可能性はあると考えます。労働契約書の内容にもよりますが、企業に求められる配慮としては、一定期間の夜勤免除、勤務時間の調整、配置転換の検討等があります(ただし、過重な負担の範囲を超えない範囲で)
質問⑦
復職の条件の一つ「当初”一定期間”業務を軽減すれば、ほどなく従前の業務を通常程度に行える健康状態にまでは回復している」とありましたが、一定期間の目安(何か月)とかあるのでしょうか?判例からは、6か月未満が一つの目安とされているように見受けられました。
軽減勤務を容認し、それが恒常化してしまい職位や職務に見合った業務をこなせない場合、職場のトラブルになるのではないかと懸念してしまいます。
■回答
厳密に期間を明示した裁判例はないと思います。ただ6か月は長く、業務量としても半分程度は軽すぎる、というのが裁判所の見解と思います。この辺りは他にも裁判例があると思いますが、「相当の期間」は、おおむね数カ月くらいと想定されているのではないかと思われます。
質問⑧
復職後に期待する業務について、復職時にマイルストーンを示すという先生のお話、非常に参考になりました。一点質問なのですが、例えば1か月後の期待値はクリアしたとして、その後にそれ以上のパフォーマンスが上がらないケースなどについて、軽減した業務でメンタル面は崩れていない場合などでは、再休職を勧めるわけにもいかないと思うのですが、その後の対応としては、どのようにしてゆけば良いのでしょうか?
■回答
1か月後の期待値をクリアしてもその後のパフォーマンス向上が見られない場合は、以下の対応が考えられます。まず、医学的観点からの問題です。例えば、病状が再燃していてパフォーマンスが出ていない場合は、主治医や産業医と連携しながら医療面での支援が必要かと思います。一方で、元来のパフォーマンスが悪く、病状は回復していても職位に合った業務が基本できない方もいます。その場合は産業保健の問題ではなく人事や労務の問題ですので、配置転換や業務内容の見直しも選択肢として考慮し、本人との面談を通じて今後のキャリアについて話し合ってもらいます。この点は、会社がしっかりしてないと産業保健側ばかりに対応を求められて、困った事例に発展しますので留意が必要です。また、病気による後遺症の影響(例えば統合失調症による認知機能低下など)などで、元来は業務できていた方であっても、疾患によってパフォーマンスが低下することがあります。その場合は合理的配慮の観点から、職務適性の再評価を行い、現在の業務が本人の能力に適しているかを検討したうえで過重な負担にならない範囲での対応が必要と考えます。
4 就業規則・制度の整備と運用
質問⑨
トライアル勤務の間、給与や通勤の交通費の支払いに関して、企業が負担すべきか、個人の負担とするか、どのように考えるべきでしょうか。
■回答
トライアル勤務期間(模擬出社、試し勤務)中の給与・交通費については、就業規則に明記された規定に従うのが原則です。繰り返しになりますが、会社が指揮命令を行い軽減した実際の業務に従事させる場合は賃金支払い義務が発生します。一方、指揮命令なしでリハビリとして行う場合は無給です。交通費についても同様の考え方が適用され、実質的な労務提供がある場合は支給対象となります。企業負担とするか個人負担とするかは、制度の目的と実際の運用方法により判断すべきです。まとめますと、模擬出社(①業務命令無し、②無給、③交通費は会社との交渉次第)、試し勤務(①業務命令あり、②有給、③交通費は支給)のように思います。
質問⑩
就業規則に、半日勤務の規定はあったのでしょうか?「ある場合は、その期間や条件などについてご教示ください。
■回答
半日勤務の規定については、企業の復職支援制度の一環として設けている企業はありますが、多くはないと思います。復職制度は、法的な制度ではないため会社の裁量での自由設計が可能です。こうしなければならないというものではありません。休職満了時の復職可否の裁判所の見解として「当初”一定期間”業務を軽減すれば、ほどなく従前の業務を通常程度に行える健康状態にまでは回復している」と解説しましたが、厳密に期間を明示した裁判例はないと思います。ただ6か月は長く、業務量としても半分程度は軽すぎる、というのが裁判所の見解と思います。この辺りは他にも裁判例があると思いますが、「相当の期間」は、おおむね数カ月くらいと想定されているのではないかと思われます。
質問⑪
貴重なお話ありがとうございました。休職期間満了が近いことから、体調が不安定なまま復職をし、その後パフォーマンスが出せない事例が頻発しております。
今後人事と会社の規則を構築していく予定ですが、現在休復職に関する規則が全くない状況のため、取り急ぎ産業保健職として対応できる方法はございますでしょうか?
抽象的なご質問となり申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
■回答
釈迦に説法ですが、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に基づく基本的な流れを人事部門と共有します。産業医面談の実施体制を整備(実施するタイミングを決めて)し、復職判定のための医学的基準を設定します。最終的には、人事や職場、産業医を交えた復職判定委員会のような合議の場を用意して復職可否を会社が決定するのがいいと思います。
短期的には、個別ケースごとに産業医意見書を活用し、主治医との連携や人事部門への助言を強化します。生活記録表や通勤訓練は比較的簡単に開始できると思うので、書類を用意して始めてもいいかもしれませんね。
5 主治医との連携方法
質問⑫
主治医との連携というのは手紙を会社が出すイメージでしょうか?本人のプライドが高く、疾病性の問題として本人が自覚することが難しいと考えられる場合の対応策の助言をいただけると幸いです。
■回答
主治医との連携は基本的に書面(診療情報提供依頼書)で行うことが一般的です。
連携の手順としては、従業員の同意を得て産業医が診療情報提供依頼書を作成し、従業員本人が主治医に持参するのが最善です。書面には職場環境、業務内容、復職判定基準等を具体的に記載します。ただし上記が最善であることは確かですが、現実には難しいこともあります。そのため、私は本人から口頭で許可を得て、直接に病院やクリニックへ書面を郵送することが多いです。その際は、本人に主治医が内容を見せる事も大いに考えられるため、本人から見られても耐えられる内容で記載することが適切と思います。
本人のプライドが高く疾病性の自覚が困難な場合は、現状の課題などは職場上司から本人へ職場で困っていることとして、フィードバックすることが必要と思います。企業によっては産業保健職に問題の指摘をさせようとしますが、これは問題が拗れてしまうことが多いため現場をよく知る職場上司が行うように依頼しています。そのような場面は、本人、人事、上司、産業保健スタッフなどが膝を突き合わせて行うのが良いでしょう。必要に応じて、産業医から医学的な説明を行い、治療の必要性を丁寧に説明することが効果的です。
質問⑬
産業医から主治医への連携はどのようにしたらよいでしょうか。手紙や電話、FAXなど、具体的に知りたいです。ご本人に持参いただくのが最善でしょうか。
■回答
産業医から主治医への連携方法としては、最も推奨されるのは紹介状による書面でのやり取りで、連携の手順としては、従業員の同意を得て産業医が診療情報提供依頼書を作成し、従業員本人が主治医に持参するのが最善です。書面には職場環境、業務内容、復職判定基準等を具体的に記載します。ただし上記が最善であることは確かですが、なるべく本人に内容を見てほしくないこともあります。そのため、私は本人から口頭で許可を得て、直接に病院やクリニックへ書面を郵送することが多いです。その際でも、(本人に主治医が内容を見せる事も大いに考えられるため)本人から見られても耐えられる内容で記載することが適切と思います。電話での連携も可能ですが、個人情報保護の観点から事前の同意が必要です。今は都心では断るクリニックも多いです。FAXは医療機関同士でなければ受け付けてくれないでしょう。いずれの方法でも、従業員の事前同意と、職場環境・業務内容の詳細な情報提供が重要です。
6 企業への働きかけ
質問⑭
休復職制度を変えましょうと人事担当者に伝えても動きがなく悩んでいます。佐々木先生が休復職制度の不備に気づき改善したいと考えたとき、会社に対してどのように働きかけるのか教えて下さい。
■回答
なかなか難しいご質問ですね。直ぐには難しいと思います。就業規則の変更というのは、かなり労力がかかることがあり、組合などが強い場合は不利益変更となることから交渉が難航することもあります。一方、就業規則を変えられなくても復職時のリハビリ勤務(模擬出社、試し勤務)などの制度については、就業規則でなくても、例えば内規のガイドラインとして会社内で運用することも可能と思います。
まずは、具体的な事例の共有や勉強会などで、人事が会社制度の不備に気がつく機会を作る必要があります。また、再休職防止による人件費削減、間接コスト削減など視覚的に見える金額とすることで、機会があれば、経営層への議題として取り上げることも効果的です。
7 支援の頻度・支援者側の負担・コミュニケーション
質問⑮
「産業医は職業的見地から意見を述べ、実際の指示や辞令はその意見を元に会社だすもの」と把握していますが、こういった内容を把握しておらず「産業医からの指示により」といった形で、復職などの辞令を出す会社があり困っています。
こういったケースに対して、会社にどのように申し入れれば良いのでしょうか?
また、不測の事態を避けるためにも、やっておくべき事や残すべき記録などについても、教えていただければ幸いです。
■回答
ご質問ありがとうございます。私もよく遭遇する困った案件で大変共感します。私の場合は、就業規則などを確認してもらうようにします。通常は、産業医は復職に関する医学的な意見であり、復職は会社(≒人事)が命じることであることをまずは確認したりします。また、勉強会を開催したりして、実際の決定は会社が行うことを理解いただく場を設けたこともありました。そのほか、職場復帰に関する産業医の意見書の作成の際に、定型文として、「医学的見地から職場復帰に関する意見であり、最終判断は会社が行う」といった内容を明記しても良いかと思います。
残すべき記録としては、産業医の意見書には、医学的な見地からの安全配慮も加味した、内容を記載するように心がけています。また、産業医面談記録には、会社への助言内容、産業医として判断した根拠を記載しています。第3者が閲覧したとしても耐えうる内容を意識してください。
質問⑯
現職では、休職者の産業医面談は復職診断書が提出された後、または本人が希望したとき(ただし事前に保健師がヒアリングを行い産業医面談を行う必要があると判断した場合)のみに行っておりますが、休職中の産業医面談を行う頻度(定期)や、ケースについてご意見をいただきたいです。
■回答
休職中の産業医面談は、マンパワーや勤務時間のリソースなどでも異なり、個人的には全ての休職者に行う必要はないと考えます。そのため、面談の頻度は休職者の状態、治療の進行状況、復職までの期間等を考慮して個別に決定します。嘱託産業医の場合、休職満了が近い長期の療養者に関しては満了となる3~6か月前ぐらいからは、定期的に面談を行なうと良いでしょう。日ごろの生活リズム、体調などを確認して、どのような状況であれば職場復帰できるのかコミュニケーションしつつ記録しておくことが大事だと思います。これは、面談記録の蓄積により、復職判定時の重要な判断材料となるだけではなく、本人とのトラブルを避け、訴訟リスクも考慮した対応となります。
質問⑰
うつ病で8か月休職中。本人の特性が強く、それが根本的な原因と考えられるが、自覚がない(労務の問題として、数回指導もしている)。配置転換・短時間勤務を必須として復職可能との診断書をだされた。会社としては異動先もないので、リワークをしてほしい。本人はリワークなんか嫌だと拒み続けており、休職延長となっている。本人の焦りもあり、上司や産業保健スタッフに頻繁にメールを送ってこられるため、支援者側が疲弊している状態。一方的な主張が繰り返されており、1時間2時間対応し続けている。どういう対処が望ましいでしょうか。
■回答
ご質問ありがとうございました。ここでご提供いただいた文章だけでは状況がつかめず、お答えが難しいところがあります。背景がわからない中でのご回答となりますが、主治医の診断書に配置転換や短時間勤務の記載がありつつも、会社では配置転換(会社規模、本人の能力、経験、スキルの観点から検討)や短時間勤務が難しい場合には、復職を不可として、通常勤務ができるようになるまで療養延長していただくのがよろしいかと思います。その際、主治医には、会社の判断として通常勤務ができない状況であればまずは、休職期間が残されていることから、療養に延長となった旨をお手紙で、お伝えいただくのがよろしいでしょう。
本人には、会社が職場復帰できると判断するには、どのような状況になっていただきたいか説明しておくのは一つです。時間通りの出勤、職位に求められる業務内容、他者との円滑なコミュニケーション、就業規則の順守など、このようなことが可能になって、初めて職場復帰と判断することを会社から伝えるようにしてください。リワークを拒否されているとのことですが、会社の判断材料の一つにリワークがあることを伝えると本人にも通うメリットが生まれます。上記は、産業保健職ではなく、人事担当者が前に出て伝える情報です。また面談は、開始前に対応できる時間の限界を伝えたうえで、時間になったら、途中でも切り上げ、次のアポイントを決めて終了するのが適切と思います。
質問⑱
小さな会社であるため、人事と産業保健スタッフ(ストレスチェックや衛生管理者・休職復職支援)を1人が担っている場合に、「つなぐ」ということが難しい状況に直面しています。支援する立場も担いつつ、労務の問題点を指摘したときに、休職者から「復職の話をするまでは優しかったのに対応が急に変わって混乱する」と言われてしまい、どう対応するのが正解か困惑してしまうことがあります。
■回答
正解が難しいのですが、私ならどうするかで回答します。私なら主に人事担当者のお立場で対応すると思います。休職者には、最初に職場復帰には、どのような条件が必要であるかを明示しておきます。よくあるのは、復職の流れを示した社内の文書としてまとめ、休職開始時に本人にお渡ししたりします。その文書の中に、復職に関する条件を明示したうえで、職場復帰までに至る過程を支援することを伝えます。職務復帰とは、現職の業務ができる、8時間働ける、他者と円滑なコミュニケーションをとれる、労働契約に基づく労務提供できること、などです。そのあたりを「会社の基準」として示した上で、担当者として、「一緒に職場復帰を目指しましょう」というスタンスが望むかと思料しました。
8 障害者雇用・合理的配慮
質問⑲
障がい者雇用をしている会社において、障がい者が、メンタル不調で休職している際の、復帰のステップについて、原則、健常者と同じでよいのでしょうか?あるいは配慮すべき点はありますか?
■回答
障害者雇用における復職ステップは、基本的には健常者と同じ流れですが、合理的配慮の提供範囲の再検討が必要となることがあります。また、主治医だけでなく、必要に応じて精神科医や障害者支援専門医との連携もより丁寧にした方が良いかと考慮します。過剰な調整は必要なく、合理的配慮の範囲内での支援を提供することが求められます。
9 その他
質問⑳
前産業医による就業制限(時間外勤務制限、夜勤制限)が数年間続いている復職者が複数名います。どのように介入していけばよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
■回答
これは私も苦慮した経験があります。数年間継続している就業制限については、基本に立ち返り、医学的根拠の再評価が必要です。主治医から最新の情報を取得し、現在の医学的状態の確認、就業制限継続の必要性の検討、段階的な制限解除の可能性を検討します。産業医として、医学的に問題を認めなければ、健康問題ではなく、労務問題となりますので、就業制限を解除し、職場での働き方について現場で方針を決定してもらうようにします。
引き続き、主治医から就業制限が必要である旨の意見が出され医学的に妥当と考える場合は、就業制限を行い定期的な面談で経過を追いつつ、合理的配慮の枠組みで調整が可能か、または配置転換なども含めた人事的側面からの検討も必要に思います。
質問㉑
佐々木先生が対応に苦慮した事例で印象深かった事例を教えて下さい。
■回答
個別の具体例をお伝えすることは難しいのですが、私は、毎月150名以上の産業医面談をしている面談マシーンですので、正直ありとあらゆる事例を経験してまいりました。そのような中で、苦慮することも多かったのですが、とにかくすべて一人で抱え込んで解決しようとせず、人事や職場とも話をしながらチームでことにあたることが重要だと思います。企業によっては産業保健職に人事の問題を解決させようとしますが、これでは問題が拗れてしまうことが多いです。各人が責任を持った役割分担をしながら、本人、人事、上司、産業保健スタッフなどが膝を突き合わせて丁寧に対応することで、どんな事例も上手くいくことが多いと実感しています。






