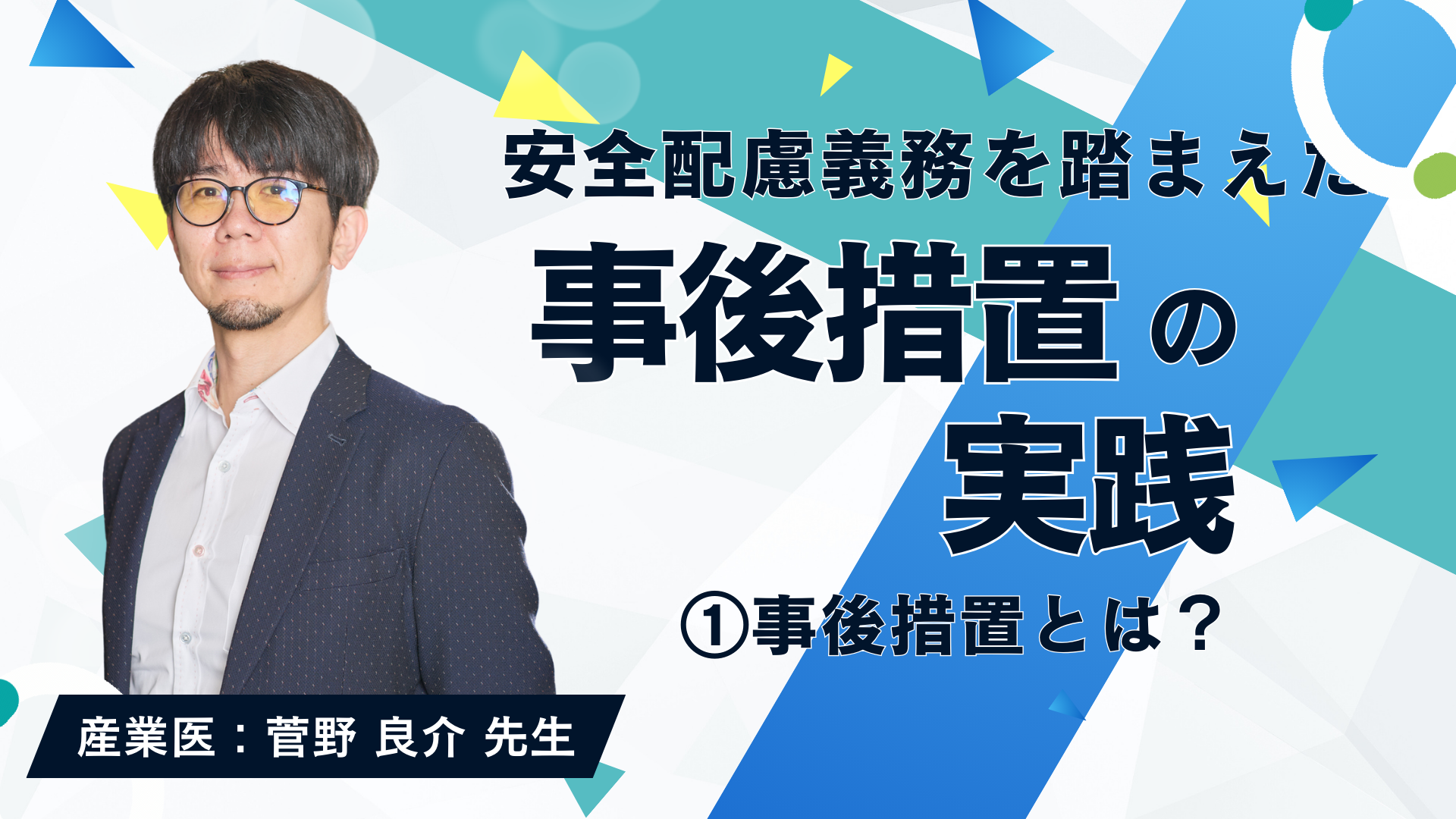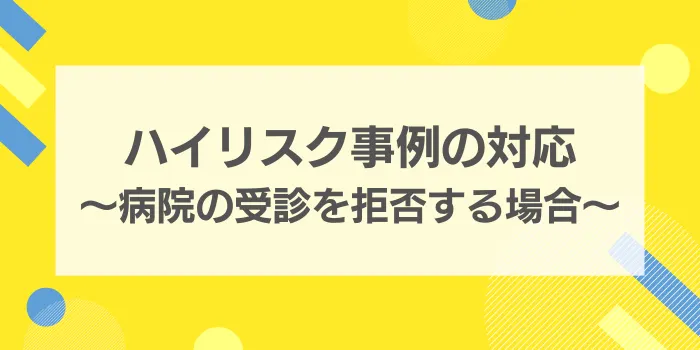「復職面談って、やっぱり難しい」――そんな悩みに応えるために
メンタルヘルス不調からの復職において、産業医が行う「復職面談」は、限られた時間と情報の中で復職の可否を判断しなければならない難しい業務のひとつです。
新任の産業医の先生方からは、「何を確認すればよいのか」「どんな基準で判断すればよいか」といった質問をよく耳にします。非常勤で勤務されている先生方にとっては、社員との関係性が十分にできていない中で判断を求められることも多く、戸惑いやすい場面かと思います。
さらに、復職支援制度が十分に整っていない職場では、企業の担当者も実務に不慣れで、産業医に判断を一任するようなケースや、中には、初対面の社員との一度きりの面談で復職の可否を判断せざるを得ない状況もあります。
復職のタイミングが早すぎると、回復が不十分なまま復帰し、徐々に疲労が蓄積して再休職に至るリスクが高まります。その一方で、回復が不十分と判断して復職を見送る場合には、社員や関係者の心情にも配慮しながら説明する必要があり、産業医の対応に慎重さが求められます。
本人や職場との関係性が十分に築けていない状況では、「なぜ復職できないのか」という落胆や反発も予想できます。このように、復職面談の場面では、伝え方や、職場との調整を行うコミュニケーション能力も問われることになります。
さらに、復職後の業務調整についても、主治医の診断書には「業務負荷の軽減」「段階的な業務調整」などと簡単な記載になっていることがほとんどです。職場にそのまま伝えても、どう対応すればよいのかわからず、不十分な対応になるおそれもあります。そこで、産業医には、適切な業務調整の内容をわかりやすく説明し、必要な措置が確実に実施されるよう、職場と丁寧にすり合わせる役割も求められます。
再発防止の側面を考えると、本人との面談の際には、ストレス要因の把握や、業務・環境調整の要否、セルフケアや再発予防への助言なども検討課題になります。とくに、休職を繰り返している社員には、より慎重な対応が必要です。
このように、復職面談にはさまざまな要素があるため、それぞれの事例に適した対応が求められます。本記事では、以下の4つの観点から、実践的な対応のヒントを整理していきます。
- 復職可否を判断する際の視点
- 面談で確認すべき具体的なポイント
- 復職後の業務調整の工夫
- 不調の背景や再発防止に関する対応
産業医として、どのように対応していくべきか、一緒に考えていきましょう。
<目次>
1. 職場復帰の可否の判断
2. 復職時の業務調整 ― 段階的な復帰の視点
3. 職場への再適応支援
4. おわりに:復職面談を「その後の支援」につなげるために
1.職場復帰の可否の判断
復職可否の判断 ― 早すぎる復職を防ぐ視点
メンタルヘルス不調の復職支援においては、主治医の診断書に「復職可能」と記載されていても、慎重な判断が必要です。本人の「早く復帰したい」という強い希望を受けて、やや早めのタイミングで診断書が提出されることも少なくありません。
産業医は、診断書の記載内容だけに頼らず、「今が本当に復職に適切なタイミングか」を丁寧に見極めることが求められます。まだ十分に回復していないときに復職すると、疲労が蓄積して症状が再燃・再発し、再休職に至るリスクが高まります。
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」には、復職可否を判断するための判断基準の例として、十分な意欲、安全な通勤、就労継続の可否、疲労の回復、適切な睡眠リズム、注意力や集中力の回復など、複数の項目が示されています。ただし、これらはあくまで目安であり、明確な基準が設けられているわけではありません。実際の判断は産業医や企業に委ねられています。
また、面談の場では、復職を強く希望する本人が、実際の体調よりも元気にふるまったり、本当は不安や不調があっても「大丈夫です」と答えてしまうこともあります。こうした背景から、復職可否の判断には、面談時の様子や、主治医の診断書だけでなく、より具体的で、客観的な評価指標の活用が重要になります。
生活記録表の活用 ― 誰にでもわかる判断基準
生活記録表は、起床・就寝・外出など1日の活動内容を記録するシンプルなツールで、回復の状況を可視化できるという利点があります。精神疾患では睡眠リズムの乱れや活動性の低下がよく見られるため、生活リズムの回復と安定を確認することが、復職判断における重要な判断材料になります。
生活記録表は、簡単に記入できる上、特別な知識がなくても理解しやすく、職場の上司や人事担当者にも説明しやすいため、納得感のある判断材料となります。生活リズムや活動性を可視化できるため、客観的に評価しやすい資料として、復職に向けた共通理解を生む助けにもなります。
復職可否の判断のためには2~3週間分の記録が必要となるため、復職希望の意思が示された段階で早めに記入を開始してもらうことが大切です。生活記録表の使用を社内の復職支援プロセスに組み込んでおくことで、運用がスムーズになります。また、休職中から産業医が月1回程度定期的に連絡を取り、生活状況を確認しながら記録のフォローを行う方法も有効です。
上記の生活記録表/生活リズム表のExcelテンプレートは以下より無料でダウンロードいただけます👇
復職の判断基準としては、例えば「①平日の朝は出勤に間に合う時間に起きていること、②日中は午前9時ごろから午後3時ごろまで外出して過ごしていること、③こうした生活リズムが週5日×2週間以上続いていること」などを用います。こうした状態が確認できて、はじめて復職の準備が整ったと判断します。
生活記録表を活用した復職可否の判断は、専門家の間でも一定のコンセンサスが得られており、復職後の再発防止にもつながるという報告があります。エビデンスに基づいた実践的な方法として、自信を持って活用できます。
リワークプログラムの活用 ― 早めの検討と丁寧な説明がカギ
復職の準備のために、医療機関や支援機関が提供する通所型の「リワークプログラム」を活用することも有効です。一定期間、毎日、継続して参加できていれば、生活リズムや体力の回復と安定が確認でき、復職判断の材料になります。
ただし、リワークプログラムは、申込みから利用開始までに時間がかかることが多く、また、終了までに3~6か月程度の通所が必要となります。主治医の「復職可」の診断書が出てから、産業医が初めて提案するという対応では、復職の時期が大幅に遅れ、本人の不満につながることもあります。リワークの利用を検討する場合は、できるだけ早めに、本人の状況や残りの休職期間を考慮して提案することが大切です。
また、地域によっては利用可能な施設が限られるため、近隣のリワーク施設の情報を事前に把握しておくと安心です。復職に対する不安の強いケースや、再発歴があるケースなどでリワークの活用が推奨されています。
2.復職時の業務調整 ― 段階的な復帰の視点
メンタルヘルス不調からの復職では、「復職可否の判断」と並んで重要なのが「復職後の業務調整」です。復職直後は、以前ほど体力や集中力が戻っていないため、最初から100%のパフォーマンスを求めることはできません。業務負荷を軽減し、数か月かけて徐々に戻していく段階的な調整が必要です。
しかし、主治医の診断書には「当面は業務の軽減を」「対人折衝を控えるように」「段階的な復帰を」などと記載されていますが、それだけで具体的な業務内容を調整するのは難しく、職場任せにすると対応が中途半端になりがちです。
復職プラン用紙の活用
職場での業務調整を、毎回、ゼロから組み立てるのは難しいため、あらかじめ「復職プラン用紙」などのテンプレートを準備しておくと、本人や職場と共有しやすく、調整がスムーズに進みます。例えば、以下のような用紙を用いて、復職後6か月間の段階的な復職プランを検討するようにします。
| 月数 | 就業制限 | 業務内容の目安 |
|---|---|---|
| 1~2か月目 | 残業なし・出張・外出なし | 定型的・作業的な業務中心/対人折衝なし |
| 3~4か月目 | 残業10時間以内・外出可 | 業務範囲を拡大/補助業務から元の業務に徐々に移行 |
| 5~6か月目 | 残業20時間以内・短期間の出張可 | 責任ある業務や出張も一部再開/新しい担当業務の引き継ぎ |
| それ以降 | 就業制限解除 | 通常の業務の体制に移行(無理のない範囲で) |
営業職など、対人折衝が多い職種では、最初の1か月は内勤業務に限定し、2か月目からは上司や同僚と同行訪問を週1~2回実施。3~4か月目で引き継ぎや訪問回数の増加、5~6か月目で主担当としての準備を進め、半年後に独立した担当者として業務に戻す、という調整が効果的です。職種に応じた具体的な目安を示すことが、現場の納得感にもつながります。
上司と相談しながら復職プランを作成する
復職プランの検討を上司に依頼する際には、できるだけ対面での打ち合わせや、オンラインミーティングなど、直接、説明する機会を設けるとスムーズです。復職プラン用紙を見せながら、就業制限の内容や、どのような業務が適しているかを説明すると、上司もイメージしやすくなります。あわせて「どの業務をいつから任せられそうか」「出張の再開は何か月目から可能か」など、具体的な相談を重ねることで、現実的な復職プランを考えてもらうことができます。
上記の両立支援プラン/復職支援プランのWordテンプレートは以下より無料でダウンロードいただけます👇
3.職場への再適応支援
①面談における心理的支援の考え方
現在、心理療法や心理教育の現場では「認知行動療法(CBT)」の枠組みが広く活用されています。これらの考え方は、職場のメンタルヘルス支援、特に、復職後の再発防止などに応用が可能です。
産業医が現場で認知行動療法を実施する必要はありませんが、基本的な考え方を理解しておくことで、より適切にケースをアセスメントできるようになり、本人や職場への説明が的確になったり、面談での説明や助言の内容に具体性や説得力を持たせることができます。
②ストレスを感じる場面と再発サインの特定
復職後の再発を防ぐためには、本人がどのような業務・場面・人間関係にストレスを感じていたのかを、できるだけ具体的に整理しておくことが大切です。特に「どんな状況で」「何が」「どのように」ストレスだったのかを明確にすることが役立ちます。
例えば「営業の仕事が苦手」という事例では、営業の仕事のうち、訪問先とのやりとり、営業会議での報告、提案書の作成など、どこがストレスだったかをより丁寧に聞き取ります。人間関係についても同様で、「先輩社員との関係がストレス」という場合には、いつ・どこで・誰との・どんな場面・状況・会話・言動が負担だったのかを、具体的に特定していきます。
こうした要因を具体的に特定できると「復職直後はそうした場面を少なくする」「段階的にアサインする」「必要に応じてサポートを得られる体制を整える」など、現実的な業務調整の方向性や、対応を工夫できそうなポイントが見えてきます。
さらに、過去に体調を崩した場面や、その際に現れた症状の特徴を振り返ってもらうことで、再発のサインを早めに察知できるようになります。実際、復職後に症状が再燃する際には、以前と同じような状況で、同じような症状が出るケースが少なくありません。こうしたパターンを事前に本人と共有しておくことで、セルフケアや再発予防にもつながります。
③フォローアップ面談のすすめ
復職後の再発を防ぐためには、復職後のフォローアップ面談を継続することが重要です。フォローアップ面談は、初回は復職後2~3週間に実施し、その後は月に1回程度の面談を継続します。安定してきたら2か月に1回に間隔を延ばしても構いませんが、少なくとも半年程度は、継続的な支援を行うのが望ましいと考えられます。
フォローアップ面談では、就業制限が適切に守られているか、治療が継続されているか、体調や就労状況に問題がないか、以前と同じような場面でうまく対応できているか、といった点を確認します。産業医が継続して関わることによって、本人の安心感が高まり、職場への適応も進みやすくなります。
4.おわりに:復職面談を「その後の支援」につなげるために
復職面談は、限られた情報の中で復職の可否を判断し、再発を防ぐための支援計画を組み立てていく、産業医にとって重要かつ難易度の高い業務のひとつです。特に、メンタルヘルス不調からの復職では、診断書の内容だけでは判断が難しい場面や、職場との調整が必要となる場面も多くあります。
本記事では、生活記録表や段階的な業務調整、フォローアップ面談など、復職支援を進めるうえで実際に役立つ視点や方法を紹介しました。こうしたツールや考え方を活用することで、より納得感のある判断や、継続的な支援が可能になります。
復職支援の実務に関わる産業医や産業保健スタッフの皆さんにとって、本記事が少しでも実践のヒントとなれば幸いです。
■執筆
難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌を執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』