9月1日は「防災の日」、8月30日〜9月5日は「防災週間」です。
職場における防災対策の見直しや訓練の実施に最適なこの時期、企業の衛生管理者にとっても重要な役割が問われます。
本記事では、防災週間の意義とともに、災害時に衛生管理者が担うべき責務や、職場全体で取り組むべき防災対策、他テナントやビル管理者との連携ポイントを具体的に解説します。
「災害はいつでも起こり得る」――その現実に向き合い、職場の安全と従業員の命を守る準備ができていますか?
<目次>
1.防災の日・防災週間とは?
2.衛生管理者が担う「防災」の役割とは
3.防災週間に見直したい職場の災害対策
4.防災訓練に衛生管理者が関わるメリット
5.災害後の支援と衛生管理者の役割
6.まとめ:防災の日をきっかけに「備え」を見直そう
1.防災の日・防災週間とは?
防災の日は9月1日です。関東大震災や伊勢湾台風など、過去に襲来した災害をきっかけとして定められました。また、防災週間は8月30日から9月5日までの1週間のことを指します。防災の日や防災週間には、防災への意識を高めるため、全国で避難訓練や救命講習などさまざまな防災・減災を目的とした訓練が実施されます。 救命講習の中でAEDの使い方や心肺蘇生法なども学べるので、非常時に備えた一次救命処置の仕方を身に付ける大切な機会といえるでしょう。
その他の○○デー/週間/月間について知りたい方はこちらをご覧ください👇
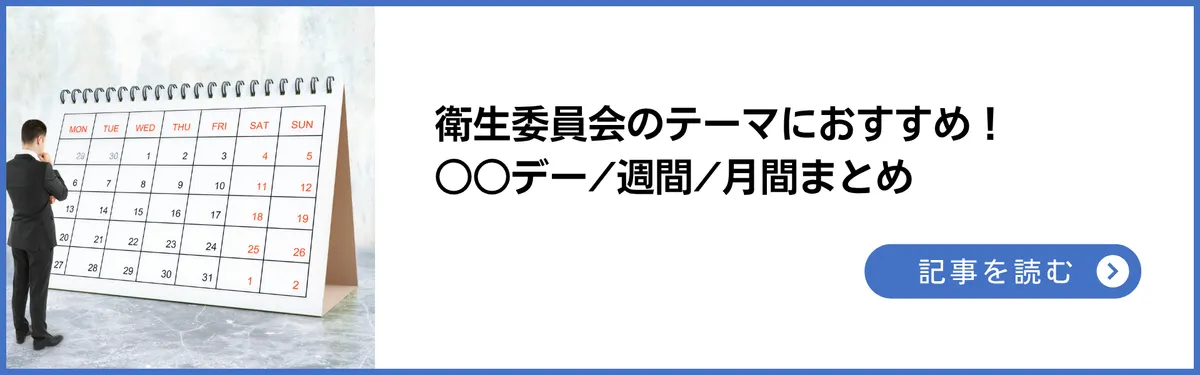
2.衛生管理者が担う「防災」の役割とは
衛生管理者は、職場の衛生環境を管理し、労働者の健康を守る専門家である立場から、災害発生時の人的・物的被害を最小限に抑えるための対策を講じ、従業員の安全確保と事業継続に貢献する必要があります。「防火管理者」「防災管理者」「安全管理者」など、防災に関して設置されている他の管理者と役割分担や連携を行いながら、避難経路の確保、防災設備の点検、防災訓練の実施、地域との連携などを担当します。
オフィスビルやテナントビルの一室に入居して業務を行っている企業も数多くあるため、地震や火災などの災害が発生した際、自社だけでなくビル全体としての対応が求められる場面も多くなります。ビル全体の防災対応は防災センターやビル管理会社に主導的な役割がありますが、例えばテナントビルの防災担当者や防災センターとの連携や情報共有といった、自社の代表としての役割があることにも意識を向けておくと、より防災体制を強化することにつながります。
災害時には、ビルに入居している複数の企業が同時に避難や初期対応を行うことになります。その際、避難経路の確保や安全確認、避難誘導などをスムーズに行うためには、テナント同士の連携が不可欠です。
特に、大規模なオフィスビルでは1フロアに複数の企業が入居しているケースもあり、避難経路の共有や非常口の使用方法について、共通の認識を持っておくことが重要です。
以下に、自社内での防災体制の整備と、他テナントやビル管理者との連携における防災体制の整備についていくつか例を挙げます。
■自社内での防災体制の整備
- 想定される災害時の危険箇所や対応すべき設備(非常口、消火器、AEDなど)の点検などのリスクアセスメント
- 避難誘導手順、安否確認フロー、帰宅困難者対応などの手順書作成・更新といった災害時のマニュアル整備と見直し
- 安全衛生委員会と連携した防災訓練の定期的な実施
- 非常食、水、毛布、トイレ、ヘルメット、懐中電灯などの備蓄状況の管理
■他テナントやビル管理者との連携における防災体制の整備
- ビル全体の防災訓練への参加・調整
- 災害時の連絡網(テナント間・ビル管理者)の整備など情報共有体制の構築
- 共用部分の安全確認や共用備蓄の使用ルールの確認
- ビル全体の避難経路や非常口の情報の把握
- フロア単位での誘導役を事前に決めておくなどの連携体制づくり
特に建物や設備の点検、火災や地震時の危険源の特定・除去、避難経路の安全確保など、災害による人的・物的被害を防ぐための安全対策においては、安全管理者と連携して行うことも重要です。
災害は「いつか」ではなく「いつ起きてもおかしくない」現実であり、いざというとき命より大切なものはありません。しかし、日々の業務の中ではその実感が乏しくなりがちです。防災訓練や指導は参加者は受け身となり、形骸化しがちです。職員全員が主体的に自分事として取り組めるような体制を整えていくことも、衛生管理者の大切な役割です。
例えば職場の構成人数にもよりますが、初期消火班(火災時)、通報班、救護班など、いくつかの役割でチームを作り、各部署を割り当てておくといった方法も、自分事として捉えてもらうために有効です。こうした班体制は、消防法に基づき防火管理者が中心となって組織する「自衛消防隊」としても位置づけられるものです。各チームで代表者を決めておきつつ、代表者が休みでいなかった場合は担当の部署で役割を担ってもらう、といった具合に決めておき、その内容に沿った防災訓練を行うと効果的でしょう。
従業員向けに災害による健康リスクや職場で行うべき備えについて発信する際は、ぜひ以下の衛生講話資料をご活用ください👇
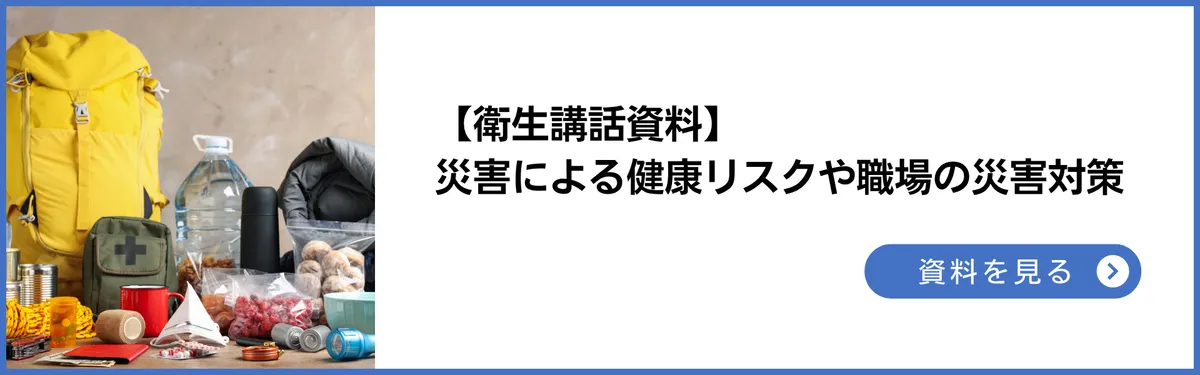
3.防災週間に見直したい職場の災害対策
防災週間は、普段防災意識のない人も巻き込んで職場の防災対策を行える絶好のチャンスです。以下の内容を従業員全員を積極的に巻き込んで行いましょう。
■避難経路と非常口の表示の整備状況の確認
レイアウト変更により避難経路がふさがれていないか、非常口が明確に表示されているか点検しましょう。また訓練時に職員それぞれが避難経路を知っているか?非常口がどこか知っているか?消火器の場所を知っているか?といった確認を一緒に行うことも効果的です。
■従業員への防災マニュアルの周知状況の確認
災害と言っても、地震・火災・停電など、複数の事態が想定されます。それぞれに対し、防災マニュアルの整備や防災訓練といった災害対策が必要となります。
特に地震の場合、東日本大震災の時には帰宅困難者が大量発生したことから、避難するのか、帰宅するのか、といった基本的なジャッジを事前に会社のルールとして決めておくこと、そしてそれを従業員の共通理解として周知することが大切です。また企業と従業員間の安否確認の方法の確認や、従業員がそれぞれ家族とどのように緊急時の連絡を取るのか、といったこともこの機会に議論し確認しておくことが必要です。
日頃からの備えについて従業員に向けて発信する際は、ぜひ以下のリーフレットをご活用ください👇
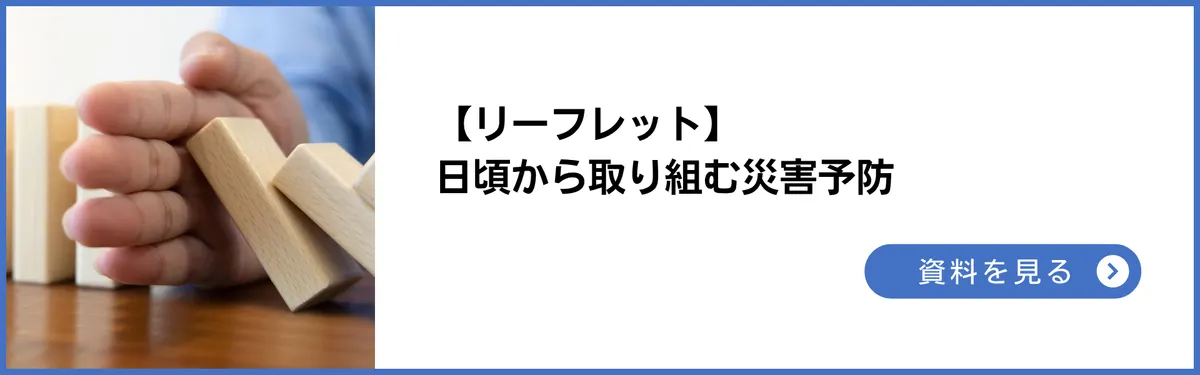
■備蓄品の点検
帰宅する場合に従業員に持たせる「帰宅セット」や会社に留まる際に必要な数日分の水・食料・簡易トイレなど、災害時に必要なものがきちんと従業員全員分そろっているか、有効期限が切れていないかを確認します。部署単位で従業員自身に点検を任せるのも一案です。
4.防災訓練に衛生管理者が関わるメリット
衛生管理者は日頃から職場の労働衛生リスクを把握しています。そういった専門的な立場から防災訓練にかかわることで、職場全体の健康・衛生・安全面の実効性が高まり、災害時の実際の対応力が向上します。組織全体のレジリエンスが強くなり、企業の価値の一つとしても対外的にアピールすることができる資産ともなりえます。衛生管理者が防災訓練に関与することで発揮できる主な役割を3つの観点から紹介します。
① 職場リスクへの知見を活かした安全な避難体制の構築
- 換気状態や熱中症リスクといった健康面も踏まえた避難経路・集合場所の設定
- 化学物質や粉じんによる被ばくなど、災害時特有のリスクへの備え
- 避難時の人の密集や心理的ストレスによる健康リスクの把握と対応
② 応急処置・健康管理に関する専門的な支援
- 応急処置の手順確認や訓練への助言
- 熱中症・心疾患など、持病を持つ従業員への配慮策の検討
- AED(Automated External Defibrillator; 自動体外式除細動器)の設置場所の確認や使用訓練の計画支援
応急処置含む緊急時の対応について発信する際は、ぜひ以下の衛生講話資料をご活用ください👇
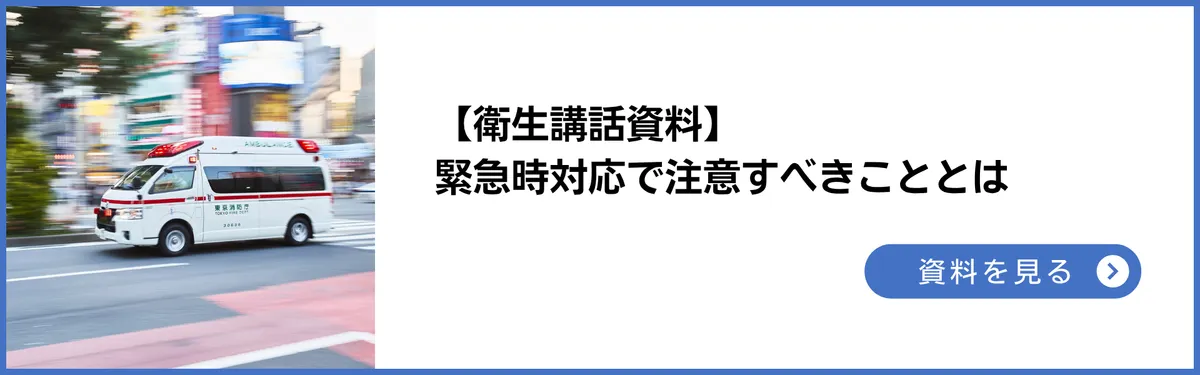
③ 多角的な危機管理への視点を提供
- BCP(事業継続計画)と連動した衛生対策の検討
- 感染症流行時も含めた災害時・災害後の衛生管理
- メンタルヘルスや心理的ケアを踏まえた安全配慮の提案
5.災害後の支援と衛生管理者の役割
災害後の支援において、衛生管理者は職場の安全と従業員の健康を守るために重要な役割を果たします。まず、避難所や仮設施設では、飲料水や食料、トイレの衛生管理が不十分になりやすく、感染症の発生リスクが高まります。衛生管理者は、手洗いや消毒の徹底指導、衛生用品の管理・配布を通じて、感染症予防に貢献します。また、瓦礫撤去や復旧作業では粉じんや化学物質への暴露が懸念されるため、防塵マスクの着用指導や作業環境の安全確認を行います。
加えて、災害時は精神的ストレスによる体調不良が増加します。衛生管理者は、必要に応じて産業医やカウンセラーとの連携を図りながら、社員の精神的な健康状態の把握や心身の健康維持の支援を行います。さらに、衛生管理者は災害時対応マニュアルの整備・改善に関わり、今後の災害に備えた職場環境の再構築にも関与します。
このように、災害後の混乱期においても衛生管理者は職場の衛生・健康管理の中心的存在として、従業員の安全と事業の早期再開に貢献します。
6.まとめ:防災の日をきっかけに「備え」を見直そう
9月1日の防災の日と防災週間(8月30日~9月5日)は、職場の防災体制を見直す好機です。避難経路や備蓄品の点検、防災マニュアルの更新を行い、全従業員が対応方法を理解することが重要です。衛生管理者は、健康リスクや応急処置、感染症対策、精神面のケアを含めた実践的な防災訓練を主導し、災害時・災害後の安全と衛生を支える要となります。ビル全体や地域との連携強化も忘れずに行いましょう。
災害の各フェーズにおける産業保健スタッフの役割やポイントについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください👇
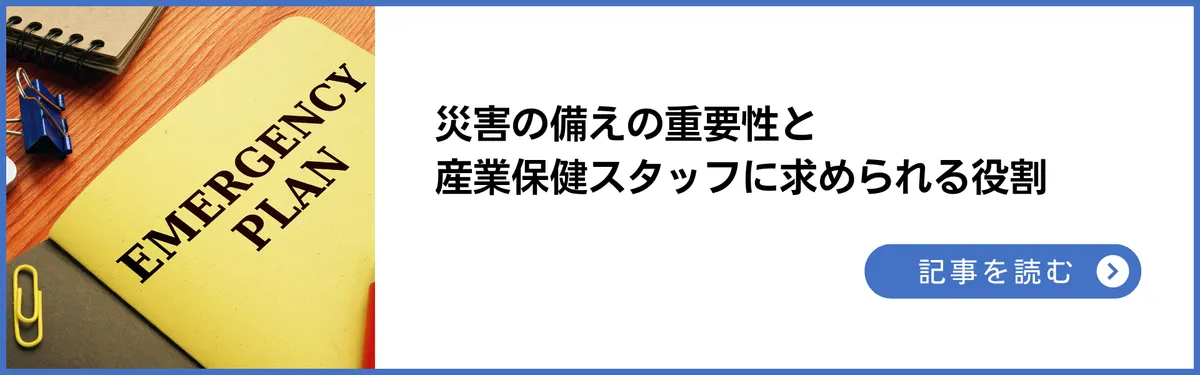
■執筆/監修
<執筆> 衛生管理者・看護師
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』




