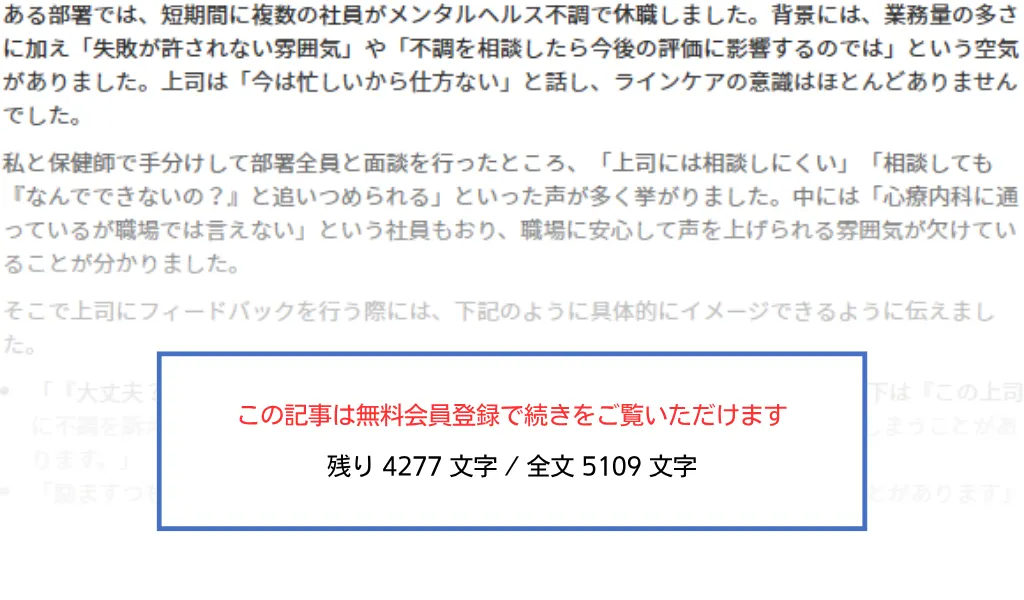はじめに
産業医として多くの職場を訪れる中で、「ラインケアは導入しているが、うまくいっていない」という声を何度も耳にしてきました。研修を受けて意識しているつもりでも、現場では部下が「相談できない」「気付いてもらえない」と感じ、不調が表面化するケースが少なくありません。私はこうした経験を通じて、上司の「できているつもり」と部下の実感の間にあるギャップこそが大きな課題だと感じています。
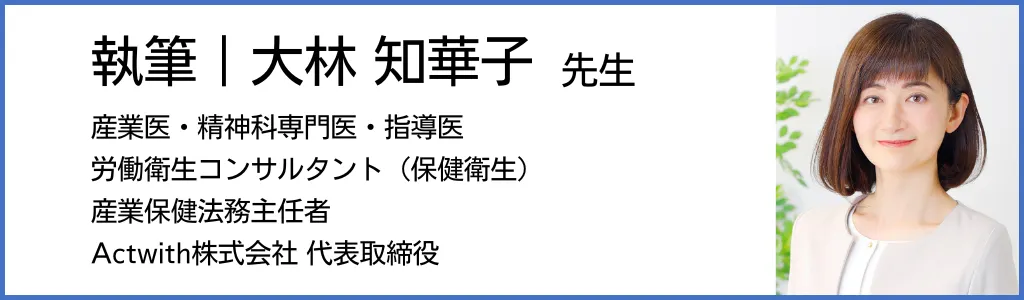
<目次>
1. 「できているつもり」の壁
2. ケース①:不調者が続いた部署で見えた上司の課題
3. ケース②:復職支援で見えた配慮の落とし穴
4. ケース③:リモートワークで見えにくくなったサイン
5. 研修を印象に残す工夫
6. 研修の場から見えてきたこと
7. ラインケア研修の意義と今後の展望
8. おわりに
1.「できているつもり」の壁
ラインケア研修でよく出てくるのは、管理職の「自分はできているはず」という言葉です。
「部下に定期的に声掛けをしている」「体調が悪そうなら気付いている」と多くの上司は話します。ところが実際に部下へ聞き取りを行うと、「形だけの声掛けに感じる」「上司に相談しても話は聞いてくれるが、何も変わらない」といった声が返ってくることも少なくありません。
この背景には、上司が「声をかけた」という行為自体に満足してしまい、その後のフォローや実際の調整につなげられていない現実があります。たとえば「大丈夫?」と聞いたあとに、部下が「実は業務量が多くて……」と答えても、「でも他の皆も大変だから頑張ってね」で終わってしまうようなケースです。上司は「部下を気にかけて声をかけた」と思っているのに、部下には「上司に相談しても何も変わらなかった」と映る。このすれ違いが積み重なると、部下は「どうせ相談しても意味がない」と考えるようになります。
研修の場でも「自分はできているはず」と考えている上司は少なくありません。認識のずれを実感してもらうために、ラインケア研修の最初に匿名の社員アンケート結果を紹介することがあります。「相談しても何も変わらなかった」「形だけの声掛けに感じた」といったコメントを見てもらうことで、「自分はできているはず」と思わずに研修を受けてもらった方が行動変容につながると考えています。
2.ケース①:不調者が続いた部署で見えた上司の課題
■執筆
大林 知華子(産業医、精神科専門医・指導医、労働衛生コンサルタント)
Actwith株式会社 代表取締役
大阪出身、大阪在住。
滋賀医科大学出身、北里大学で精神科後期研修修了。
精神保健指定医、精神科専門医・指導医。
第1子出産を機に大阪に帰省し、精神科病院に勤務しながら嘱託産業医として活動を開始。第3子出産後は産業医としての活動に重点を置き、現在は製造業、情報・通信業、人材派遣業、レジャー業など、約20社の産業医を務めている。