【ウェビナーへのご質問に回答】伝わる!記憶に残るメンタルヘルス研修の設計と実践
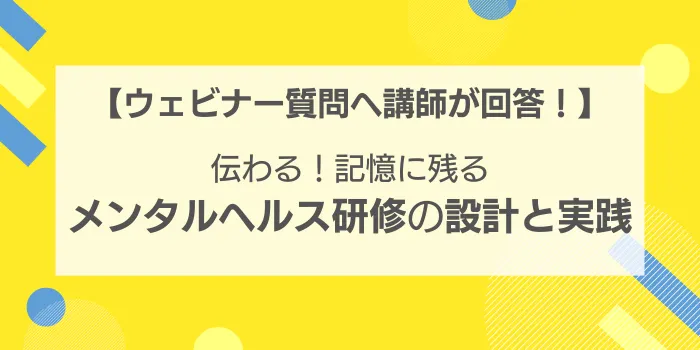
多くの企業でセルフケア研修やラインケア研修が行われていますが、「伝わっていない」「形だけ」と感じる声も少なくありません。2025年5月29日のさんぽLABウェビナーでは、こうした課題に応える研修設計や伝え方の工夫が紹介されました。
▶ウェビナー動画「伝わる!記憶に残るメンタルヘルス研修の設計と実践」
ウェビナー内でお答えしきれなかった質問について、講師の平野井啓一先生にご回答いただきましたので本記事にて紹介させていただきます。
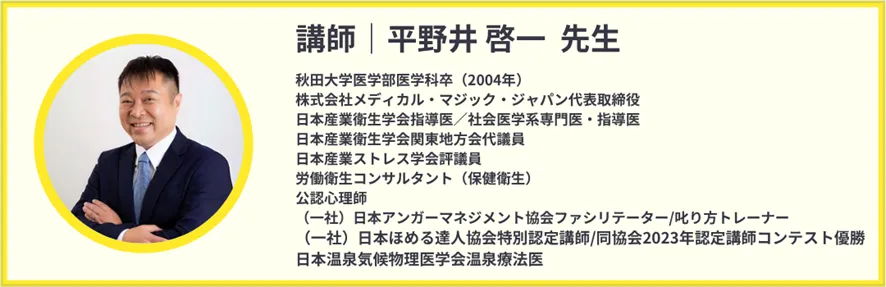 目次
目次
1. 講師としての伝え方・工夫
2.構成の工夫や注意点
3.セルフケア・ヘルスリテラシー向上
4. 効果検証
5.発達障害への配慮
6.具体事例
1. 講師としての伝え方・工夫
質問①
メンタルヘルスの研修というと、マイナスなイメージ(暗い話、難しい話、いつも決まった話、今の自分には関係のない話)と思われがちかと思います。少しでも興味がでる内容・ポジティブなイメージの研修とするために、先生が工夫している点がありましたら、教えてください。
■回答
おっしゃる通り、メンタルヘルスの研修は「暗い話」「難しい話」「自分には関係なさそう」といったイメージを持たれがちです。特に、あまり悩んだ経験のない方にとっては、距離を感じるテーマかもしれません。
ですので私は、いきなり「マイナスをゼロに戻す話」(たとえばうつ病の解説や休職事例など)から入るのではなく、「ゼロからプラスへ」「プラスをもっと増やすには?」という視点でスタートするようにしています。
たとえば睡眠をテーマにするときも、「不調のサイン」として取り上げるのではなく、「良質な睡眠をとると、仕事のパフォーマンスがこれだけ上がる!」というワクワクする入口から入ります。そこから「ではどうすればよく眠れるのか?」と関心を広げ、最後に「それでも眠れないときは、心が疲れているサインかも」といった形で、自然にメンタル不調の話題へつなげていくようにしています。
また、うつ症状の説明をするときには、「二日酔いの朝の感覚を思い出してください」とお伝えすると、具体的にイメージしやすくなります。
一見関係のないような身近なテーマと、メンタルヘルスの共通点をかけ合わせながら、「あ、自分にも関係あるかも」と思ってもらえるように、日々工夫しています。
質問 ②
セルフケアについて、感情が動くような話の内容や例え話など、先生が研修等で話した具体例など知りたいです。なかなかセルフケアの必要性は、メンタルが悪化したあとでないと自分事としてとらえてもらいにくいです。
■回答
ご指摘の通り、セルフケアの重要性は、調子を崩して初めて「大切だったのだ」と気づかれることが多いです。そのため私は、できるだけ“感情に訴える”話や例えを入れて、セルフケアを「今この瞬間から大事にしたくなること」として伝えるようにしています。
まず、前回の話とも共通しますが、「マイナスをゼロに戻す」より、「プラスをもっと増やす」視点で話すのが一つの工夫です。
そして私は、どんな忙しい人にも「一日5分、自分のためのセルフケア時間を取ってください」とお伝えしています。
そのうえで、「もし5分も取れないような毎日を過ごしているとしたら、その仕事は辞めた方がいいと思います。」と、あえて強めの言葉も使います。
というのも、体が疲れたときは「お風呂に入ろう」「ストレッチしよう」「早めに寝よう」と“ケアしよう”としますよね。
でも、心が疲れたときには「寝て忘れて、なかったことにしよう」と、ケアを飛ばしてしまう人が多い。
しかし、残念ながら“なかったこと”にはなりません。その積み重ねが、ある日突然メンタル不調という形で表れてしまいます。
だからこそ、セルフケアは“調子が悪くなってからのもの”ではなく、“毎日の生活の中に当たり前に組み込むべきもの”なんだ、と伝えるようにしています。
また、もし私自身に伝えられる経験がある場合には(もちろん重くならない範囲で)、その一部を開示することもあります。「あ、自分と同じようなことで悩んだ人がいるんだ」と感じてもらえることで、セルフケアの必要性をよりリアルに捉えてもらえることがあるからです。
質問 ③
研修で具体的な事例を紹介する時の注意点はありますか?
■回答
まず第一に、自分以外のエピソードを扱う場合は、必ず個人が特定されないよう配慮しています。とくに許可を得ていないケースでは、年齢や職種、エピソードの細部などもぼかして伝えるようにしています。
そしてもう一つ大事にしているのは、「演技に力を入れすぎないこと」です。
もちろん、話し手の熱量や表現力も大切なのですが、それよりも「聞き手の頭の中に、同じ情景や状況が思い浮かんでいるか」に気を配っています。
たとえば、「朝、出勤前に上司からLINEが…」といったように、できるだけ具体的な場面設定を丁寧に描くことで、聞いている人の中に共通のイメージが生まれます。
その共有こそが、感情の動きや気づきにつながると感じています。
事例紹介は「語り手のドラマ」ではなく、「聞き手のリアルな体験」として感じてもらえるかどうかが大切だと思います。
2. 構成の工夫や注意点
質問④
製造業で生産優先となりなかなか職場を抜けて教育を実施することが難しいです。そのためついつい詰め込み授業のような研修になっていたなと反省しました。今後現場の負担を軽減するためオンデマンド教育も検討していますが、構成を考える際にここは気をつけておくと良いというポイントはありますか?グループワークの内容は検討すれば良いでしょうか?
■回答
製造業の現場では、ラインを止めてまで研修に参加するのが難しいことが多いですよね。
さらに交代制勤務も重なると、全員が一度に集まるのはほぼ不可能。実際、同じ事業場で1日に3〜4回同じ内容の研修を行ったこともあります。
そんな現場では、オンデマンド型の研修は非常に有効な選択肢だと思います。
ただし、オンデマンドにはリアル研修とは異なる難しさもあります。録画視聴だと「参加した感」がどうしても薄くなりがちで、ながら視聴になってしまうことも…。
ですので私は、受講後のアンケートを丁寧に取ることを重視しています。
・内容が伝わったか
・どこでつまずいたか
・今、職場で困っていることは?
といった問いを設けて、個別のコメントにはきちんと返信するようにしています。
また、個人的な経験からも、「一回の動画を短く分ける」ことで視聴率が上がると感じています。10分×3本など、分割形式で組むと“今なら1本見ようかな”と思ってもらいやすくなります。
グループワークについては、条件が整えば入れてもよいですが、私は基本的に汎用性を重視して、入れないことが多いです。視聴環境がバラバラな場合、グループワークの再現性や参加のしやすさがどうしても低くなってしまうからです。
3. セルフケア・ヘルスリテラシー向上
質問⑤
メンタルセルフケアの底上げとして、社員のヘルスリテラシーを向上させるにはどのような対策を行うのが効果的でしょうか?
管理職へのラインケア教育だけでなく、管理職自身のセルフケアにはどのような教育が良いかと思われますか?
■回答
まず、社員のヘルスリテラシー向上に向けた対策は、「今その組織のどこに課題があるのか」によって変わってくると思います。
もしメンタル不調者が増加傾向で、全体的にリテラシーが低いと感じられる場合は、まずは”2次予防”(早期発見・早期対応)を優先的に整えることが重要です。
そのうえで、並行してハラスメント対策や不調サインの気づきなど、職場の安心感に直結するテーマを取り入れていくと効果的です。
一方で、ある程度の土台がある組織であれば、今度は1次予防の観点から、「より元気に働けるための工夫」や「ウェルビーイング」向上をテーマに、ポジティブな話題も交えた研修を行うのもおすすめです。
そこにコミュニケーションや感情理解の研修を組み合わせると、全体の空気がぐっと柔らかくなる実感があります。
そして管理職のセルフケアについてですが、ここは本当に多くの企業から相談をいただきます。
ただ正直なところ、「これが正解です」という完璧なプログラムは、私自身もまだ模索中です。
ただひとつ確かに言えるのは、「管理職も人間である」という視点を持つことが出発点だということです。
つい「できて当たり前」「上だからこそ我慢して当然」と見られがちな立場ですが、どんなにタフな人でも、認められたい・共感してほしいという思いはあります。
ですので私は、制度的な教育と並行して、あなたの頑張りを見ていますという言葉を経営層から届けることを、強くお勧めしています。
メンタルヘルスの取り組みを企画する際には、そうしたトップメッセージの発信もぜひ含めて設計していただけると、管理職の方々の気持ちにも寄り添えるのではないかと思います。
4. 効果検証
質問⑥
行動変容に繋がったかどうかの効果検証は何を使っておられますか?よろしければ教えていただけないでしょうか。
■回答
これは本当に難しいですよね。講義や施策がその場で好評でも、「実際に行動が変わったかどうか」を追うのはなかなか簡単ではありません。
私自身の現場では、いくつかの方法を組み合わせて効果を見ています。
たとえば、ストレスチェックでの変化を参考にすることがあります。
・高ストレス者の割合の推移
・集団分析における「上司の支援」や「職場の一体感」などの項目の経年変化
などをチェックして、「職場環境として何かが改善してきているか?」を定点観測的に見ています。
また、研修後すぐの満足度アンケートだけでなく、2〜3ヶ月後にあらためて受講者にアンケートを実施し、
・実際に試してみたか?
・自分の中で何が変わったか?
といった“行動変容”に近い視点で振り返ってもらうのも、ひとつ面白いやり方だと思います。
必ずしも数値で完璧に捉えられなくても、「変化の芽」があるかどうかに気づく工夫を少しずつ取り入れるようにしています。
5. 発達障害への配慮
質問⑦
発達障害についての研修のしかけについてアドバイスいただきたいです。診断はついていなくとも特性が濃い部分で業務に体調に影響が出ている、まだまだ発達障害のテーマについて理解度を高める仕掛けのハードルを感じます(脳機能の特徴の濃淡だけのもので誰しもがあるもの、などポジティブに捉えて、強み・苦手をうまく捉えて、セルフケア、相互の支え合い)
■回答
確かに、とても難しいテーマですよね。発達障害そのものを正確に理解してもらうのは簡単ではありませんし、「自分とは関係ない」と捉えられてしまうこともあります。
そのため私は、まず事例やストーリーを使って伝えることを大切にしています。特性の名前や診断名から入るのではなく、
「こんな場面で、こんな風に困っている人がいたらどう思いますか?」
という問いかけから始めることで、共感をベースにした理解が生まれやすくなります。
また、研修の中で取り入れやすい教材として、「障害者雇用マニュアル・コミック版(No.1〜6)」のシリーズがあります。
特に「No.5」は発達障害に関する内容がわかりやすく、職場での支援のあり方や特性理解に活用しやすいツールだと思います。
https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/manual/emp_ls_comic.html
個別対応が必要な場面では、主治医の診断、知能検査の結果、ジョブコーチの助言などを参考に、就労条件の調整を行いますが、集団向けの研修では、あまり細かく医学的な話をしすぎないことも大切だと思います。
その代わりに、研修の目的を「特性や困りごとが“あるかも”と気づけること」「困っている人を見かけたとき、声をかけてみようと思えること」に設定すると、参加者にとっても実感がわきやすくなります。
そのため私自身がいつも意識しているのは、
「就業においてうまくいかずに悩んでいるケースがあったときに、研修の内容を思い出して相談してもらえるようになる」というゴールを設定することです。
つまり、「あのとき聞いた話って、もしかしてこのことかも」「ちょっと相談してみようかな」と思ってもらえることが、研修の一番の価値だと考えています。
強みと苦手は誰にでもあるもの。特性を“障害”と捉えるより、「違い」として理解し、どう支え合えるかを一緒に考える時間にすることを目指しています。
6. 具体事例
質問⑧
弊社では、休職者に対して、上司が月1回連絡を取るというルールになっているのですが、上司との人間関係が原因で休職している場合、どうすれば良いか悩んでます。また、連絡頻度も月1番で良いのか、悩んでます。何かアドバイス頂けますと幸いです
■回答
ご相談のように、休職のきっかけが上司との人間関係にある場合は、原則ルールとは別に例外の対応を柔軟に設ける必要があると考えます。
このような場合には、上司からの直接連絡を避け、人事や保健師・産業看護職などの第三者が窓口となる体制を整えることで、復職までの過程がぐっとスムーズになります。
その際、上司の方には「原因があなたです」といった伝え方はせずに、
「本人としては現在、そのように感じているようです」
「今は少し距離をとる方が、安心して療養に専念できるとのことです」
といった客観的かつ丁寧な説明を人事から行うのが望ましいと思います。
また、連絡頻度についても一律に“月1回”とせず、病状や本人の状態に応じて柔軟に対応していくことが重要です。
参考までに、他社で実際に行われている例をご紹介します:
日々の体調報告(メールで数行:元気です/眠れています、など)
→ 週3〜5回程度
電話やオンライン面談(20〜30分ほどの近況確認)
→ 週1回程度
主治医の受診日、病状変化、産業医面談などの節目
→ 必要に応じて随時対応
このように、「頻度」だけでなく「連絡手段」や「やり取りの密度」を調整することで、本人にとっても負担の少ない関わり方が可能になります。
状況に応じて適切な伴走役を配置し、“安心して戻ってこられる環境づくり”ができれば、復職支援としても非常に効果的だと思います。
ご相談のように、休職のきっかけが上司との人間関係にある場合は、原則ルールとは別に例外の対応を柔軟に設ける必要があると考えます。

講師 |平野井 啓一 先生(産業医)
秋田大学医学部医学科卒(2004年)
株式会社メディカル・マジック・ジャパン代表取締役
日本産業衛生学会指導医/社会医学系専門医・指導医
日本産業衛生学会関東地方会代議員
日本産業ストレス学会評議員
労働衛生コンサルタント(保健衛生)
公認心理師
(一社)日本アンガーマネジメント協会ファシリテーター/叱り方トレーナー
(一社)日本ほめる達人協会特別認定講師/同協会2023年認定講師コンテスト優勝
日本温泉気候物理医学会温泉療法医
温泉ソムリエ
卒業後、臨床研修を経て産業医学の道を志す。きっかけは「病気を治すのも医者の仕事だが、病気にならないようにするのも医者の仕事」という指導医の一言。働くことで不幸になっていけないという理念のもと、SBS東芝ロジスティクス株式会社本社統括産業医、他約20社の嘱託産業医を務め、また指導医として後進の指導・育成にも力を注いでいる。
昨今急増する職域のメンタルヘルス問題について、感情のコントロール手法としてのアンガーマネジメント研修やほめる管理職研修等、産業医学をベースに様々な分野の知見を取り入れた研修は好評を博し、講演依頼も年々増加。産業医活動の傍らで年間60回以上多くの人の前に立ち、情報を発信している。
また副業でマジシャンとして多くの人にサプライズと笑顔を届けている




