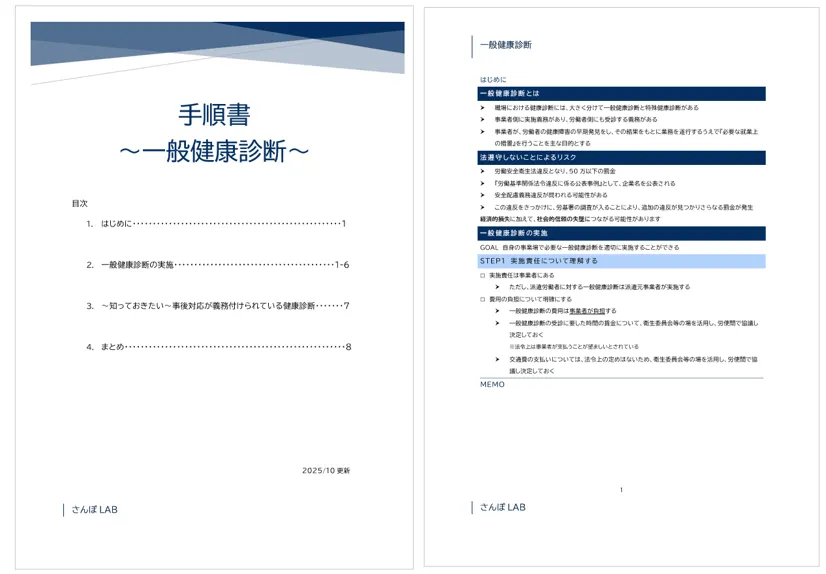職場における健康診断とは、労働衛生の3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)のうち、健康管理の一部として行われます。健康診断は大きく、一般健康診断と特殊健康診断の2つに分類されます。労働安全衛生法における一般健康診断とは、常時使用する労働者の一般的な健康状態を調べるための健康診断のことです。ここでは、一般健康診断についてご説明いたします。
STEP 1 チェックリストで職場の課題を可視化
STEP 2 解説を読んで根拠や活用できるコンテンツをチェック
STEP 3 手順書をダウンロードして体制づくり
STEP 1 チェックリストで職場の課題を可視化
STEP 2 解説を読んで根拠や活用できるコンテンツをチェック
それぞれの項目をクリックいただくと、その課題についての根拠や関連コンテンツ、活用できるフォーマット等が閲覧できるようになっております。ご自身の理解を深めるためにご利用ください。
■一般健康診断とは
■一般健康診断の種類
■健康診断の実務
■情報の取扱い
■一般健康診断に関連するその他の制度
■まとめ
■一般健康診断とは
▶目的
一般健康診断の目的は主に次の2つです。健康診断の後で企業が実施しなければいけない『事後措置』については、こちらのコンテンツをご覧ください。
① 事業者が、労働者の一般的な健康状態を把握し、その結果をもとに、安全配慮義務を適切に果たすために、業務を遂行するうえで必要な就業上の措置を行うこと
② 労働者自身が、健康への関心を高めること
▶健康診断の実施義務
安全配慮義務の観点から、事業者は、労働者に対して必要な健康診断を実施する義務があります。対して労働者は、事業者が行う健康診断を受診する義務があります。
▶一般健康診断の実施方法
健康診断の実施については、外部の医療機関や健診機関に委託することができます。
▶一般健康診断の費用の負担
健康診断の費用は事業者が負担する必要があります。一般健康診断の受診に要した時間の賃金については、労使協議により定めるべきものとされていますが、事業者が支払うことが望ましいとされています。(昭和47年9月18日基発第602号)
健康診断の受診にかかる交通費を誰が支払うべきかどうかについては、法令では特に定められていません。そのため、交通費の支払いについては、衛生委員会等の場を活用し、労使間で協議して決めることが必要です。
派遣労働者の一般健康診断については、雇用主である派遣元の事業者に、実施・管理の責任があります。
■一般健康診断の種類
実施が事業者に義務付けられている健康診断は大きく5つに分類されます。
健康診断の種類や項目によっては、医師の判断で省略や変更が可能なものもあります。ただし、年齢等で一律に省略するのではなく、労働者ひとりひとりの過去の健康診断結果などを参考に、医師が個別に判断する必要があります。

参考:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう|厚生労働省
▶雇入時の健康診断(安衛則43条)
事業者が常時使用するすべての労働者に対して雇入れたときに必ず行う健康診断です。目的は、労働者の適正配置です。つまり、入社後に担当させる業務を行わせて良いかどうか、健康診断結果から判断する必要があります。健康診断項目の省略はできません。受診時期は、基本的には採用決定後に行います。目安としては、就労開始前3か月から直後とされています。本人が、3か月以内に受診した必須の項目を網羅した健康診断結果を事業者に提出した場合は、雇入時の健康診断を省略することができます。
また雇入時の健診を受けてから1年以内であれば、定期健康診断を省略することも可能です。
▶定期健康診断(安衛則44条)
定期健康診断は、事業者が常時使用するすべての労働者に対して1年以内毎に1回行う健康診断です。かつては結核の発見を主な目的としていましたが、労働者の高齢化や労働環境の変化により、健康診断の目的は、生活習慣病・作業関連疾患対策に変わってきています。
定期健康診断ではそれぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは健康診断の項目の省略が可能です。ただ、年齢等で一律に項目を省略することはできず、過去の健康診断結果などを参考に、医師がひとりひとりの労働者について個別に判断することが必要です。
▶特定業務従事者の健康診断(安衛則45条)
安衛則第13条第1項第2号で定められた特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際、および6か月に1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施することが、義務付けられています。また胸部X線検査については、定期健康診断とあわせて1年以内に1回毎に定期に行えば足りるとされています。
▶海外派遣労働者の健康診断(安衛則45条2)
海外派遣労働者に対する健康診断は、派遣前と帰国時の2種類が、定められています。海外派遣前
事業者は労働者を6か月以上海外に派遣しようとするときには、あらかじめ健康診断を実施しなければなりません。健康診断の項目としては、定期健康診断の項目に加え、医師が必要と判断した場合は、腹部画像検査(胃部X線検査、腹部エコー検査)・血中の尿酸の量・B型肝炎ウイルス抗体検査・ABO式およびRh式の血液検査を実施する必要があります。
海外派遣後
事業者は労働者を6か月以上海外に派遣した後、国内の業務に従事させる際に健康診断を実施しなければなりません。健康診断の項目としては、医師が必要と判断した場合は、派遣前の健康診断のABO式血液型の代わりに糞便塗抹検査を実施する必要があります。
| 【補足】 海外派遣労働者は海外派遣前後の健康診断の規定があるだけで、その他、定期健康診断や特殊健康診断などについて、法令では定められていません。そのため、長期間海外で労働している場合、健康確認の機会がほとんど失われてしまうことになってしまいます。事業者の安全配慮義務の観点からは、労働者の健康状態を確認することが望ましいといえるため、健康診断の受診について社内規程等で定めておくことをおすすめします。 |
▶給食従業員の検便(安衛則47条)
事業場にある食堂または炊事場における給食の業務に従事する[※注釈1]労働者に対し、食中毒、伝染病の観点から、雇入れや配置換えの際に検便による健康診断を行わなければいけません。一般的には、感染症法における3種類感染症に分類される、赤痢菌、サルモネラ属金(チフス菌、パラチフスA菌を含む)、腸管出血性大腸菌(O-157、O-26、O-111)の健康保菌者の検索を目的に実施します。| ※注釈1.一般消費者に食事を提供する飲食業の厨房等で働く労働者に対しては、食品衛生法や大量調理施設衛生管理マニュアル等での検査が義務付けられている |
▼おすすめ学習コンテンツ▼

■健康診断の実務

※意見聴取、事後措置、医師または保健師による保健指導については、こちらのコンテンツをご覧ください。
▼健康診断事後措置▼
▶健康診断の実施
自身の事業場内で実施が難しい場合は、外部医療機関に委託する必要があります。委託する際には価格や項目だけでなく、個人情報の取扱い、役割分担についても取り決めることが重要です。法令で定められた対象者を把握するとともに、法令の範囲外となる人を対象に含めるか等は、事業場内であらかじめ決めておくことが重要です。
また、健康診断の項目についても法定外の項目を含めて実施することもあります。その場合はあらかじめ、事業場内のニーズにより、項目の追加等を産業保健スタッフ中心に検討することも求められます。衛生委員会等の機会を活用し、審議するとよいでしょう。
法定外の検査項目を実施する際には、個人情報保護法に基づき、法定外項目の検査結果の情報を企業が取得することについて、利用目的の説明や事前の同意取得などが必要です。
▶健康診断結果の受領
健康診断結果は、個人情報であるため適切に管理する必要があります。しかし、健康診断を実施すること、その結果を保存すること、結果を確認し業務上必要な措置をとることは、法令に基づく行為です。そのため、法定の検査項目に限り、事業者は本人の同意なく健康診断の結果を取得することができます。ただし、法定外の検査項目を取得することについては、前述のとおり、本人の同意を得ることが必要です。
▶本人への結果の通知
事業者は、健康診断の結果を受領後、遅滞なく本人に健康診断の結果を通知することが義務付けられています。(安衛法66条6項、安衛則51条4)▶労働基準監督署長への結果の報告
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、一般健康診断のうち、定期健康診断と特定業務従事者健康診断の結果を所定の様式(定期健康診断結果報告書様式)にて、事業場の所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられています。(安衛則52条)▶結果の保存
事業者は、健康診断の結果を受領後、それぞれの労働者の個人票を作成し、5年間の保存が義務付けられています。(安衛法66条3項、安衛則51条)また、労働者から自発的健康診断の結果が提出された場合も同様に5年間の保存が義務付けられています。(安衛法66条3項)
医師、または歯科医師から聴取した意見も個人票に記入する必要があります。
(安衛法51条2項)
▶事後措置
健康診断の結果、「要医療・要再検査・要精密検査」などの異常所見があると診断された労働者については、医師などに就業上の措置について意見聴取をすることが必要です。また事業者は、医師等の意見を踏まえて、必要な就業条の措置を講じ、労働者の健康保持を図る必要があります。また、健康診断結果に応じて、医師や保健師等による保健指導や受診勧奨などを行います。これらの対応を「健康診断の事後措置」と言います。※健康診断の事後措置については、こちらのコンテンツをご覧ください。
▼健康診断事後措置▼
■情報の取扱い
情報の取扱いについては、健康情報取扱規程をご参照ください。
▼法令チェック『健康情報取扱規程』▼
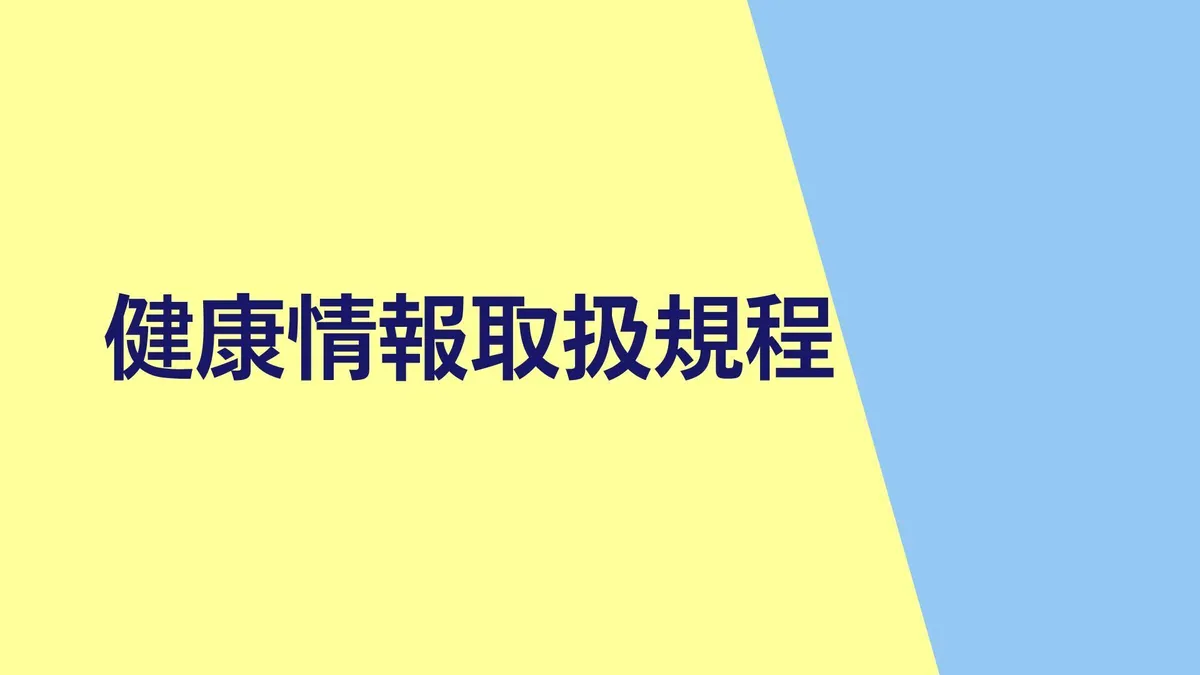
■一般健康診断に関連するその他の制度
一般健康診断に関連して、自発的健康診断と労災保険による二次健康診断の制度をご紹介します。
▶自発的健康診断
自発的健康診断とは、深夜業に従事している労働者が自分の健康状態に不安を抱いた際に、自らの判断で自発的に医療機関に行って受ける健康診断のことです。
対象者は、常時使用する労働者で、過去6か月を平均して1か月あたり4回以上深夜業に従事している者です。
自発的健康診断の結果は、受診した日から3か月以内に、労働者が自らの判断で事業者へ提出します。結果の提出を受けた事業者は、一般健康診断と同じく、結果について医師の意見を聴取し、必要に応じて事後措置を実施する義務があります。また、結果は5年間の保管が必要です。
▶労災保険による二次健康診断
労災保険二次健康診断等給付とは、定期健康診断等の職場の健康診断により、一定の条件を満たす場合に、生活習慣病に関するさらに詳しい検査を受けられる労災保険の制度です。二次健康診断の受診は本人の任意の希望によるもので、事業者の義務ではありません。
下記の(ア)~(ウ)の条件を全て満たす場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度以内に1回、無料で受診することができます
対象者は、下記(ア)~(ウ)の3つの要件があります。
(ア) 一次健康診断(定期健康診断など職場で実施した健康診断)の結果、(血圧/血中脂質/血糖/BMI・腹囲)の検査項目全てに異常がある
(イ)脳・心臓疾患の症状があると診断されていない場合
(ウ)労災保険の特別加入者ではないこと
二次健康診断の項目としては、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には下記のような検査があります。
・空腹時血中脂質検査
・空腹時血糖値検査
・ヘモグロビンA1C(一次健康診断で実施していない場合)
・負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
・頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・微量アルブミン尿検査(一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限る)
事業者が実施すべきこととしては、下記の二つがあります。
・本人が二次健康診断実施医療機関に提出する『二次健康診断等給付請求書』の事業主証明欄に記入
・二次健康診断実施後3か月以内に本人が事業者にその結果を任意で提出し、かつその結果に異常の所見がある場合、事業者は提出日から2か月以内に医師への意見聴取を行い、必要に応じ適切な事後措置を実施する。
■まとめ
一般健康診断は、疾病の早期発見・予防の目的だけでなく、就業の可否や適正配置等の判断を実施するための判断材料となります。その目的を、事業場側だけでなく労働者にも理解してもらうことが大切です。健康診断は、労働者の健康状態を知り、職場の健康づくりをすすめていくための土台となりますので、その機会を最大限活用できるようにしましょう。
▼おすすめ学習コンテンツ▼

STEP 3 手順書をダウンロードして体制づくり
手順書には、体制づくりの進め方が記載されています。実際に体制整備を実施する際に、関連部署に提供し、一緒に体制づくりを進めるためにご活用ください。