【寒くなる前に】冬場のヒートショック・寒冷ストレス対策は万全ですか?
冬の職場環境は、ヒートショックや寒冷ストレスといった健康リスクを引き起こしやすく、労災や体調不良の原因となります。特に寒冷地や夜間・屋外作業のある事業所では、血圧変動による心疾患や脳卒中、作業効率低下による事故リスクが高まります。
本記事では、衛生管理者や産業保健スタッフが押さえておくべき「冬の職場に潜む健康リスク」と「具体的な防止対策」を解説します。従業員の安全と健康を守るために、冬場の労働安全衛生管理に役立ててください。
<目次>
1.はじめに:冬の職場に潜む体調リスク
2.ヒートショックと寒冷ストレスのメカニズム
3.事業所でできる具体的対策
4.衛生管理者が押さえるべきポイント
5.まとめ:冬場の体調リスクに「事前の備え」が安全を守る
1.はじめに:冬の職場に潜む体調リスク
朝晩の冷え込む時間や、寒冷地にある事業所や工場などでは、作業環境が厳しい寒さにさらされることで、労働者の健康リスクが高まり、冬場の体調不良を訴える労働者が多くなります。
外気温が低くなると体温維持のために血圧や心拍数が上昇し、体への負担が大きくなります。これを「寒冷ストレス」と言います。寒冷ストレスによって、冷えやだるさ、肩こり、頭痛、不眠、自律神経の乱れなど、様々な体の不調を引き起こす可能性があります。
さらに、暖かい場所から急に寒い場所へ移動したり、その逆を繰り返したりすることで、急激な血圧変動を引き起こす「ヒートショック」の危険性も高まります。これは心筋梗塞や脳卒中など命に関わる症状を引き起こす可能性があり、特に高齢労働者にとって深刻な健康リスクとなります。
また、労災の観点でいうと、冬場の低温による作業効率の低下や判断力の鈍化、指先の操作性低下などが原因となり労災につながる事例も多く報告されています。
寒さで身体が強張ると、転倒や挟まれ事故、手指の切創といった外傷のリスクも増加します。衛生管理者としては、これらのリスクを「季節要因による一時的なもの」と軽視せず、作業環境の温度管理、防寒対策、休憩環境の確保などを計画的に進める必要があります。
近年では、省エネルギーや換気強化の観点から室温を低めに設定する事業所も増えていますが、その分、寒冷ストレスやヒートショック労災の可能性は高まります。
早朝や夜間勤務、屋外作業を伴う職場では特に、寒さによる体調不良の予防策を事前に講じることが、労働者の健康と安全を守る第一歩となります。
2.ヒートショックと寒冷ストレスのメカニズム
前述したように、冬場の職場環境で注意すべき代表的な健康リスクが「ヒートショック」と「寒冷ストレス」です。これらは同じ“寒さ”を原因としますが、体内で起きている反応には明確な違いがあります。
【ヒートショック】
急激な温度差によって血圧が大きく変動する現象です。
暖かい場所から寒い場所へ移動すると、皮膚表面の血管が急速に収縮し血圧が上昇します。
逆に寒い場所から暖かい場所に移動すると血管が拡張し、血圧が急低下します。
この急変が心臓や脳の血管に強い負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中の引き金になります。
特に高齢労働者や高血圧・動脈硬化の既往がある人はリスクが高く、屋外と屋内を頻繁に行き来する作業環境では発生する可能性が増します。
さんぽLABでは、ヒートショックのメカニズムや起こさないポイントを解説した衛生講話資料を公開しております。以下よりPDF形式で無料ダウンロードできますので是非情報提供にご活用ください👇
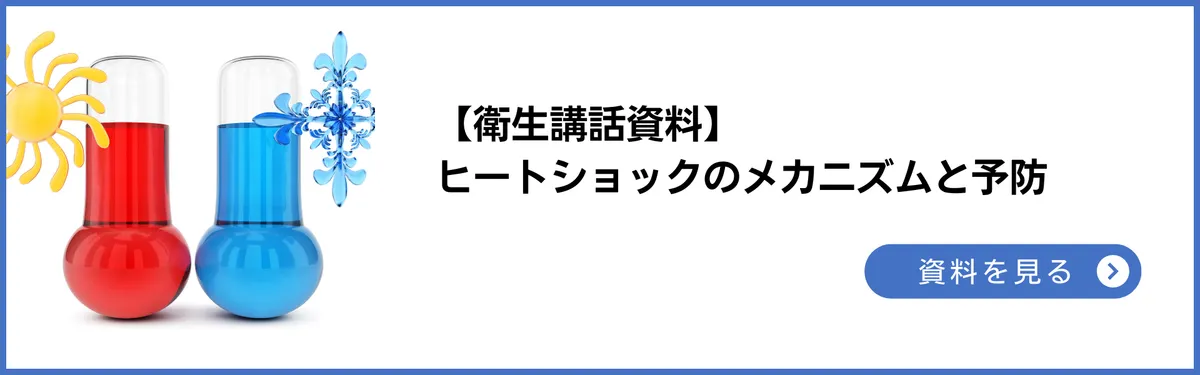
【寒冷ストレス】
低温環境そのものが体に与える長時間の負荷です。
外気温が低い環境では、体は熱を逃がさないよう血管を収縮させ、筋肉を震えさせて熱産生を高めます。この反応は一時的には体温維持に有効ですが、長時間続くと交感神経が過剰に刺激され、血圧・心拍数の上昇、代謝の増大、免疫力低下、筋肉の硬直などを招きます。
結果として疲労の蓄積、判断力低下、細かい作業のミス増加といった形で労災リスクが高まります。
重要なのは、ヒートショックは「温度差の急変」、寒冷ストレスは「低温の持続」によって引き起こされる点です。衛生管理者は、作業環境の温度管理や移動時の保温措置を組み合わせ、両方のリスクを同時に低減する対策を講じる必要があります。
3.事業所でできる具体的対策
ヒートショックや寒冷ストレスによる労災や体調不良を防ぐためには、作業環境の改善と労働者自身の行動変容の両面が重要です。
衛生管理者は事業主や安全管理者と連携し、以下の対策を組み合わせ、冬場特有のリスクが低減できるよう取り組みましょう。
【作業環境の温度管理】
室温*の適正化
事務所衛生基準規則に準じて、17℃以上28℃以下に設定する。また、事務所以外の場所でも、作業場所の気温が10〜18℃となるよう、作業内容に応じて調整する。特に暖房の効きにくい場所は局所暖房機やパネルヒーターを活用する。
*室温:工場や屋外現場を含む「作業場所の気温や室温」のこと
温度差の緩和
屋外作業や温度差の大きい場所へ移動する通路にカーテンや風除室を設置し、急激な温度変化を防ぐ。
換気計画の工夫
冷気の直接流入を避け、局所換気や短時間換気を組み合わせる。
【個人の防寒対策】
重ね着と保温素材の活用
吸湿発熱素材や断熱性の高いインナー、耳や手足を守る防寒具を支給する。または着用を推奨する。
温かい飲み物の提供
休憩所に温かい飲料を常備し、体内からの保温を促進する。
【作業スケジュールと休憩管理】
寒暖差のある移動を減らす
屋外と屋内を行き来する作業はまとめて実施し、移動回数を減らす。
短時間ごとの休憩
寒冷環境下では1時間に1回程度、暖かい場所での休憩を確保する。
高齢労働者への配慮
負担の大きい作業や夜間・早朝作業はローテーションを組み、過度な寒冷ストレスを避ける。
【教育・周知活動】
ヒートショック・寒冷ストレスの危険性を共有
朝礼や掲示板で症状や予防法を定期的に周知する。
体調申告制度の徹底
手足のしびれ、めまい、胸の痛みなど異常を感じた際はすぐに報告できる環境を整備する。
【緊急時対応】
救急対応マニュアルの整備
倒れた人を発見した際の初動対応、救急連絡手順を全員に周知する。
AED・救急セットの設置
屋外作業現場や温度変化の大きい場所にも配置する。
このように、「温度差をなくす工夫」「体を冷やさない行動」「症状を見逃さない仕組み」の3点を柱に、事業所全体で取り組むことが、冬場のヒートショック労災や寒冷ストレス対策の鍵となります。
さんぽLABでは、ヒートショックの症状や予防のポイントを解説したリーフレットを公開しております。以下よりPDF形式で無料ダウンロードできますので社内掲示や配布にご活用ください👇
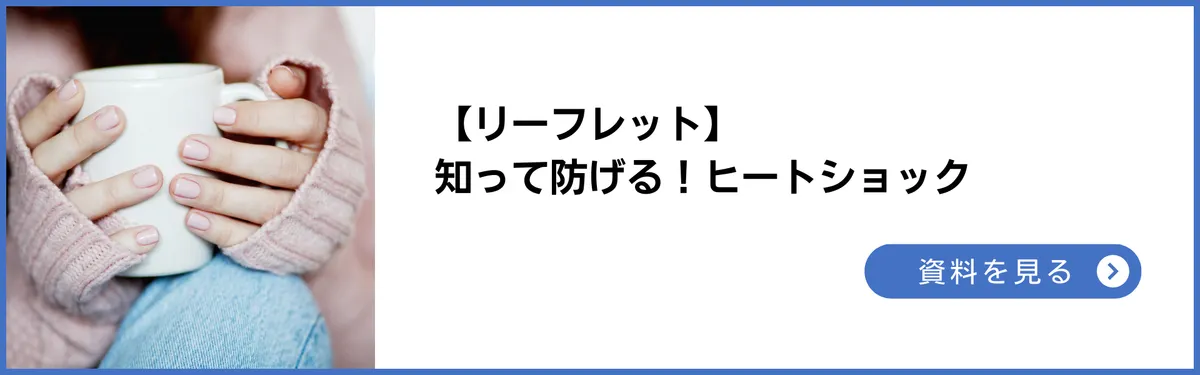
4.衛生管理者が押さえるべきポイント
前述した具体的対策を実行に移すうえで、衛生管理者には「現場に密着し、運用を定着させる」役割があります。衛生管理者は、現場と経営層をつなぎ、日々の観察とフィードバックで安全を守るキーパーソンとなります。以下は、その際に重要となるポイントです。
【温度管理の実効性を担保する】
温度測定と記録
暖房の効きにくいエリア、通路、屋外作業場の温度を定期測定し、データ化する。
改善要否を安全管理者や事業主に報告する。
温度差の確認
屋外・屋内間や建屋間の温度差を把握し、ヒートショックリスクが高い場所を特定する。
【防寒具の適正使用を徹底】
着用状況の巡視
配布した防寒具が適切に着用されているかを作業中に確認する。
サイズや機能不足があれば改善提案を行う。
使い方教育
重ね着の順番や素材の選び方、防寒具のメンテナンス方法を実演指導する。
【休憩と温熱環境の確保】
休憩実施状況の把握
寒冷作業での休憩が計画通り取れているかを確認し、未実施が多い部署にはリーダー等を通じて是正を促す。
休憩所の環境点検
室温、暖房器具、温かい飲料の有無をチェックし、不足があれば事業主や現場リーダーの協力を得て改善できるよう検討を行う。
【高リスク者への配慮】
健康状態の事前把握
高齢労働者や持病を抱える人をリスト化(本人同意のもと)し、寒冷環境下での作業割り当てを調整できるよう、事業主や現場リーダーに働きかけを行う。
体調確認の声かけ
作業前後に体調を聞き取り、異変があれば早期対応を心掛ける。
【教育と現場浸透】
掲示・朝礼での周知
寒冷ストレスやヒートショックの注意点を定期的に発信する。
ヒヤリ・ハットの収集
寒さが関係した事例を集め、全員に共有して再発防止につなげる。
【緊急対応力の維持】
訓練の実施確認
AEDや心肺蘇生法の訓練が計画通り行われているかチェックする。
初動体制の明確化
現場で倒れた場合の役割分担・連絡経路を再確認する。
5.まとめ:冬場の体調リスクに「事前の備え」が安全を守る
冬場の職場では、ヒートショックや寒冷ストレスによる健康被害は、決して特別な事例ではなく日常業務の中で潜むリスクです。特に寒冷地の事業所や工場では、作業環境や移動経路の温度差が大きく、高齢労働者や持病を持つ人の体調悪化につながる危険性があります。
衛生管理者は、事業主や安全管理者と連携し、温度管理や休憩体制、防寒対策を事前に計画・周知・点検することが重要です。また、体調変化の早期発見と対応ルールを整えることで、万が一の事故や労災を未然に防げます。
冬の安全管理は「起きてから対応」では間に合いません。季節の変化を見越した備えこそが、職場の健康と安全を守る第一歩です。
■参考
1)高齢者の事故に関するデータとアドバイス等|消費者庁
2)冬場の住居内の温度管理と健康について|地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター
3)事務所衛生基準規則|e-GOV 法令検索
■執筆/監修
<執筆> 衛生管理者・看護師
<監修> 難波 克行 先生(産業医、労働衛生コンサルタント)
アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医
メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆。YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信。
代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』




