【頭痛】治療と仕事の両立支援ガイド
はじめに🔰
頭痛は、重大な病気のサインである可能性もありますが、多くは命に関わらない慢性的な頭痛です。これらの慢性頭痛は「一次性頭痛」と呼ばれ、代表的なものに片頭痛(※)や緊張型頭痛があります。一方で、くも膜下出血や脳腫瘍など、他の病気が原因でおこる「二次性頭痛」もあり、注意が必要です。また、片頭痛や緊張型頭痛を持つ人が、頭痛薬を慢性的に使用することで引き起こされる薬剤性頭痛も課題になっています。
※片頭痛は一般的に「偏頭痛」と表記されることもありますが、本資料では医学用語に基づき「片頭痛」と記載しています。
日本では、片頭痛の患者数が約800万人、緊張型頭痛は2000万人以上と推測されており、多くの人が日常的に頭痛に悩まされています。これらの頭痛は業務のパフォーマンスを低下させ、プレゼンティーズム(出勤しているが生産性が落ちている状態)の大きな要因にもなります。
このような状況を背景に、2021年には健康経営度調査の「従業員への教育に関する項目」に「片頭痛・頭痛」が追加されています。つまり、企業において、従業員の頭痛対策に積極的に取り組むことが求められています。
本コンテンツでは、頭痛についての基本的な知識と、職場で配慮すべきポイントについて解説します。
頭痛とは
◆頭痛と受診
◆一次性頭痛と二次性頭痛
◆一次性頭痛の種類
◆一次性頭痛の治療
◆薬剤性頭痛
頭痛と就業
◆就業において確認すべきこと
◆治療と就業における配慮の例
▼詳細なマニュアルはこちらから!

※アンケート回答の最後にダウンロードURLがありますので取得ください。
まとめ
頭痛は、自分自身の頭痛の特徴を理解し、種類、程度に合わせた対応を行い、薬物療法を中心とした治療を継続することが重要です。市販薬などで症状がコントロールできない場合には、頭痛専門外来の受診も勧めましょう。
頭痛を抱える労働者は非常に多く、さらにパフォーマンスの低下に直結するため、プレゼンティーズムを引き起こす大きな要因となります。健康経営度調査にも頭痛の項目が追加されていることからもわかる通り、企業にも対策が求められています。
産業保健スタッフには、頭痛について正しい知識を持ち、個々に合わせた対応方法について、事業場とともに考えることが求められます。
本コンテンツでは、こうした支援のポイントをわかりやすくまとめています。今後の取り組みにお役立ていただける内容ですので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
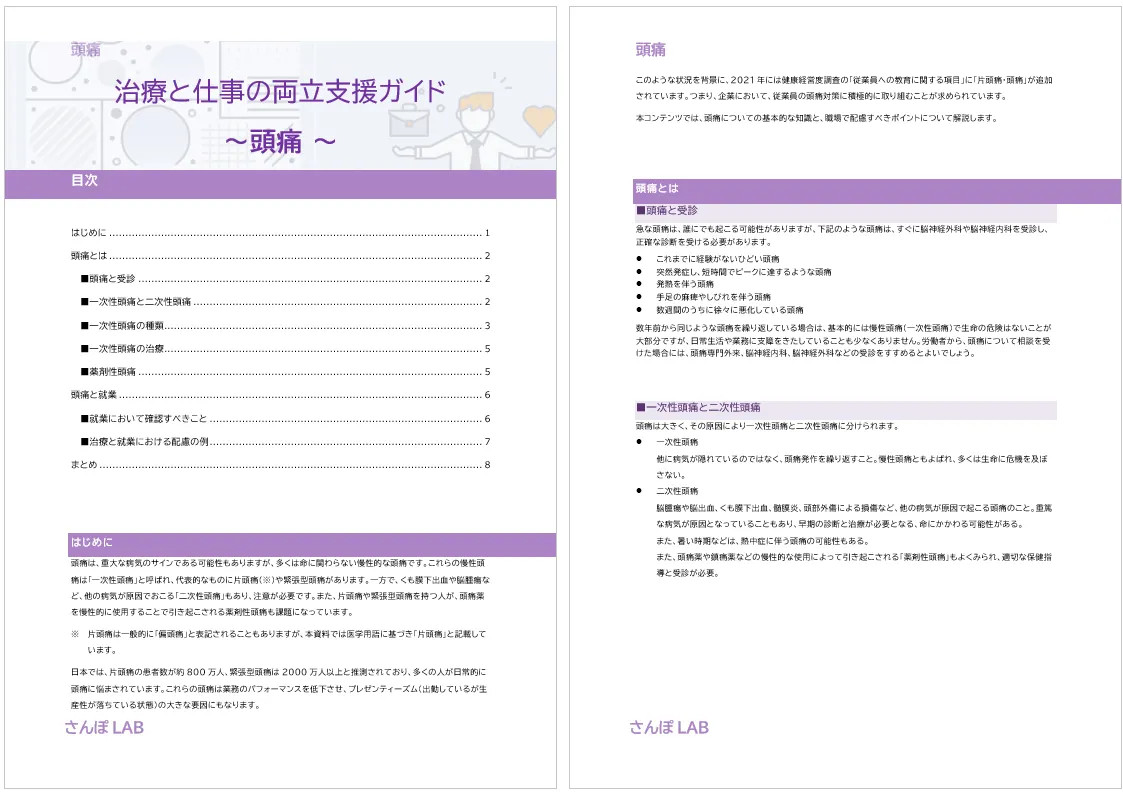
▼両立支援ガイドのダウンロードはこちらから!

※アンケート回答の最後にダウンロードURLがありますので取得ください。




